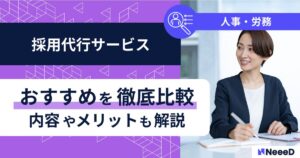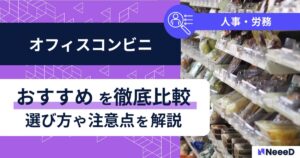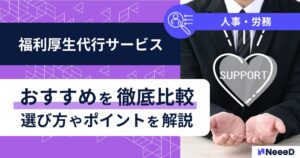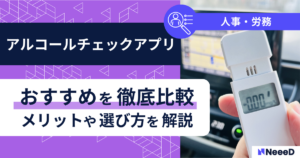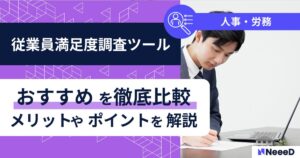【2025年6月最新】労務管理システムおすすめ6選を比較!事業規模に合った選び方も解説
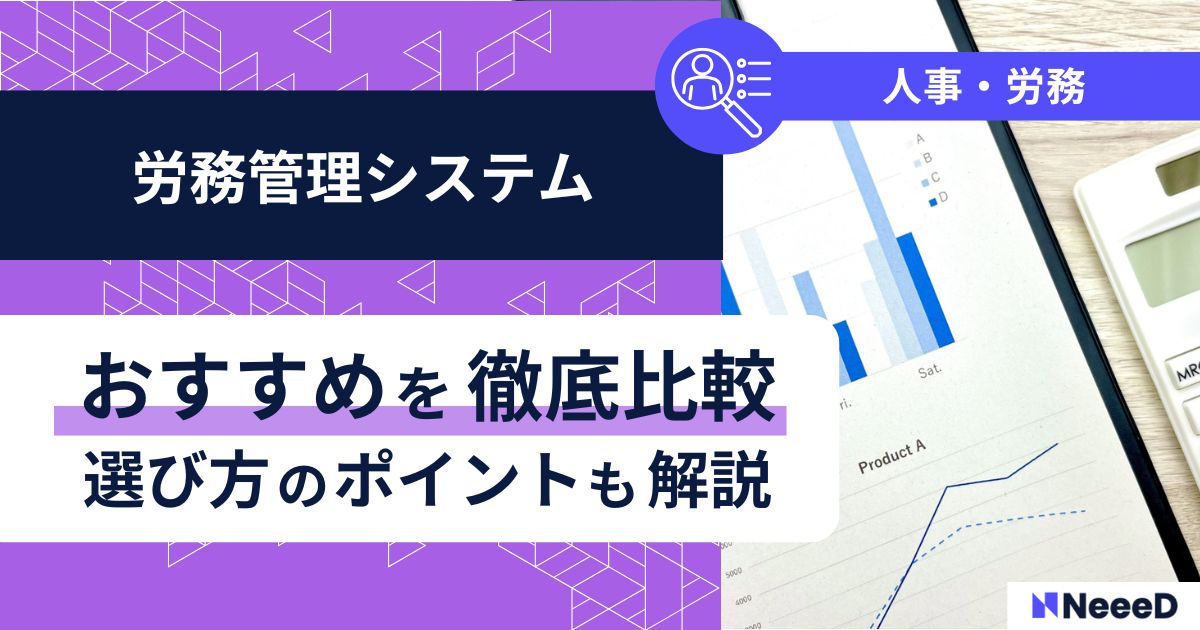
「給与計算や社会保険手続きの負担を軽減したい」と感じている方にとって、労務管理システムの導入は大きな助けになります。
業務の煩雑さやヒューマンエラーのリスクを減らすうえで、適切なシステム選定は欠かせません。
しかし、「どの労務管理システムを選べば良いか分からない」と考える方も多いでしょう。
当記事では、おすすめの労務管理システムや比較する際のポイントを紹介します。事業規模に合った労務管理システムの選び方やタイプ、機能や導入メリット・デメリットなどについても解説しているので、製品の選定で迷っている方はぜひご覧ください。
労務管理システムおすすめ6選
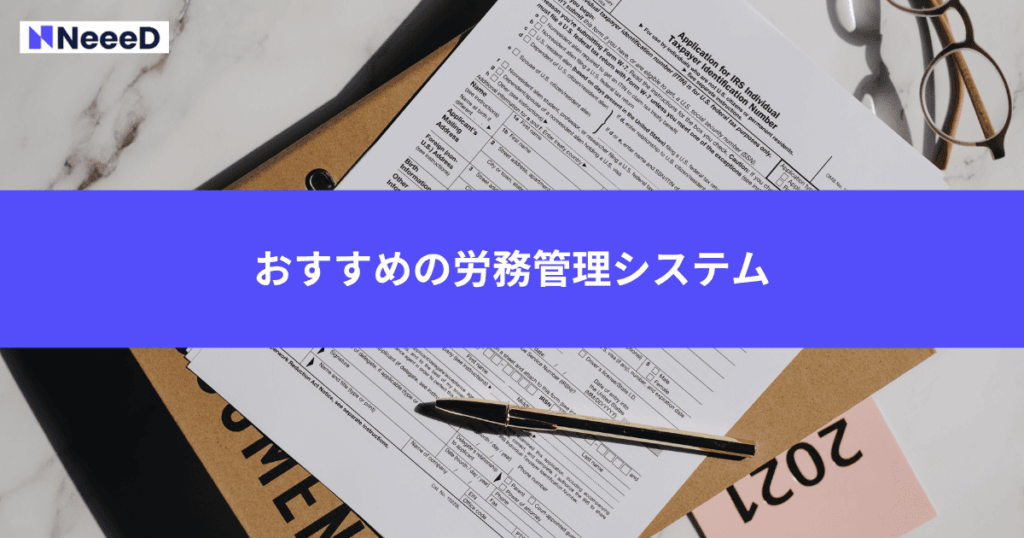
当記事でおすすめの労務管理システムを6つ紹介します。
| おすすめの労務管理システム | 特徴 |
|---|---|
| SmartHR労務管理 | 30人までなら無料で利用可能 |
| freee人事労務 | 他のfreee製品や外部サービスと連携可能 |
| ジョブカン労務HR | 初期設定の代行オプションが特徴 |
| fapi | エンジニアに特化した労務管理システム |
| Chat&Messenger | ビジネスチャットやWeb会議機能を1つのプラットフォームで提供 |
| アイピア | 建築業界に特化したクラウド型業務管理システム |
それぞれ異なる強みを持つので、導入時の参考にしてください。
SmartHR労務管理

| 料金プラン | 要問い合わせ(30名まで無料) |
|---|---|
| 機能 | 勤怠管理機能 給与計算機能 入社手続き機能 年末調整機能など |
| タイプ | クラウド型の機能拡張が可能なタイプ |
| 導入実績 | ファイテン株式会社 日野グローバルロジスティクス株式会社 株式会社すかいらーくホールディングスなど |
| 会社所在地 | 〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
SmartHR労務管理は、クラウド上で労務管理を一元管理できるサービスです。プランによって基本的な労務管理からタレントマネジメントまで対応可能で、自社の目的に合わせて選べます。
また、従業員50名以下の企業に向けた労務管理機能に特化したプランや、30人までの従業員情報を管理できる無料プランも用意されており、小規模な企業であればコストを抑えた運用が可能です。
従業員自身がスマホなどから直接情報を入力・更新できるため、労務担当者だけでなく従業員にとっても利便性が高くなっています。すでに7万社以上が導入している実績からも信頼性が高く、実績重視で導入するシステムを選びたい企業にもおすすめです。
freee人事労務
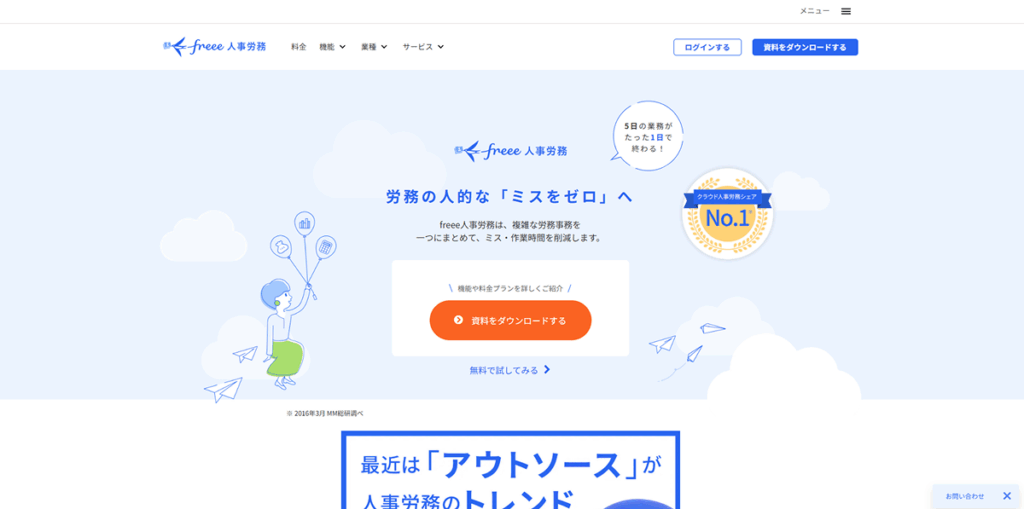
| 料金プラン | 月額400円/名~ |
|---|---|
| 機能 | 勤怠管理 給与計算 年末調整 行政手続き人事マスタなど |
| タイプ | クラウド型の多機能タイプ |
| 導入実績 | WHITE CROSS株式会社 株式会社佐竹製作所 ホーセック株式会社など |
| 会社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 |
freee人事労務は、給与計算や勤怠管理、年末調整、マイナンバー管理といった労務業務を1つのプラットフォームで完結できるシステムです。業務ごとにシステムを切り替える必要がないため、入力の重複や管理ミスを削減できます。
また、freee会計など他のfreee製品や外部サービスとの連携性も高く、データの自動反映によって人的作業の負担を大幅に軽減することが可能です。
法令対応を含むアップデートも迅速に行われており、最新のセキュリティのもとで個人情報を安心して扱える環境が整っています。日々の労務業務を効率化しながら、法令遵守や情報保護にも配慮した運用を行いたい企業におすすめです。
ジョブカン労務HR

| 料金プラン | 初期費用:無料 月額利用料:0円~ |
|---|---|
| 機能 | 書類作成・電子契約機能 人材管理機能 ストレスチェック機能 マイナンバー管理機能など |
| タイプ | クラウド型の多機能タイプ |
| 導入実績 | 株式会社エストレージ 株式会社石橋楽器店 築地本願寺など |
| 会社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階 |
ジョブカン労務HRは、あらゆる労務手続きを自動化できる労務管理システムです。ワークフローや書類提出を自動化できるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。
初期設定の代行オプションが用意されており、クラウドサービスに不慣れな企業でも導入しやすい点が特徴です。
また、従量課金制で必要な機能だけを選べる柔軟さも評価されています。無料プランも存在し、事業規模が小さければコストを抑えた運用も可能です。
ジョブカンシリーズの一つとして信頼性も高く、シリーズ累計250,000社以上の導入実績がある点も導入を検討する際の判断材料になるでしょう。労務管理のコストと手間を最小限に抑えたい企業におすすめです。
fapi

| 料金プラン | 要お問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | アサイン管理 スキル管理 要員検索レポート表示など |
| タイプ | 業界特化型のクラウドサービス |
| 導入実績 | 株式会社NSIT 常磐システムエンジニアリング株式会社 株式会社アイティ・フォレストなど |
| 会社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目17番地18 クリスタルビル5階 |
fapiは、エンジニアや専門職が多い企業向けのスキル管理・アサイン管理ツールです。最適な人材配置は、能力活用や過度な業務負荷防止に繋がり、労務管理の観点からも重要です。
SES・受託開発の現場から生まれ、柔軟な管理項目とデータ分析で適切なアサインを支援します。加えて、スキルシート作成・更新も効率化し、属人化を防ぎます。
労務担当者は、スキルや稼働状況データの適正評価や長時間労働防止、キャリア支援の参考にできます。アサイン精度向上はリソース最適化、従業員満足度向上、健全な労務環境構築に貢献するため、労務と人材戦略を連携させたい企業におすすめです。
Chat&Messenger

| 料金プラン | 基本機能:無料 オンプレミス:月額200円 クラウド:月額300円 |
|---|---|
| 機能 | 勤怠管理機能 ・出退勤の打刻 ・勤怠状況の確認 ・パソコン稼働状況の把握 ビジネスチャット機能 ・ファイル共有 ・絵文字リアクション ・メンション機能 ・定型文送信 ・スクリーンキャプチャ機能 ・画像ペイントツール |
| タイプ | オンプレミス型・クラウド型 |
| 導入実績 | 大企業、銀行、政府省庁、県庁、市役所、IT、大学、病院など幅広い企業・組織での導入実績多数 |
| 会社所在地 | 〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12F |
Chat&Messengerは、勤怠管理を含むグループウェアです。正確な勤怠データの収集・管理を効率化し、日々の業務負担を軽減します。
ビジネスチャットやWeb会議も統合しているため、複数のツールを導入する手間を省けます。クラウド・オンプレミス両対応で、スマホアプリからも勤怠打刻や申請・確認が可能です。
勤怠管理を起点とした労務効率化と円滑な情報共有を目指す企業におすすめです。
アイピア

| 料金プラン | 要お問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | 見積作成、原価管理、現場日報管理、顧客管理、工程管理など、建築業務全般の効率化支援 |
| タイプ | クラウド型の業務管理システム |
| 導入実績 | 年間導入実績150社以上 年間新規ユーザー数1,000以上 |
| 会社所在地 | 〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123-1 貿易ビル503 |
アイピアは、建築業界に特化したクラウド型業務管理システムです。見積作成や原価管理、工程表の作成など、工務店やリフォーム業者に必要な機能を一元化し、業務の効率化をサポートします。
Google Chrome対応でスマートフォンからのアクセスも可能なため、現場や外出先でもスムーズに活用できます。
導入初心者にも安心な電話・メール・画面共有によるサポート体制が整っており、初期設定から活用までしっかりフォローしてもらえる点も魅力です。
業界ノウハウを活かした改善提案も多く、建設業務のデジタル化を進めたい企業は、導入を検討することをおすすめします。
労務管理システムを選ぶ際の12の比較ポイント
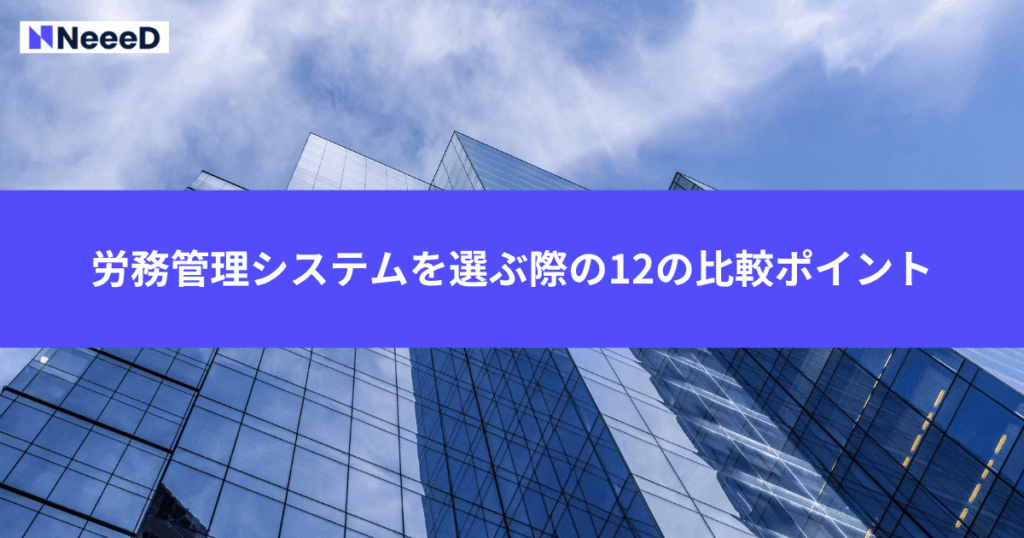
労務管理システムを選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。
効率化したい業務に対応しているかだけでなく、利便性の高さや拡張性についても確認することが重要です。それぞれ詳しく解説します。
自社の業務範囲に対応しているか
労務管理システムを導入する際は、自社の業務範囲に対応しているかを見極めることが重要です。
中小企業や事業規模の小さい会社の場合、状況に応じて業務フローが変わることもあるため、ある程度の柔軟性が必要になります。そのため、対応範囲が広く、業務フローを広範囲で固定せざるをえない労務管理システムは相性が悪いことが多いです。
また、労務について独自の慣習がある業界の場合、汎用的な製品では対応しきれないことも少なくありません。導入するシステムを検討する際には、自社の業務フローに無理なく組み込めるかを確認しましょう。
業務に必要な機能が搭載されているか
労務管理システムを導入する際は、業務に必要な機能が過不足なく搭載されているかも確認しましょう。
勤怠管理や給与計算、年末調整、社会保険の手続きなど、必要な機能が網羅されていないと別システムとの併用が必要になり、かえって業務が煩雑になるおそれがあります。
業務ごとに必要な機能を洗い出し、導入を検討しているシステムが対応できるか確認しておけば、導入後のギャップや無駄なコストを回避することが可能です。
比較検討時は、機能一覧表や公式サイトの記載をもとに、対応範囲の明確な把握を心がけましょう。
予算に合った料金か
検討している労務管理システムの料金が予算に合っているかも、労務管理システムの選定基準になります。
労務管理システムを利用する際には、初期費用や月額料金、機能のカスタマイズ費用など、様々な費用が発生します。
導入コストだけでなく、運用にかかるランニングコストも含めた総額をシミュレーションすることで、想定外の出費を予防することが可能です。
また、自社の利用頻度や必要な機能に対して、コストが適正かもあらかじめ見極めましょう。たとえば、初期費用が低くても月額料金が高ければ、長期的に見てコストがかさむ場合もあります。
コスト面での失敗を避けるためには、導入後のサポート費や機能追加に伴う追加料金も含め、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
操作性は高いか
労務管理システムを選ぶ際は、操作性の高さも確認しましょう。UIが直感的でないシステムは、導入しても現場に定着しにくい上、操作ミスによって業務の混乱につながるおそれがあります。
また、入力画面が複雑だったり、画面の遷移などが多い仕様のシステムを導入してしまうと、従業員の負担が増える可能性があります。
労務管理システムを検討する際は、実際の運用を想定し、操作性を確認しておきましょう。選定時には実際に使用する担当者にも確認を依頼することで、現場へのよりスムーズな定着を期待できます。
従業員自身が情報を入力・確認できるか
労務管理システムを導入する際は、従業員が自身の情報を直接入力・確認できるかどうかも確認しておきましょう。
マイページ機能やスマホ入力に対応しているシステムであれば、住所変更や扶養情報の更新、勤怠申請などを従業員自身がWeb上でセルフ入力できるようになります。
こうした自己申請機能により、労務担当者の手間を減らしつつ、従業員の情報管理意識を高めることが可能です。
また、リアルタイムでの確認や修正が可能となることで、入力ミスの早期発見にもつながります。日常的な労務手続きを円滑にするには、業務を分散できるような選択肢のあるシステムを導入するのがおすすめです。
他のシステムと連携できるか
他のシステムと連携できるかも、労務管理システムを比較する際のポイントです。
給与ソフトや勤怠管理システムなど、既存のシステムと連携できれば、それぞれのシステムで管理しているデータをシームレスに利用できます。
会計ソフトやERPと連携させることで、勤怠連携から給与計算、経理処理まで一連の流れをスムーズに自動化でき、業務全体の効率化につながります。特にAPIを通じて外部システムと連携できる製品であれば、多くのシステムと連携することが可能です。
連携性の高いシステムは、現行の業務フローを崩さず導入できることも多いので、システム選定時の基準にすることをおすすめします。
サポート・フォロー体制が整っているか
労務管理システムを選定する際は、導入後のサポート体制が整っているかも確認しましょう。
労務管理システムに限らず、業務関連のシステムでは不測のトラブルが発生することが少なくありません。また、システム導入時には担当者が設定や操作に戸惑う場面が多いです。
サポートやフォロー体制が万全の製品であれば、トラブル発生時に迅速な対応をしてもらえる他、導入時の設定や運用に関する支援を受けられます。
特に「24時間365日受付可能」なサポート体制が整っている製品であれば、自社の業務体制や状況に寄らず、迅速なサポートを受けることが可能です。
労務管理システムの選定時には、サポートやフォローの体制が自社の要求レベルに合っているかをあらかじめ確認しておきましょう。
周辺業務に対応しているか
労務管理システムを選ぶ際には、勤怠管理や給与計算だけでなく、人事評価や経費精算など、周辺業務への対応範囲も確認しておくことが重要です。
入退社手続きや年末調整などの関連業務を別ツールで運用していると、データの入力ミスや作業漏れが発生しやすくなります。
一方で、上記のような業務に対応している製品であれば、同じデータをもとに帳票発行や社会保険手続きを自動化できるため、全体の業務負荷を大幅に軽減することが可能です。
また、人事評価の管理や採用業務まで対応できる製品であれば、部門間の情報連携もスムーズになり、業務の属人化防止や生産性向上にもつながります。
周辺機能が充実しているかどうかは、将来的な業務拡張への柔軟性にも関わるため、自社のニーズに応じたシステムを見極めることが重要です。
電子申請(e-Gov)で手続きが進められるか
電子申請に対応しているかも、労務管理システムを選ぶ際のポイントです。
社会保険手続きや労働保険の年度更新といった書類は、電子化することで外出の手間や書類の準備時間を削減できます。特に申請業務が集中する時期には、いつでもオンラインで処理できることが大きなメリットです。
また、社会保険手続きが自動化されていれば、申請内容に沿って自動提出されるため、入力ミスや漏れのリスクも抑えられます。
電子申請機能が搭載された労務管理システムを選ぶことで、事務工数の削減による業務全体の効率化が可能です。
セキュリティ対策が充実しているか
労務管理システムには、給与情報やマイナンバーなどの個人情報を多く扱う性質があります。
そのため、セキュリティ対策が充実しているかは、導入前に必ず確認しておかなければいけません。
暗号化通信(SSL)やアクセス制限、IPアドレスによる制御などが備わっていれば、不正アクセスや情報流出のリスクを大幅に軽減できます。
システムに不備があると、情報流出により企業の信頼が損なわれ、損害賠償や行政指導など法的なリスクも生じる可能性があります。
安心して運用を続けるためにも、不正アクセス対策が講じられているかを事前に確認し、万一の事態にも備えられる体制が整ったサービスを選ぶことが重要です。
導入実績は豊富か
導入実績も労務管理システムの導入を検討する際の重要な判断材料です。
実績のある製品は、実際の現場で繰り返し利用されており、運用面での安定性やトラブル対応のノウハウが蓄積されているため、初めて導入する企業でも安心して使い始めやすくなります。
また、導入企業数が豊富なほど、機能改善やUIの最適化も進みやすく、結果的にユーザーの使い勝手が向上していることが多いです。
さらに、同業種・同規模の企業での活用事例があれば、自社の活用イメージを具体化でき、比較検討がしやすくなります。
労務管理システムを検討する際は、あらかじめ導入実績や事例を確認し、信頼性の高いものを導入しましょう。
事業成長に合わせた機能拡張が可能か
労務管理システムを選ぶ際は、将来的な事業成長に対応できる拡張性があるか確認しましょう。
導入当初は最低限の機能で十分でも、社員数の増加や業務領域の拡大に伴い、必要な機能や処理量は確実に変化します。
たとえば、最初は給与計算や年末調整にしか使っていなかったシステムでも、後から人事評価やスキル管理に利用したくなることもあるでしょう。
オプション機能の追加や段階的なアップグレードが可能な製品なら、上記のような場合でも買い替えや再構築の手間を避けながら運用を継続できます。
また、既存の機能のアップデートが定期的に行われているなど、利用するシステムのスケーラビリティがどこまで確保されているかも重要な比較ポイントです。現在だけでなく、将来の変化に柔軟に対応できる製品かを見極めることが、長期的な導入効果を高める鍵になります。
事業規模に合った労務管理システムの選び方
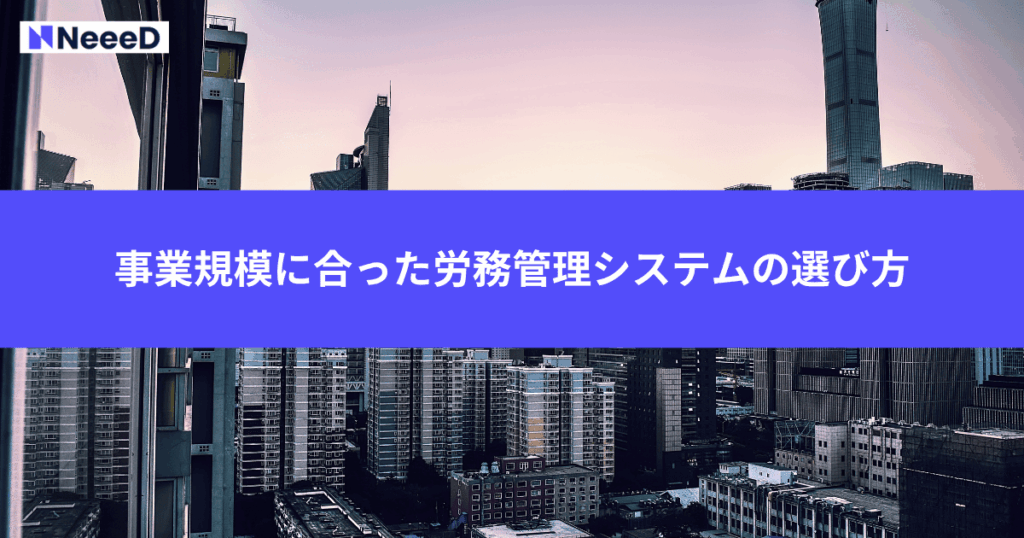
労務管理システムを選ぶ際には、自社の規模に合ったものを選ぶことも重要です。当記事では以下の規模に分類し、導入すべき労務管理システムについて解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
スタートアップ・創業期の企業の場合
スタートアップや創業期の企業にとって、労務管理システム選びで重視したいのは導入のしやすさとコストの低さです。
社員数が少ないうちは、複雑な機能よりもミニマムな構成で必要な業務だけをカバーできるシステムが適しています。
たとえば、勤怠管理・給与計算・社員情報の登録といった基本機能を中心に備えた手軽なツールであれば、専門知識がなくてもすぐに使いこなせます。
また、無料プランが用意されているサービスであれば初期導入のハードルも下がり、業務効率化に向けて円滑なスタートを切ることが可能です。
小規模な体制でも無理なく始められるソリューションを選ぶことで、将来的なシステム拡張にも対応しやすくなります。
中小企業の場合
中小企業が労務管理システムを導入する際は、業務効率化と法令対応の両立が図れる製品を選ぶことが重要です。
社員数の増加や制度改正に柔軟に対応できるよう、拡張性やアップデート体制が整った中堅向けのシステムが適しています。
また、勤怠管理・給与計算・年末調整などの機能をひとつにまとめた一元管理型ツールであれば、日々の手間を減らしつつ管理ミスを防ぎやすくなります。
加えて、システムの操作性や導入サポートの充実度、月額料金と機能のバランスが取れているかどうかも確認すべきポイントです。
特にコストパフォーマンスを重視する企業にとっては、必要な機能を無理なく導入できる価格帯かどうかも判断材料となります。
対応業種が広く、中小企業特有の課題に寄り添った設計がされている製品を選ぶことで、現場の混乱を最小限に抑えながら労務管理の最適化を図ることが可能です。
大企業の場合
大企業が労務管理システムを選ぶ際は、多拠点展開や複雑な組織構成に対応できる柔軟性とシステム自体の安定性が求められます。
数百名以上の従業員を管理するには、部門ごとの承認フローや権限設定が細かく行えるシステムが有効です。
また、既存の基幹システムや会計ソフトとのAPI連携がスムーズに行えるクラウド型ツールであれば、業務全体のデジタル化を加速させやすくなります。
さらに、セキュリティ対策が万全であることも必須条件となり、アクセス制限やログ管理、データ暗号化などの仕様を事前に確認しておく必要があります。
導入後のサポート体制やカスタマイズ性も含めて、長期的な視点での運用を見据えた製品選定が重要です。
労務管理システムとは

労務管理システムとは、企業の労務業務を一元管理できるツールです。従業員数が増えるにつれて複雑化しがちな労務関連業務を効率化し、生産性の向上につなげます。
法令改正への対応や帳票出力機能を備えているシステムも多く、コンプライアンスの強化にも貢献します。
また、勤怠管理や給与計算、人事管理などに関する機能が搭載されているものもあり、労務データをもとにした効率的な業務を実現することが可能です。
上記のような機能については専用のシステムも多くリリースされています。それぞれのシステムについては別の記事で詳しく解説しているので、気になる方は当記事と合わせてご覧ください。
関連記事>>勤怠管理システムのおすすめ・比較
関連記事>>給与計算ソフトのおすすめ・比較
クラウド型とオンプレミス型の違い
労務管理システムには、クラウド型とオンプレミス型の2つの提供形態があります。
クラウド型はインターネット環境があればすぐに利用を開始でき、初期設定や保守の手間が少ない点が特徴です。定期的なアップデートが自動で行われるため、常に最新状態で運用でき、テレワークや複数拠点の対応にも適しています。
一方で、オンプレミス型は自社のサーバーにシステムを構築するため、カスタマイズ性やセキュリティ面に優れているのがメリットです。また、基本的に月額料金が発生せず、年間のメンテナンス費用のみで運用できることが多いため、長期的にみるとクラウド型よりも割安になる傾向があります。
ただし、導入時のコストが高額なため、キャッシュに余裕のある企業でないと導入できません。またメンテナンスを外注しない場合は、社内の運用負担が高くなるので注意が必要です。
労務管理システムのシェア率が高い人気のタイプについて
労務管理システムで、シェア率が高く人気があるタイプは、クラウド型で幅広い業務を効率的にカバーできるタイプです。これらのシステムは、システム間の連携やモバイル対応といった運用の柔軟性にも優れている点が特徴です。
クラウド型で幅広い業務を効率的にカバーできるタイプの製品は、導入実績が豊富で機能の信頼性が高く、継続的なアップデートにも対応している傾向があります。
また、従業員数や業種を問わず導入しやすいように設計されているシステムも支持を集めています。まずは小規模な範囲からシステム導入を始めたいと考える企業にとっても、安心して選定できる選択肢となっています。
労務管理システムのタイプ
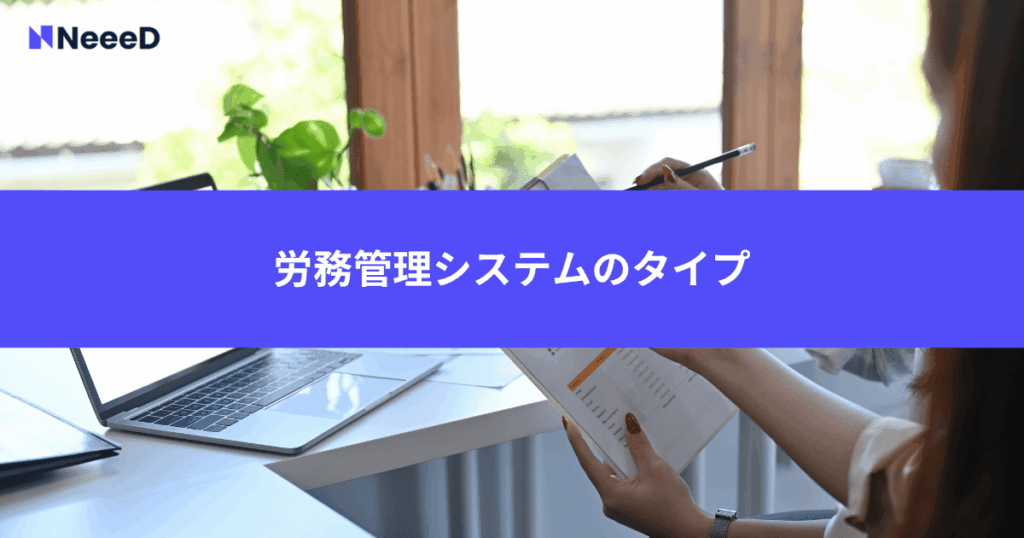
労務管理システムは、以下のようなタイプに分類できます。
それぞれのタイプの特徴について詳しく解説します。
労務手続きの効率化ができる汎用タイプ
日常的に発生する入退社手続きや社会保険関連の申請、年末調整や帳票出力といった基本的な業務を効率化したい企業には、汎用的な労務管理システムが適しています。
汎用タイプは従業員情報の登録や書類の電子申請など、標準機能を備えており、複雑な設定を必要とせず導入しやすいのが特徴です。
導入コストを抑えつつ必要な作業を効率化できるため、労務担当者が少人数の企業や、これから本格的なデジタル化を進めたい中小企業に人気があります。
システムの操作もシンプルなケースが多いため、専用のトレーニングを受けずとも直感的な運用が可能です。
はじめて労務管理システムを検討する企業や、まずは一部業務の効率化から取り組みたい企業は、汎用タイプから導入を検討してみると良いでしょう。
機能拡張が可能なタイプ
将来的な組織拡大や業務範囲の変化を見据えるなら、機能拡張が可能な労務管理システムを選ぶのが効果的です。
このタイプはモジュール設計が採用されているケースが多く、必要に応じてオプション機能を後から追加できる柔軟性を備えています。
たとえば、初期導入時は勤怠管理や給与計算に限定し、組織が拡大した段階で人事評価や経費精算などの機能を加える運用も可能です。
また、他のクラウドサービスや会計ソフトとの連携機能が用意されている場合は、業務間のデータ共有もスムーズになり、さらなる効率化を実現しやすくなります。今後の成長や業務変化に備えておきたい企業に特におすすめのタイプです。
労務管理以外の機能もある多機能タイプ
人事や総務の業務全体を効率化したい場合は、労務管理にとどまらず周辺機能も備えた多機能タイプが適しています。
上記のようなタイプでは基本的な労務管理だけでなく、以下のような業務もワンストップで効率化することが可能です。
- 勤怠管理
- 人事評価
- 採用管理
- 福利厚生の管理
複数のツールを使い分ける必要がなくなるため、業務の重複や抜け漏れを予防できます。また、それぞれの業務で共通のデータを活用できることもメリットです。
たとえば、従業員の人事データをもとに評価内容やキャリア情報を管理できるタレントマネジメント機能が搭載されていれば、戦略的な人材配置や育成も進めやすくなります。
また、情報が一元化されていることで、部署間の連携や経営層へのレポーティングもスムーズに行うことが可能です。特に複数拠点や多職種を抱える企業におすすめのタイプといえるでしょう。
特定の業務プロセスや課題に特化したタイプ
特定の業務負荷が集中している場合は、課題に特化したシステムを導入すると良いでしょう。
たとえば、年末調整の書類作成やマイナンバー管理、採用手続きといった業務は、作業が煩雑でミスが起きやすく、社内のリソースを圧迫しがちです。
こうした業務にフォーカスした特化型の労務管理システムであれば、必要な機能が洗練されており、業務フローの自動化や法令対応がスムーズに進みます。
社労士向けの電子申請機能や、入退社手続きの効率化を支援する機能を備えた製品も多く、ピンポイントで業務の負担を軽減したい企業に最適です。
業務フローやすでに導入しているシステムへの影響も少ないため、導入や運用のハードルも抑えやすくなっています。
労務管理システムの機能

労務管理システムの主な機能は以下の通りです。
それぞれの機能について詳しく解説します。
労務管理機能
労務管理機能は、労務管理システムの基本といえる機能で、従業員の労働条件や社会保険・労働保険の手続きを適切に管理できます。
具体的には、社会保険・労働保険の書類作成やe-GovからのWeb申請、法定三帳簿の作成などを効率化することが可能です。他にも算定基礎届の作成や、労働保険の年度更新なども自動化できます。
また、システムによっては勤怠管理機能も搭載されており、勤怠データを人事管理や給与計算に活用することが可能です。
人事管理機能
製品によっては、人事管理機能が搭載されている場合があります。人事管理機能は社員情報を一元管理できる機能です。
氏名や連絡先、所属部署などの基本情報に加え、保有資格などのスキルに関する機能や、異動履歴や昇給記録なども時系列で整理できます。
情報を一覧化できることで、検索や更新作業にかかる手間を削減し、担当者間の情報共有や連携を円滑に行うことが可能です。
また、組織図と連動する機能があれば、部署ごとの構成や役職ごとのバランスも把握しやすくなり、人事評価や配置転換の判断材料としても活用できます。
分散していた情報を一つのプラットフォームに集約することで、社内の情報共有精度が高まり、確認ミスの防止や業務スピードの向上が期待できます。
給与計算機能
給与計算機能が搭載されている労務管理システムでは、従業員の基本給や残業、各種控除などを自動で集計し、正確な給与を計算できます。
単体の給与計算システムとは異なり、勤怠データをもとにした給与・賞与計算が行えるため、データの入力ミスや転記漏れが発生するリスクを抑えられます。結果として、より効率的な給与計算業務を行うことが可能です。
また、あらかじめ控除額の設定や就業規則に基づく支給条件の登録をしておけば、毎月の給与計算を自動化できます。
さらに、CSV出力やWeb明細の発行に対応していれば、印刷・配布の手間も省け、社内全体のペーパーレス化にもつなげることが可能です。
年末調整機能
年末調整機能は、源泉徴収票の作成や控除証明書の確認といった煩雑な作業を一括で効率化できる機能です。
従業員が直接入力できるセルフ申告機能や、不備を自動で検出するチェック機能を備えることで、担当者と従業員の双方の負担を大幅に軽減できます。
手作業による転記ミスや確認漏れを防ぎながら、入力から申告までをワークフローで進行できるため、提出期限直前に混乱が起こることもありません。
また、電子申請対応のシステムであれば、税務署への提出もオンラインで完了できるため、紙の提出に比べて手間と時間を削減できます。
入退社手続き機能
入退社手続き機能は、新入社員の雇用保険や社会保険の届け出を含む一連の事務処理をオンラインで一元管理できる機能です。
入社時に新入社員が個人情報や扶養控除申告書などの書類をWeb上で提出・確認できる仕組みを整えることで、紙でのやり取りに伴う不備や紛失のリスクを最小限に抑えられます。
また、退職時に発生する資格喪失の申請もシステム内で完結できるため、複雑な手続きも効率良く進行できます。
進捗の可視化や申請ステータスの一覧管理も可能なので、入退社手続きにかかる担当者の負担を減らしながら、正確かつ迅速な対応を実現することが可能です。
マイナンバー管理機能
マイナンバー管理機能では、マイナンバーの収集から保管、利用履歴の記録まで一貫して行えます。マイナンバーは厳重な管理が法律で義務付けられており、紙でのやり取りや個人端末での保管では情報流出や不正利用を招きかねません。
マイナンバー管理機能がある労務管理システムであれば、情報を閲覧できる担当者を明確にし、アクセス履歴を自動的に記録できるため、情報の追跡性と安全性が高まります。
また、データの暗号化や登録制限といったセキュリティ機能も搭載されているものが多く、外部からの不正アクセスにも備えやすくなります。結果的にマイナンバーの適正管理に関する社内体制を強化することが可能です。
労務管理システムを導入するメリット

労務管理システムを導入するメリットは以下の通りです。
給与計算や労務の効率化が可能なだけでなく、データをもとにした組織改善が可能になることも大きなメリットです。それぞれ詳しく解説します。
給与計算を効率化できる
給与計算機能のある労務管理システムを導入すれば、毎月の給与計算業務の大幅な削減が可能です。
勤怠データと連携することで、基本給や残業代、各種手当や控除額などを自動計算できるため、転記ミスや計算漏れを防ぎやすくなります。
特に紙や表計算ソフトで処理していた企業では、明細の作成や帳票出力などの定型業務に追われがちですが、システム化により一連の作業をワンクリックで完了できるようになります。
月末の処理が集中する担当者にとっては、業務負担を軽減しつつ、正確な給与支給につなげられる点が大きなメリットです。
労働時間が正しく管理できる
勤怠管理機能がある労務管理システムを活用すれば、従業員の出退勤時刻や残業時間などを自動で記録・集計でき、労働時間の正確な管理が可能になります。
従来のタイムカードや手書きの打刻では、記録ミスや不正確な申告が発生しやすく、労働基準法に基づいた管理が難しいことも少なくありません。
システムの導入することで、打刻データをリアルタイムで確認・蓄積できるようになるため、月単位の残業時間や休憩時間の把握が容易になります。
また、勤務実態が可視化されることで、管理者は早めの対応が可能となり、法令違反や過重労働のリスクを抑えられます。
適切な人材配置が可能になる
人事管理機能のある労務管理システムを導入すれば、従業員のスキルや職歴、勤怠傾向といった人事データを一元管理できるため、最適な人材配置を行いやすくなります。
業務の属人化を防ぎつつ、各従業員の特性に応じた配置転換や配属の判断が可能になることで、組織全体の生産性向上につなげられます。
特にスキル管理機能や組織図との連携があるシステムであれば、部署ごとの人員構成や過不足も把握しやすいため、長期的な人材育成や人事戦略の立案に役立てることが可能です。
法令遵守を徹底できる
労務管理システムを導入することで、法令遵守を継続的に徹底しやすくなります。
社会保険や労働基準法などの法改正に効率良く対応できるようになるため、就業規則の更新や帳票の修正に手間をかけることなく、最新のルールに則った運用が可能です。
たとえば、変更点が発生した際には通知機能でアラートが届くシステムであれば、申請漏れや対応遅れによるリスクも抑えやすくなります。
コンプライアンスの観点からも、正確な記録や提出が求められる業務で制度に沿った処理をある程度自動化できるのは大きなメリットです。
福利厚生を一元管理できる
福利厚生制度を効果的に運用するには、手当や休暇制度などの情報を一元的に管理できる環境が重要です。
福利厚生に関する機能を搭載した労務管理システムを導入すれば、申請書類の提出から承認までのフローをデジタル化でき、紙ベースでのやり取りや記録の分散による混乱を防ぎやすくなります。
また、有給休暇や特別休暇の管理、有資格者向け手当の申告といった処理もシステム上で行えるため、従業員が制度を利用しやすくなるのもメリットです。
加えて、制度の利用状況を可視化できるようになるため、福利厚生が活用されていない原因を把握し、改善にもつなげやすくなります。
労務管理とあわせて福利厚生も一括管理することで、働きやすい職場環境を整備することが可能です。
ヒューマンエラーを防止できる
労務では、入力ミスや記載漏れが起こりやすい工程が多く存在します。労務管理システムを導入すれば、入力項目の自動チェックや計算処理の自動化ができるため、ヒューマンエラーを最小限に抑えることが可能です。
たとえば、給与や勤怠データの集計はあらかじめ設定されたルールに従って行われるため、手計算によるズレや転記漏れが発生しにくくなります。
また、チェック機能により不備のある入力がリアルタイムで検知され、ミスの早期発見につながるのもメリットです。
法改正に対応できる
法改正に対応しやすい体制が作れることも、労務管理システムを導入するメリットです。労務関連の法改正には必ず対応が必要になりますが、改正が頻繁に行われることもあり、逐一対応していると生産性の低下を招きます。
労務管理システムを導入していれば、自動更新機能で常に最新の法令に対応した労務管理が行えるため、改正に合わせた更新業務にかかる工数の削減が可能です。
また、改正情報の通知機能が備わっている製品もあり、自動化によって担当者自身が法改正に追従できなくなるリスクも抑えられます。
法改正対応の負担を軽減したい企業は、特に労務管理システムを導入するメリットが大きいといえるでしょう。
勤怠報告に関する不正が防止できる
勤怠報告の正確性を高めたい企業にとって、不正打刻の防止は重要な課題です。
勤怠管理機能が搭載された労務管理システムを導入すれば、GPS打刻やモバイル認証などで打刻位置や端末の制限が可能となり、虚偽報告を抑止できます。
さらに、ログ取得機能を備えていれば、打刻履歴の追跡や操作状況の把握も行えるため、不自然な勤務記録の早期発見が可能です。
こうした仕組みは、従業員一人ひとりの勤怠に対する意識向上にもつながり、組織全体のコンプライアンス強化にもつながります。
正確な勤怠データが蓄積されることで、残業時間の把握や働き方の見直しにも活かせるため、健全な労働環境の構築を目指す企業は勤怠管理機能が搭載された労務管理システムを導入すると良いでしょう。
データをもとにした組織改善が可能になる
業務改善や人材活用の精度を高めるうえで、データに基づく改善は欠かせません。
労務管理システムには、蓄積された勤怠データや人事情報をレポートやダッシュボードで可視化し、傾向の把握や分析に活用できる機能が備わっているものもあります。
たとえば、部署ごとの残業時間や有休取得率を比較することで、負担の偏りや業務過多の兆候を早期に発見できます。結果として適切な人材配置や業務分担の見直しが可能です。
データの分析を定期的に行うことで、属人的な判断に頼らず、客観的な組織運営が実現できることも労務管理システムを導入するメリットといえるでしょう。
労務管理システムを導入するデメリット・注意点

労務管理システムを導入するデメリットや注意点は以下の通りです。
特に導入から運用開始までに時間がかかる点は、あらかじめ把握しておきたいポイントです。それぞれ詳しく解説します。
導入・運用に費用がかかる
まず、労務管理システムの導入や運用には初期費用やランニングコストが必要です。初期費用に加え、毎月の月額課金や運用にかかるランニングコストが発生し、システムによっては必要な機能を追加するごとに料金が上乗せされることもあります。
特に中小企業やスタートアップにとっては、導入後に想定以上のコストが発生し、予算を圧迫するリスクもあるため注意が必要です。
費用対効果が見合わないまま契約を継続してしまうと、資金を消耗するだけで求める効果が得られない可能性もあります。
導入を検討する際は、無料トライアルの活用や複数製品の比較を徹底し、長期的にみて費用対効果が高いか検討することが重要です。
システム更新や保守管理に手間がかかる
労務管理システムの導入後に定期的なメンテナンスやアップデートが必要になる点にも注意が必要です。特にオンプレミス型の場合は、自社で保守作業を行う必要があり、ITに詳しい担当者がいないと対応に手間がかかります。
クラウド型であっても、機能追加や仕様変更により、操作方法の習得や社内マニュアルの更新が必要になる場面があります。
さらに、アップデート後に不具合が発生する可能性もゼロではなく、業務の進行に支障が出るリスクも考慮しておくべきです。
日々の業務を止めず安定運用を実現するには、ベンダーのサポート体制を事前に確認し、トラブル時にすぐに対応してもらえる環境を整えておくことが重要になります。
システムに慣れるまで従業員の教育が必要になる
労務管理システムを導入しても、すぐに現場で活用できるとは限りません。基本的に、導入初期には従業員への教育が必要になります。
操作性が高いツールであっても、新しいシステムに対する戸惑いや、業務フローの変更に伴う混乱を避けることは困難です。
特に従来の手作業やExcel管理に慣れていた場合、使い方を習得するまでに時間がかかり、教育コストやマニュアルの整備といった追加対応も求められます。
スムーズに運用を始めるには、ベンダーが導入支援や運用サポートに対応しているか確認しておくと安心です。
急なトラブルで業務が停止するおそれがある
労務管理システムの導入にあたっては、システム停止による業務中断リスクも見過ごせません。
オンプレミス型はもちろん、クラウド型であってもサーバー障害や通信トラブルが発生すれば、給与計算や社会保険の手続きなど重要な業務が一時的にストップする可能性があります。
こうした状況に備えるためには、定期的なバックアップ体制や緊急時のマニュアルを整備し、最低限の業務が継続できる仕組みを構築しておくことが重要です。
また、障害発生時の対応スピードやサポートの有無も確認しておくと良いでしょう。万が一に備えた対策を講じておくことで、安心して運用できる環境を維持しやすくなります。
イレギュラーな業務に対応しにくくなる
労務管理システムは業務を標準化・効率化するうえで有用ですが、イレギュラーな業務に対応しにくくなるリスクがあります。
たとえば、特殊な勤務体系や一時的な雇用形態など、柔軟な処理が必要な場面では、あらかじめ決められた入力項目や処理手順に制約がかかり、対応できないケースも考えられます。
そのため、あらかじめカスタマイズ性や手動での補完機能の有無を事前に確認しておくことが重要です。
システムの柔軟性が不十分だと、結果的に別途手作業が必要になり、導入による業務効率化の恩恵が薄れてしまうおそれがあります。
日常業務だけでなく例外対応まで視野に入れて選定することが、失敗を避けるポイントになります。
セキュリティ面のリスクがある
労務管理システムには利便性がある一方で、セキュリティ面のリスクも無視できません。
従業員のマイナンバーや給与情報といった機密性の高い個人情報を扱う以上、不正アクセスや個人情報漏洩のリスクに常に備える必要があります。
セキュリティ対策が不十分なまま運用すると、企業の信頼性が損なわれるだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
労務管理システムを導入する際には暗号化技術やアクセス制限機能があるか確認し、導入後も定期的な脆弱性チェックを実施して安全性を保つ体制を整えましょう。
業界によっては適切なカスタマイズができない可能性がある
労務管理システムは汎用的な設計であることが多く、すべての業界や業種に完全対応できるとは限りません。
特に医療や建設業など、独自の勤務形態や労務処理が求められる業種の場合、一般的な労務管理システムでは対応しきれないことも多いです。具体的には、必要な帳票への未対応や、特殊な勤務形態への未対応などが挙げられます。
導入前には自社と同じ業界での導入実績や、要望に応じたカスタマイズ対応の有無を必ず確認し、必要に応じて追加開発や外部ツールとの連携も検討しましょう。
労務管理システムの価格・料金相場
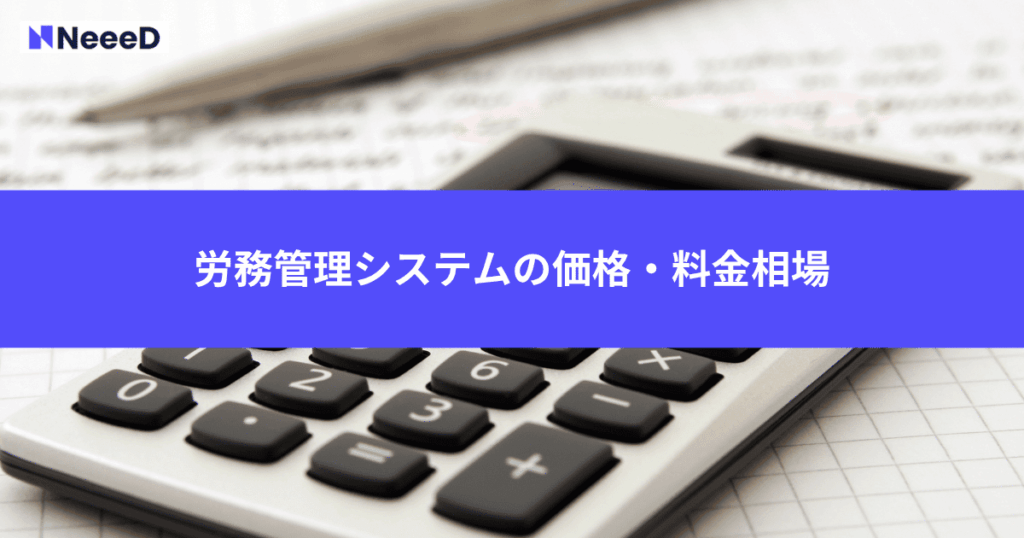
労務管理システムの価格・料金相場は以下の通りです。
| 料金体系 | 費用相場 |
|---|---|
| 従量課金型 | 月額300円〜600円程度(1ユーザーあたり) |
| 買い切り型 | 初期費用:数十万円~数百万円程度 ※別途保守・管理費用が発生する場合あり |
基本的には、従量課金型と買い切り型で料金体系に違いがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
従量課金型の料金相場
クラウド型の労務管理システムでは、従量課金型の料金体系が採用されていることが多いです。従量課金型の場合、月額料金が利用人数や選択機能に応じて変動するため、自社の規模や業務内容に合わせた柔軟なプラン選定ができます。
加えて、機能を追加したいタイミングでプランを拡張できるため、業務の成長にもスムーズに対応しやすいのがメリットです。
料金相場は1ユーザーあたり月額300円〜600円程度が目安とされ、トライアル期間を設けているサービスも多いため、導入前に使用感を確かめやすいのもメリットといえます。
買い切り型の料金相場
オンプレミス型の労務管理システムの場合、基本的には料金体系が買い切り型になっていることが多いです。
クラウド型と異なり、パッケージとして自社のサーバーや端末に導入する形式が一般的であり、初期費用として数十万円~数百万円程度の膨大な料金が発生することも少なくありません。
また、定期的なアップデートや法改正への対応に自社で対応する必要があり、外注する場合は別途費用が発生します。
一方で、従量課金型のような月額利用料は発生しないため、長期運用するとクラウド型よりも料金が安くなることも多いです。
【まとめ】自社に規模や業務に合った労務管理システムを選ぼう
労務管理システムのおすすめや比較ポイント、導入メリット・デメリットなどについて解説してきました。
労務管理システムを導入すれば、労務関連の業務を効率化することが可能です。また、人事管理や給与計算などに対応しているシステムであれば、労務の枠を超えた業務を効率化することもできます。
労務管理システムを導入する際は、会社の規模や業務内容、将来の人員増などを見据えながら、必要なタイプや機能を明確にすることが重要です。
当記事を参考に、自社に合った労務管理システムを探してみてください。

の口コミや評判は?選べる料金プランや導入メリットも解説-300x158.jpg)