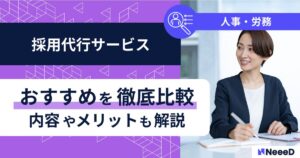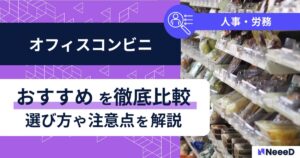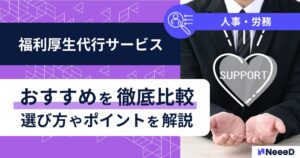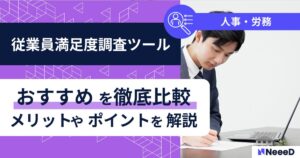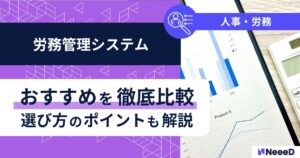【2025年6月最新】アルコールチェックアプリのおすすめを比較!無料アプリや選び方も解説
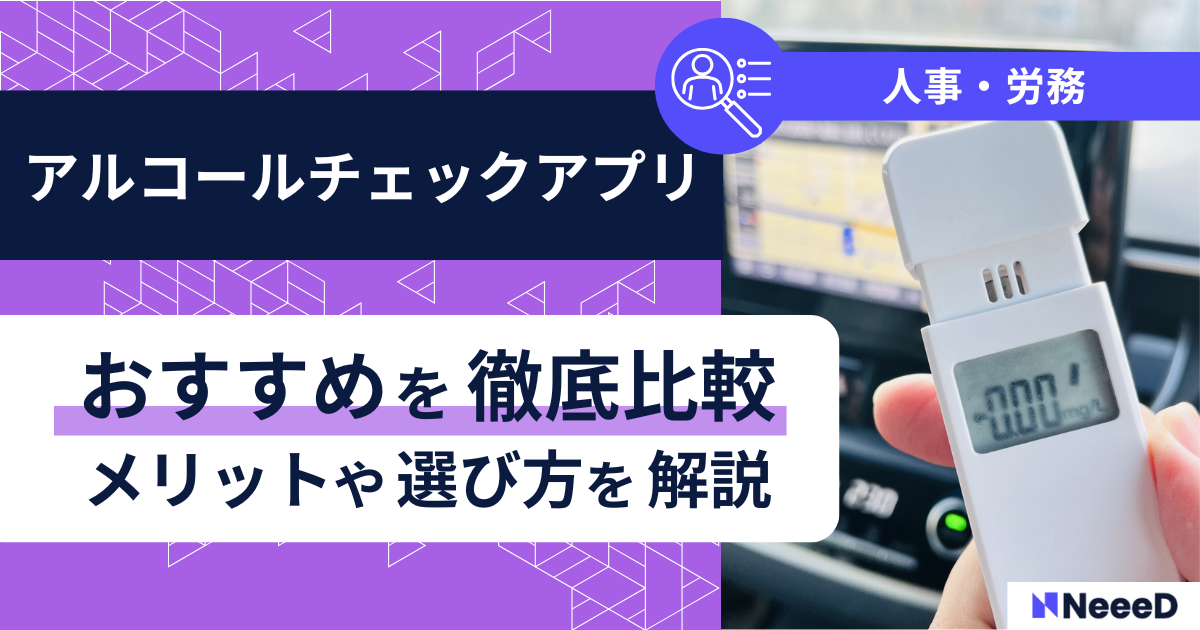
アルコールチェック義務化の対象が拡大され、多くの企業が対応に追われています。従業員や営業所の数が多い企業では、手作業での記録や管理は業務が煩雑になり、完全に法令を遵守するのが困難なこともあります。
そこで、「アルコールチェックアプリ」を導入する企業が増えています。
当記事では、おすすめのアルコールチェックアプリを厳選してご紹介します。導入メリットや比較ポイントなども解説していますので、アルコールチェックアプリの導入を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
おすすめのアルコールチェックアプリ3選
ここでは、アルコールチェック義務化への対応や安全運転管理の強化に役立つ、おすすめのアルコールチェックアプリを3つご紹介します。それぞれの特徴を以下にまとめました。
| おすすめのアルコールチェックアプリ | 特徴 |
|---|---|
| Bqey | ・測定結果はリアルタイムで反映 ・デジタルキー機能あり ・社用車管理機能あり |
| アルキラーNEX | ・業界トップクラスの導入実績 ・多様なアルコール検知器に対応 ・外部システムとの連携に強み |
| ALPiT | ・シンプルで低価格な特化型サービス ・手持ちの検知器を利用可能 ・無料トライアルあり |
サービスによって搭載機能や強みが異なりますので、自社に合ったものを見つけましょう。
Bqey(ビーキー)/株式会社東海理化電機製作所

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 主な機能 | ・アルコール測定 ・チェック時の写真撮影 ・デジタルキー機能 ・社用車の利用状況の確認・予約機能 |
| 特徴 | ・アルコール数値と連動し、問題があれば車両の鍵操作不可(飲酒運転防止) ・アルコールチェック時の写真撮影・データ保存で信頼性向上 |
| 導入実績 | ・日本経営 ・LINK ・リゾートトラスト ・マグチグループ ・インディード横浜 ・シミズ など |
| 会社所在地 | 〒480-0195 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 |
Bqey(ビーキー)は、アルコールチェックから社用車の管理までできる、車両管理一体型のアルコールチェックアプリです。アルコールチェックの記録だけでなく、社用車の予約管理や点検記録の管理も行えます。
Bqeyの特徴のひとつは、デジタルキー機能(車の鍵のスマート化)です。これはアルコール濃度が基準値を超えた場合に車のキーがロックできる機能で、異常が検知されたら即時に管理者に通知されるため、迅速に問題に対応できます。デジタルキーの管理はスマートフォンで行われ、遠隔での受け渡しも可能です。
アルコールチェックのデータは、他の運行記録とまとめて管理できます。車両管理に関する業務を広範囲で効率化したい企業におすすめのサービスです。
アルキラーNEX /株式会社パイ・アール

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 主な機能 | ・アルコール測定・記録 ・管理なりすまし防止 ・交換時期アラート ・異常値通知・リマインダー機能 |
| 特徴 | ・外部システムとの連携機能が多様 ・検知器の無償修理・代替機貸し出し ・検知器の自動メンテナンス・無償交換 ・アプリ起動から30秒程度でチェック完了 |
| 導入実績 | ・ウェルシア薬局株式会社 ・近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店 ・エプソン販売株式会社 ・オリオンビール株式会社 ・サントリーホールディングス株式会社 など |
| 会社所在地 | 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル18F |
アルキラーNEXは、スマートフォンやPCで利用できるアルコールチェックアプリです。業務で車両を使用する多くの企業に採用されています。
多種多様な外部システムと連携できるのが特徴で、ChatWorkやMicrosoft Teamsなどと連携可能です。勤怠管理システムや運行管理システムの他、IT点呼にも対応しており、車両管理から人事情報管理まで、幅広い管理を効率化できます。
アルコール検知器に対するこだわりも強く、圧力センサーとガスセンサーの二重で検知できる、日本製の検知器を採用しています。交換用カートリッジの無料提供など、メンテナンスに関するサポートも手厚く、長期的に利用しやすいサービスです。
走行管理機能も充実しており、運転日報作成、走行時間・距離・給油量自動集計、Excel出力などができます。
ALPiT/アイリスオーヤマ株式会社

| 料金プラン | 月額/運転者1名あたり アルコール検知器付き:980円~ クラウド管理機能のみ:490円〜 (2年プランあり) |
|---|---|
| 主な機能 | ・アルコール測定 ・計測結果自動記録 ・なりすまし防止機能 ・測定忘れ防止機能 ・運転日誌機能 |
| 特徴 | ・手持ちの検知器を利用可能 ・クラウドで全拠点の記録を一元管理 ・帳簿出力(CSV) ・3年間のクラウド保存 ・閾値設定(0.01~0.15mg/l)で厳格運用可能 ・2週間の無料トライアルあり |
| 導入実績 | ・株式会社サンテック ・中川商事株式会社 ・信幸プロテック株式会社 など |
| 会社所在地 | 〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 |
ALPiTは、アイリスオーヤマ株式会社が提供するアルコールチェックアプリです。専用アプリで測定結果を即時クラウドに送信し、全拠点の記録を一元管理できます。
初期費用無料、月額980円から導入できるのが特徴で、低コストでアルコールチェックを効率化できます。クラウド管理のみのプランは月額490円で利用できます。
すでにアルコール検知器を購入している場合には、既存の検知器がそのまま利用できることもALPiTの特徴です。
運転日誌機能も充実しており、CSV帳簿をExcelに出力でき、データはクラウド上に3年間保存されます。
アルコールチェックに特化したシンプルなサービスであるため、導入から運用までの時間が比較的短いことも嬉しい点です。既にアルコール検知器を保有している場合や、アルコールチェックに関する機能しか必要ない企業におすすめのサービスです。
無料で利用できるアルコールチェックアプリ

アルコールチェックアプリの導入において、コストを抑えたいと考える事業者も多いでしょう。そのようなニーズに応え、一部のサービスは無料で利用できるアプリを提供しています。
しかし多くの場合、アプリ自体は無料でも測定に必要なアルコール検知器本体を別途購入する必要があります。
ここでは、代表的な無料アプリと、導入を検討する際のポイントをあわせて解説します。
主な無料アルコールチェックアプリ
無料で利用できるアプリは、主に次のようなものがあります。
- アルコー楽(株式会社慶洋エンジニアリング)
- AI-Contact フリート
- アルコールセンサー Alcohol Sensor(Google Play)
「アルコー楽」は、アプリが無料で利用でき、導入・運用の費用がかかりません。また、無料で使える運行管理システムとしての機能も備えています。
「AI-Contact フリート」も、無料で利用できるアプリですが、詳細な機能や連携する検知器については、公式サイトでの確認をおすすめします。
「アルコールセンサー Alcohol Sensor」は、Google Playストアで提供されている汎用的なアルコール検知アプリの一つです。アルコール検知器と連携して利用するタイプで、アプリのダウンロードや利用は無料です。
検知器本体は別途購入が必要
無料アプリを検討する際に注意すべき点として、ほとんどのアルコールチェックアプリは「専用のアルコールチェッカー本体」との連携が前提となっていることがあります。
アプリ自体は無料でも、測定器が別途必要であり、BluetoothやUSB接続などの対応機種に限られているケースがほとんどです。
また、無料プランにはクラウド保存件数の制限や、レポート出力・顔認証などの高度な機能が使えないといった制約がある場合もあります。
業務での利用を想定している場合は、無料アプリでどこまで運用できるかを事前に確認し、必要に応じて有料プランへの切り替えや、初期費用・ランニングコストも含めて検討しましょう。
アルコールチェックアプリとは?
アルコールチェックアプリとは、文字通りアルコールチェックに利用するアプリで、アルコール検知器(チェッカー本体)と連携させて使います。
運転者がアルコール検知器で測定した結果を、スマートフォンやタブレットを通じて記録・管理し、事業所はそのデータを一元管理できます。異常が検知された場合はリアルタイムで管理者に通知され、飲酒運転の予防にも効果的です。
測定結果は自動的にアプリに読み取られるため、入力作業なども必要ありません。検知器を回収しなくてもアルコールチェックの結果を確認でき、遠方で業務を行っているドライバーでも利用できます。
主要な機能
アルコールチェックアプリの機能は多岐にわたります。サービスによって異なりますが、次のような機能は多くのアプリに共通して搭載されています。
- アルコール検知器との連携
- 呼気に含まれるアルコール濃度の測定
- 測定データの自動記録
- 異常値が検出されたときの警告
- クラウド保存・管理
検査自体は、専用または汎用のアルコール検知器と接続し、測定データを自動でアプリに取り込みます。基準値以上のアルコールが検知された場合、即座に管理者へアラート通知が送られます。
アルコール検知器との連携は、 Bluetoothでスマートフォンなどとペアリングするタイプが一般的です。測定日時、測定結果(アルコール濃度)、測定者の情報(氏名、IDなど)を自動で記録するため、手入力によるミスや改ざんのリスクも減ります。
記録されたデータはクラウド上に保存され、管理者はインターネット環境があればどこからでもアクセスし、全従業員のチェック状況を一元的に確認・管理できます。義務化の一環である記録項目に対応したレポートや、CSV形式でのデータ出力も可能です。
オプション機能
サービスによっては、以下のようなオプション機能が付いているものもあり、必要に応じて選択します。
- 顔認証・なりすまし防止
- 位置情報記録
- 運転日報自動生成
- 免許証や車両検査証の有効期限の管理
- IT点呼・ビデオ通話機能
なりすまし防止は、多くのサービスに搭載されている重要な機能です。アルコールチェック時に連動するカメラによる顔認証を行うことで、本人ではない人物による測定や不正行為(なりすましなど)を防止します。
位置情報機能は、GPS機能と連携し、測定時の位置情報を自動記録したり、アルコールチェックの結果と紐付けて運転日報を自動生成する機能です。免許証・車両検査証の管理機能は、ドライバーの運転免許証や車両の車検・点検時期などの有効期限をアプリ内で管理し、期限が近づくとアラートで通知します。
IT点呼・ビデオ通話機能は、ビデオ通話機能を活用したIT点呼をアプリ上で行える機能です。管理者は遠隔地にいるドライバーの健康状態や顔色を確認し、「目視確認の義務」にも対応できます。
これらのオプション機能の中には、有料(追加料金)で使えるようになるものもあります。詳しくは、各社のサイトなどで確認しましょう。
アルコールチェックアプリのタイプ
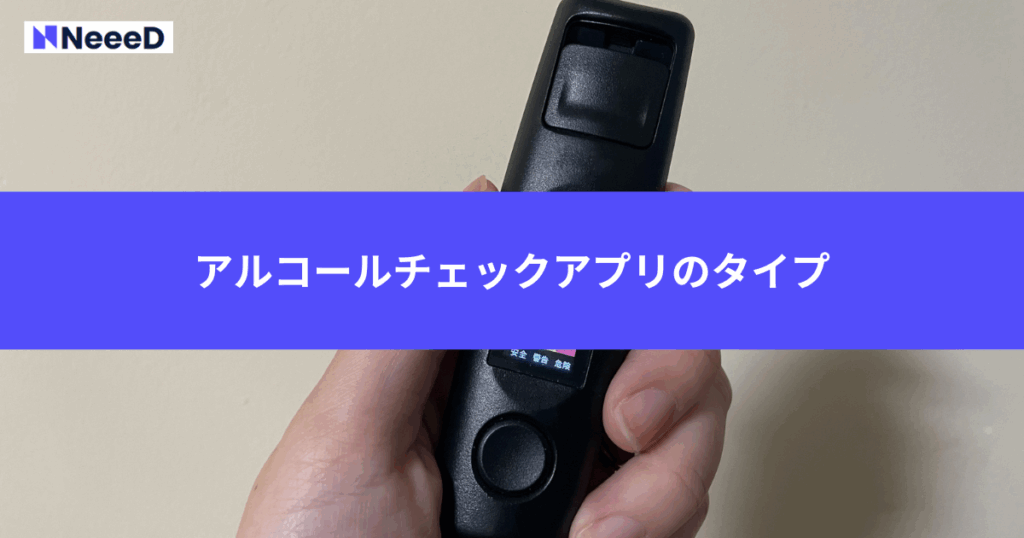
アルコールチェックアプリには多くの種類がありますが、大別すると以下の3タイプです。
それぞれ異なる強みを持っているので、あらかじめ把握して自社に合ったものを見定めておきましょう。自社の運用形態や課題に合わせて、最適なタイプを選ぶことが重要です。
アルコールチェック特化型
アルコールチェック特化型は、アルコールチェックを実施するために必要な機能のみを搭載したタイプです。アルコールチェックの測定結果を自動で記録することに機能が限定されているものが多く、低コストで導入できます。
最小限の機能といっても、アルコール検知器との連携、測定結果の自動記録、クラウドでのデータ保存、管理者へのアラート通知などの必要な機能はすべて備わっています。
特化型のアルコールチェックアプリが向いているのは、小規模事業者や、既存の車両管理システムや運行管理システムを既に導入しており、アルコールチェック機能のみを補完したい事業者です。
ただし、アルコールチェック以外の車両管理や運行管理機能は付いていないため、それらの業務は別途システムや手作業で行う必要があります。低コストで検知性能の高いアルコールチェックアプリを導入したい場合は、特化型が適しているでしょう。
IT点呼一体型
IT点呼一体型は、IT点呼サービスと一体化しているアルコールチェックアプリです。このタイプの特徴は、基本的なアルコールチェック機能に加え、テレビ電話機能や健康状態を記録できるIT点呼(遠隔点呼)の機能が搭載されていることです。
運転者はアプリ内でアルコールチェックを行い、結果をIT点呼の記録と紐付けます。安全管理者はPCやスマートフォンから、運転する従業員の健康状態をチェックできます。
ビデオ通話機能によって、管理者とドライバーが離れた場所にいても、法令に基づいた点呼(日常点検、健康状態の確認、アルコールチェックの結果確認など)の実施・記録が可能です。
IT点呼一体型が向いているのは、遠隔地に営業所や車庫があり、点呼業務を効率化したい事業者です。また、特定の条件(運行管理者の配置状況など)を満たす必要がある運送事業者にも、このタイプがおすすめです。
車両管理一体型
車両管理一体型は、IT点呼一体型よりもさらに多様な機能が搭載されたタイプのアルコールチェックアプリです。
アルコールチェックやIT点呼の機能に加え、車両の位置情報を取得したり、運行情報や点検記録、免許証管理までできるなど、広範な車両管理業務をカバーできます。
他にも、日報の作成機能や車両管理台帳、安全運転管理に関する機能など、車両管理に関する業務を包括的に効率化できます。
車両一体型タイプが向いているのは、車両台数が多く、運行管理業務が複雑化している運送業や、車両管理のデジタル化を一気に進めたい事業者です。
アルコールチェックの義務化について

アルコールチェックは、業務で自動車を使用する企業や事業者に義務付けられている、酒気帯び運転を未然に防ぐための法定点検です。
以前は、タクシーやトラックなどの「緑ナンバー」を運転する事業者(運送業など)に限定されていましたが、2021年6月に発生した悲惨な飲酒運転事故をきっかけに、義務化の対象が拡大されました。
2022年4月からは、営業車や社用車といった「白ナンバー」の車両を運転する事業者もアルコールチェックの義務化対象となっています。
現在では、運送業に限らず、一般企業でも運転を伴う業務を行う場合は、アルコールチェックを行わなくてはなりません。
参照元
義務化の対象となる事業者の規模
アルコールチェックの実施が必要な事業者は以下の通りです。
- 緑ナンバーの自動車を保有する事業者
- 乗車定員11人以上の自動車を保有する事業者
- 白ナンバーの自動車を5台以上保有する事業者
上記の条件のいずれかに該当する場合は、社内で安全運転管理者を選任し、アルコールチェックを実施することが義務づけられます。
なお、自動二輪車(オートバイ)などもアルコールチェックの対象範囲です。自動二輪車は0.5台として計上され、ナンバーのついた小型特殊車両、大型特殊車両も1台として計上されます。
アルコールチェック未実施業者への処分
現在の道路交通法において、運転前のアルコールチェックを怠った「行為そのもの」に対して、直接的な罰則や罰金は定められていません。 例えばスピード違反のように、その場で反則切符が切られ、罰金を科されることはないということです。
しかし、アルコールチェックが適切に実施されない状態が続くと、安全運転管理者の義務違反とみなされ、次のような行政処分が課される可能性があります。
- 公安委員会からの是正措置命令
- 公安委員会からの解任命令
是正措置命令に従わない場合や、義務違反の状況が改善されないと判断された場合、安全運転管理者の解任命令が出されることもあります。
さらに、これらの是正措置命令や解任命令に従わなかった場合には、道路交通法に基づき、「50万円以下の罰金」が科されます。これはアルコールチェックそのものを怠ったことに対する直接的な罰則ではなく、公安委員会の命令に違反したことに対する罰則です。
車両を使う事業者は、安全運転管理者を選任し、職務を適切に遂行させることが求められており、アルコールチェックの実施は、その重要な一つです。
参照元
アルコールチェックアプリにかかる費用相場
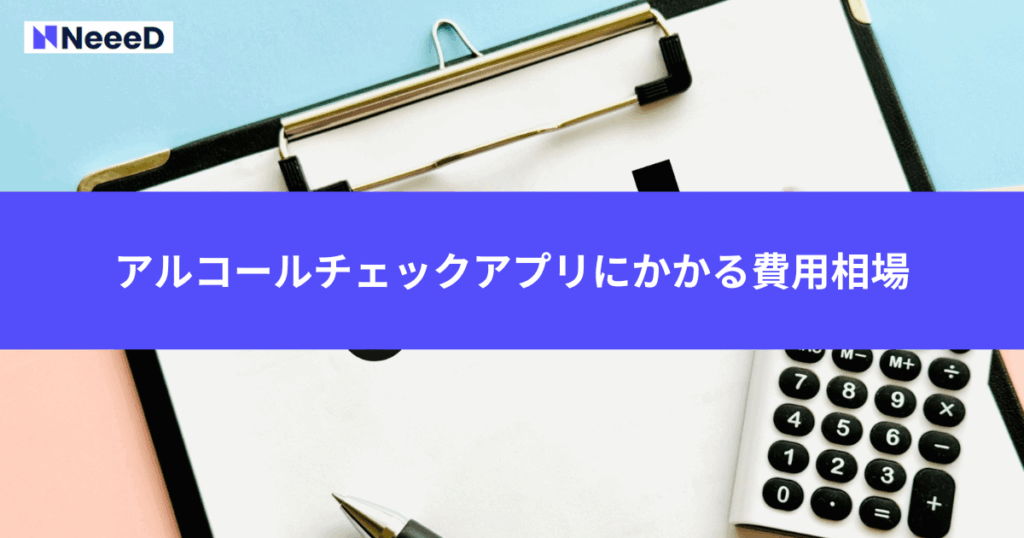
アルコールチェックアプリにかかる費用は、選ぶサービスやプランによってさまざまです。しかし、どのようなサービスでも、料金の内訳は基本的に「初期費用」「アルコール検知器本体の購入またはレンタル費用」「月額費用」「オプション費用」の4つに分解して考えることができます。
ここでは、それぞれの費用項目について、その相場と内容を詳しく解説していきます。
アルコールチェックアプリを導入する際、費用は重要な判断材料の一つです。料金体系はサービス内容や契約プランによって異なりますが、一般的には次の3つで判断します。
以下、それぞれの費用相場について詳しく解説します。
初期費用
アプリ導入時の初期費用は、導入支援やシステム設定の有無によっても異なりますが、管理システムの場合は15,000円〜20,000円程度が相場です。
初期設定、アカウント登録、検知器との連携設定などが含まれます。導入説明やサポートが手厚いサービスは、やや高額になる傾向があります。
初期費用が無料のサービスもありますが、月額費用や検知器代が高めに設定されているケースもあります。
アルコール検知器本体の購入またはレンタル費用
アプリ本体とは別に、アルコール検知器本体の購入(またはレンタル)費用もかかります。
- 安価な半導体式:数千円〜
- 高精度な電気化学式:2万円〜4万円程度
義務化に対応した業務用途では、高精度のアルコール検知器が必要になるため、導入にはある程度の初期投資が必要です。
月額費用
アプリ利用にかかる月額費は、主に利用人数と使える機能によって決まります。一般的なアルコールチェックアプリの月額は、800円~3,000円程度が相場です。
基本的なチェック記録・管理機能を備えたプランであれば、多くのサービスは月額1,000円前後で利用できます。
ドライバー1人あたりで課金されることが多く、多機能なプランほど月額費が高くなる傾向があります。
オプション・追加費用
より高度な管理機能や自動化を求める場合は、オプション機能が必要になります。代表的なオプション機能としては、以下のようなものがあります。
- 顔認証による本人確認
- IT点呼機能(遠隔点呼)
- 詳細レポート作成
- 運転日報の自動生成
- テレマティクス機能(走行・位置データ管理)
- 車両や免許の有効期限管理
このような機能は標準プランには含まれず、必要に応じて追加料金が発生することがほとんどです。
アルコールチェックアプリ導入のメリット
アルコールチェックアプリの導入には、次のようなメリットがあります。
順番に解説していきます。
管理業務が効率化できる
アルコールチェックに関する業務を効率化できることが、アプリ導入の大きなメリットです。
従来は、運転手が運転前後にアルコール検知器を使ってチェックを行い、その結果を手書きなどで記録する必要がありました。記録は各営業所ごとに保管され、管理者がその内容を確認・管理する手間もかかっていました。
アルコールチェックアプリを導入すれば、これらの管理業務を大幅に効率化できます。測定データは自動で記録・保存され、管理者による手作業での転記や集計が不要になり負担が軽減します。
また、記録の入力が必要なくなるため、入力漏れやミスがなくなるのもメリットです。
遠隔地でもリアルタイムで結果が分かる
アプリを導入することで、地理的な制約にとらわれずアルコールチェックの管理が可能になります。 スマートフォンとアルコール検知器さえあれば、ドライバーは会社から離れた場所でもチェックを実施できます。
直行直帰のドライバーや出張先から運転を開始するケースでも、これまでは難しかった目視による確認を、アプリを通じて確実に行えるようになります。
また、測定結果はクラウドに即時アップロードされるため、管理者はオフィスや自宅など、どこにいてもリアルタイムでチェック可能です。ドライバーの状態を常に把握できるため、万が一異常があった場合も、迅速に対応できます。
コンプライアンス(法令遵守)が強化される
アルコールチェックアプリを導入することで、コンプライアンス(法令遵守)を強化できます。
従来のアルコールチェックは測定結果を手入力で行うため、数値を改ざんすることも可能でした。しかし、アルコールチェックアプリでは測定結果が自動で記録されるため、数値の改ざんは不可能です。
結果として、従業員が測定結果を無視して飲酒運転をするリスクがなくなり、コンプライアンスを徹底できます。
アプリによっては「デジタルキー」という専用のツールを使って、アルコールチェックを行わなかったり数値に異常があったりする場合に、車の鍵が作動しなくなるように設定できるサービスもあります。
ペーパーレス化でコスト削減になる
アルコールチェックアプリの導入は、ペーパーレス化によるコスト削減にもつながります。
記録はクラウド上に保存されるため、紙での記録が必要なくなります。紙が必要なくなれば、記録を保存する場所の確保や用紙代、印刷代などが必要なくなり、これもコストの削減につながります。
記録はすべてクラウドに保存されるため、用紙代・印刷代・保管スペースが不要になり、その分のコスト削減が可能です。
また、紙での保管にともなう記録の紛失や盗難といったリスクも軽減できます。火災や災害によって記録が消失する心配もなくなるため、より安全かつ確実にデータを保存できるのも大きなメリットです。
アルコールチェックアプリの選び方・比較ポイント
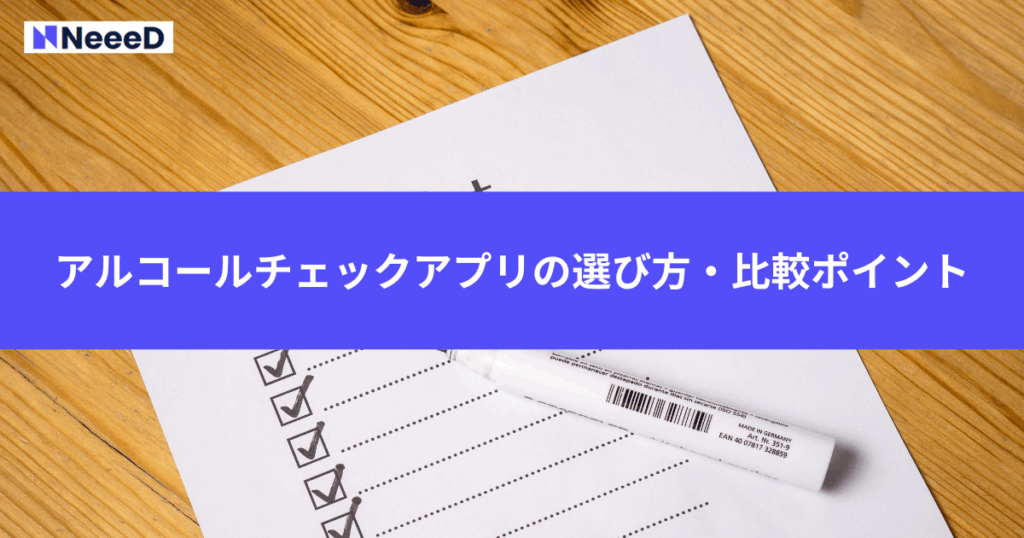
アルコールチェックアプリを導入する際は、数多くのサービスの中から自社に最適なものを選ぶことが大切です。以下に、主な選び方・比較ポイントをまとめました。
比較するときは費用だけでなく、機能性、使いやすさ、サポート体制など、多角的な視点を検討する必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
測定方式・検知精度
アルコールチェックの信頼性は、アプリと連携させる「アルコール検知器」の精度に大きく左右されます。精度や価格を決定づける重要な要素が、センサーの「測定方式」です。
主な測定方式には、以下の3つがあります。
- 半導体式
- 燃料電池式
- NDIR方式
半導体式は小型で取り回しが良く、比較的低価格で購入できます。ただし、アルコール以外の物質(タバコの煙など)に反応しやすい傾向があり、周囲の環境や前後の食事によって測定結果が左右されやすいのがデメリットです。
燃料電池式は半導体式よりも検知精度に優れていますが、測定に時間がかかる上、購入費や維持費が割高となります。
NDIR方式は反応時間も早く、検知精度も高い最新のアルコール検知器です。他の2つの方式よりも価格が高額なのが難点ですが、センサーの寿命が長いため、長期で利用できます。
アルコールチェックアプリは上記のうちの1つまたは複数に対応しているものが多いです。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の運用方針に合った検知器が利用できるアプリを選びましょう。
必要な機能があるか(なりすまし防止機能・通知機能など)
次に確認したい比較ポイントは、必要な機能がアプリに備わっているかどうかです。特に重視したいのは、なりすまし防止機能と通知(アラート)機能の2つです。
- なりすまし防止機能…測定時にスマートフォンのカメラで顔写真を自動撮影したり、GPSで位置情報を記録したりする機能
- 通知機能…測定結果に異常値が検出された際や、チェックが未実施の場合に、管理者と本人へ即座に警告(アラート)を送信する機能
他にも、検知器とBluetoothで自動連携したり、測定結果をOCR(画像認識)で読み取って自動記録できる機能があると、手入力による手間が省けるだけでなく、入力ミスや改ざんリスクも防げます。
さらに、車両管理や運転日誌作成など、アルコールチェック以外の「業務支援機能」が必要なケースもあります。これらは手間やコストを削減できるため、導入検討の際には大事な比較ポイントになるでしょう。
対応している検知器の種類は豊富か
アプリが対応しているアルコール検知器の種類も確認すべきポイントです。対応機種が豊富であれば、自社の運用形態に合ったタイプを選べます。
検知器の種類は大きく分けて、営業所に設置して複数のドライバーが共用する「据え置き型」と、ドライバーが携帯してどこでも測定できる「モバイル型」があります。
ドライバーの勤務形態が多様な企業では、直行直帰が多いケースや複数の営業所が拠点になる場合もあります。アルコールチェックアプリを選ぶ際は、こうした勤務スタイルに対応できる柔軟性があるかを確認しましょう。
また、既にアルコール検知器を所有している場合や、特定の検知器を使いたい場合にも、アプリがその検知器に対応していれば、購入費を節約できます。
アプリによっては、特定のメーカーやモデルの検知器にしか対応していない場合もあります。既存機器を活用できるか、新たな検知器購入が必要になるかによって、トータルコストが変わります。
コスト・料金体系はどうか
アルコールチェックアプリを選ぶ際には、導入費用や月額費用など、導入と運用にかかるトータルコストを把握することが重要です。
初期費用には、クラウド環境の構築やアカウントの作成、検知器の購入費も含まれます。月額費用には、アプリの運用料やクラウドサービスの維持費などがあります。他にも、オプション費用や検知器の購入費用やレンタル費用、メンテナンス・校正費用を算出します。
中には利用できる機能が限定されるものの、月額費用が無料のサービスもあります。予算や求める機能に合ったアプリを選択しましょう。
また、無料トライアルがあるサービスであれば、実際に使ってみて使い勝手や機能を試すことができます。
管理・運用がしやすいか
データのクラウド保存ができるか、管理を一元化できるか、操作が直感的で使いやすいかなど、サービスの使いやすさを確認しましょう。
測定データがクラウド上に自動保存され、管理画面から一括で確認・操作できるシステムであれば、日々の業務負担が軽減されます。
また、CSV出力やレポート自動作成などの機能も、記録の整理や提出を効率化するのに役立ちます。義務化された記録の保存形式や提出方法に対応しているかどうかもポイントです。
実際の運用をイメージしながら、管理業務の手間がどれだけ減るかを具体的にシミュレーションしてみましょう。
サポート・フォロー体制は万全か
サポートやフォロー体制の充実度は、アルコールチェックアプリ導入後の安心感に関わる重要なポイントです。
導入時の初期設定や操作方法に不安がある場合も、サポートが手厚いサービスなら不安が軽減します。運用中にトラブルが起きたり不明点が生じたりしても、迅速な対応体制が整っていれば、業務に支障が出るリスクを抑えられます。
問い合わせ窓口の選択肢(電話、メール、チャットなど)、緊急時の対応時間も確認しましょう。
また、アルコール検知器は定期的なメンテナンスが必要です。サポートが充実しているサービスなら、メンテナンス時期の管理まで任せられます。
これらのサポート体制が整っているサービスを選ぶことで、継続して利用するときにも安心です。
アルコールチェックアプリを選ぶ際に見落としやすい注意点
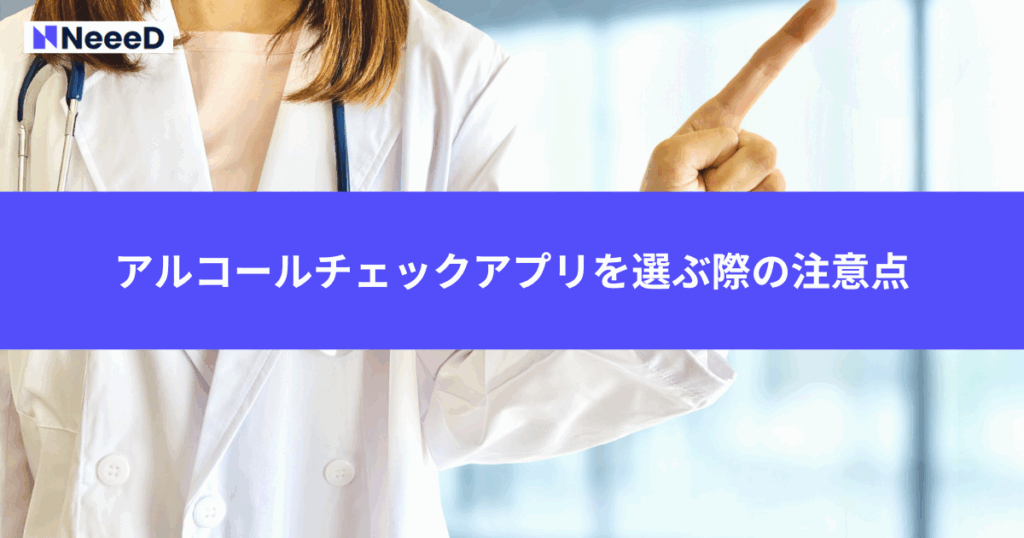
アルコールチェックアプリを選ぶ際には、機能や費用だけでなく、長期的な運用を見据えた細かな点にも目を向けることが重要です。
ここでは、アプリを選ぶ際に見落としがちなポイントを紹介します。事前に確認しておくことで、導入後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用ができるようになるでしょう。
検知器はレンタルか購入か
アルコールチェックに用いる検知器は、レンタルと購入があります。事業の規模や利用頻度に合わせて、購入かレンタルかを選択しましょう。
長期的に、かつ頻繁にアルコールチェックを行う場合は、レンタルよりも購入した方がトータルコストを抑えられるケースがあります。
一方、短期間だけ利用したい場合や、まず試験的に導入して使用感を確かめたい場合、あるいは初期費用を抑えたい場合は、レンタルが便利です。レンタルであれば、機器のメンテナンスや校正の手間もかからず、常に最新の検知器を利用できるメリットもあります。
サービスによっては、検知器のレンタル料金もプランに含まれている場合があるので、アプリの検討と合わせて比較しましょう。
使える端末(iPhone / Androidで使えるか)
アプリが動作する端末の種類は、必ず導入前に確認が必要です。ドライバーが使用するスマートフォンの機種やOS(iPhone / Android)でアプリが使えるか、事前に確認しましょう。
特定のOSにしか対応していないアプリや、古いOSバージョンでは動作しないアプリもあります。
従業員がスムーズに利用できるよう、幅広い端末に対応しているか、あるいは自社で支給している端末にアプリが対応しているかを確認してください。
アルコールチェックアプリ導入の5ステップ
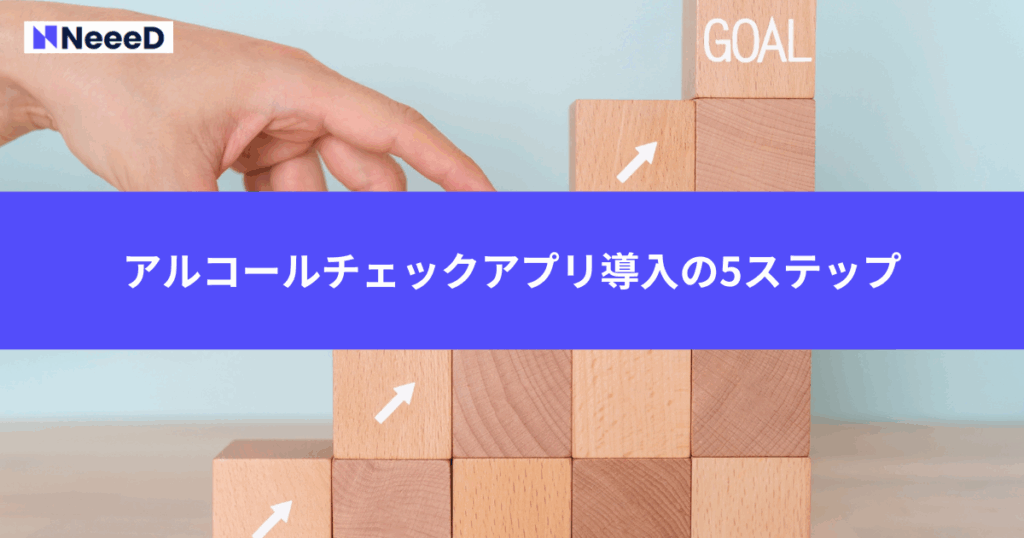
アルコールチェックアプリの導入は、計画的に進めることでスムーズに行えます。ここでは、具体的な導入プロセスを5つのステップに分けて解説します。
それぞれについて、詳しく解説します。
ステップ1:対象となる従業員と車両台数の確認
まず、自社がアルコールチェックの義務化対象となるかを確認しておきましょう。
一般的な大きさの白ナンバー車なら5台以上、乗車定員11人以上の白ナンバー車なら1台以上使用している事業者が義務化の対象です。
台数は「事業所単位」でカウントされます。また、リース車、代車、レンタカーであっても、月例的に業務で利用する車両は台数に含める必要があります。
対象となる従業員と車両の正確な台数を把握することで、必要なアプリや検知器の数、費用の概算が見えてくるはずです。
ステップ2:サービス選定
次はアルコールチェックアプリサービスの選定です。 会社の運用規模(従業員数、拠点数など)や、必要な機能(クラウド管理、顔認証、車両管理、IT点呼機能など)を具体的に検討し、それに合致するサービスを絞り込みます。
ステップ3:導入準備
サービスを選定したら、具体的な導入準備に進みます。まずは利用契約の手続きです。社内で稟議を通し、予算を確定させたうえで、ベンダー側と契約条件を調整します。
導入スケジュールを決め、必要な機器(アルコール検知器など)の発注や、アプリのアカウント申し込みをするのも、この段階です。
その後は、運用開始に向けて、検知器の初期設定やアプリのインストール、各ドライバーのアカウント登録などを行います。
こうした準備を段階的に進めておくことで、スムーズに運用開始できます。
ステップ4:従業員への周知
アプリの準備が整ったら、実際に利用するドライバーや関係従業員への周知と教育を行いましょう。
ドライバーや利用者にアプリの使い方、測定手順、記録保存の重要性などを説明します。なぜアルコールチェックが必要なのか、アプリを使うことで何がどう変わるのか、などを全員に理解してもらうことが大切です。実際にアプリを操作してもらう研修時間を設けることも有効です。
また、アルコールが検知された場合の対応フローなど、運用ルールを徹底し、疑問点や不安を事前に解消しておきましょう。
ステップ5:アルコールチェック実施業務の定着
準備と周知が完了したら、いよいよアルコールチェックアプリの本格運用を開始します。
ドライバーは、定められた手順に従ってアルコールチェックをアプリで実施します。管理者は、クラウド上の管理画面でリアルタイムに記録を確認し、チェック漏れがないか、異常値が出ていないかを都度確認します。
異常値が出た際のアラート対応や、未実施者へのリマインド、日々のデータの管理・集計といった業務フローを確立し、定着させていくことが重要です。
定期的に運用状況を振り返り、改善点があれば見直していくことで、より効率的で確実なアルコールチェック体制を維持できるでしょう。
アルコールチェックアプリ・比較に関するよくある質問(FAQ)
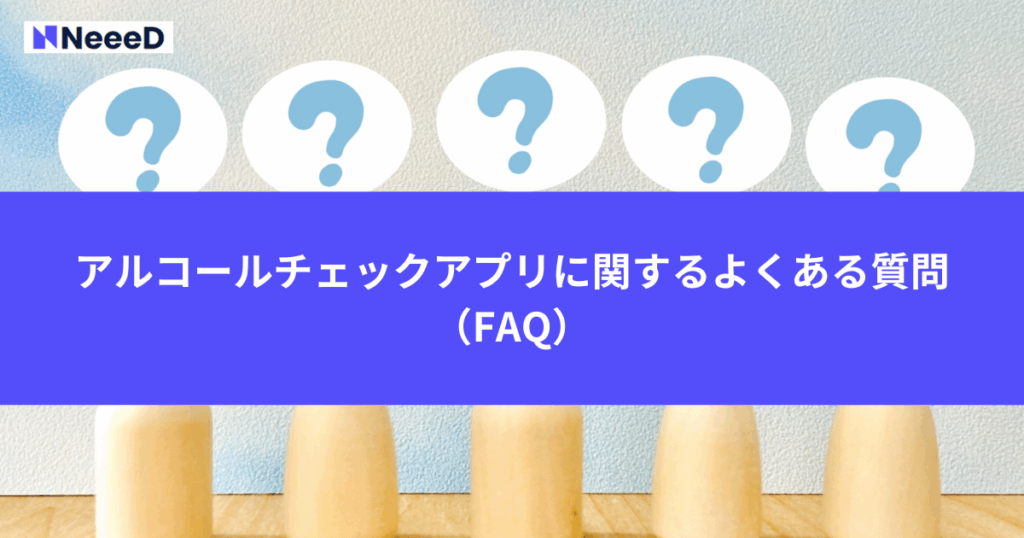
最後に、アルコールチェックアプリの導入や比較検討の際に、多くの人が疑問に思う「よくある質問」をQ&A形式でまとめました。
基本的な使い方からコスト、機器の精度、法令対応まで、導入前に知っておきたいポイントを網羅しています。疑問を持っている方は気になる部分をお読みください。
スマホだけでアルコールチェックは可能?
スマホ単体だけでは呼気中アルコール濃度の測定はできません。
アルコールチェックを行うには、必ず専用のアルコール検知器が必要です。
スマホアプリは、検知器で測定した結果を記録・管理するためのツールであって、専用の検知器と連携して機能するものです。
厚生労働省の無料アルコールチェックアプリとは?
厚生労働省が提供している無料のWebアプリで、正式名称は「アルコールウォッチ」です。
スマートフォンやPCブラウザで利用でき、飲酒したお酒の種類と量を入力することで、純アルコール量とアルコール分解時間を簡単に把握できます。
ただし、「アルコールウォッチ」は、あくまで参考情報を提供するもので、事業者が法令で求められる酒気帯び検査の代替にはなりません。
法令遵守のためには、必ず専用のアルコール検知器による測定が必要です。
アルコールチェックアプリはいくらくらいしますか?
アルコールチェックアプリの費用は、サービス内容や機能によって異なりますが、一般的な月額費用は1ユーザーあたり800円~3,000円程度が相場です。
多くのサービスは月額1,000円前後で基本的な機能(測定データの自動記録・管理、クラウド保存など)を利用できます。
これとは別に、初期費用やアルコール検知器本体の購入・レンタル費用がかかります。
アルコールチェックアプリは自作できる?
アルコールチェックアプリを自作することも可能です。アプリ作成ツールや業務アプリ開発プラットフォームなどを使えば、プログラミングの専門知識がなくてもアルコールチェックアプリを自作できます。
しかし、職務で使うアプリを自作するのはハードルが高いといえます。法令で求められる記録要件を満たし、検知器との連携や本人確認機能(顔認証など)の実装など、現場運用に耐える設計には高度な技術と専門知識が求められます。
そのため、アルコールチェックを法令に準拠した形で確実に行う必要がある企業では、実績のある市販サービスを選定し、必要に応じて一部カスタマイズする方法が現実的です。
コスト面でも、自作と維持管理の手間を考慮すると、既存サービスの導入が結果的に合理的な選択になることが多いでしょう。
アルコールチェックアプリの無料トライアルはある?期間は?
多くのアルコールチェックアプリサービスでは、無料トライアル期間を設けています。期間は1週間〜1ヶ月程度が多く、サービスによって異なります。
無料トライアル期間中は、アルコール検知器の無料貸し出しがセットになっていて、実際の使用感を試すことができます。
トライアル期間終了後はそのまま本契約に移行できるのが一般的ですが、途中解約や期間延長の条件はサービスによって異なるため、申し込み前に確認することをおすすめします。
アルコールチェックアプリの市場シェアは?
日本では道路交通法改正によるアルコールチェック義務化の影響で、事業者向けの需要が増えており、今後も市場の拡大が見込まれます。多くの企業が、様々な機能や料金体系のサービスを提供しています。
アルコールチェックアプリの市場シェアについては、調査会社や調査対象の範囲(緑ナンバー向け、白ナンバー向け、特定の機能に特化など)によって結果が異なりますが、当記事で紹介したアプリは、どれも市場シェアの上位を占めるものです。
アルコールチェックはどの数値までセーフですか?
道路交通法上、呼気中アルコール濃度が「0.15mg/L未満」であれば違反になりません。
しかし、これはあくまで法令上の基準であり、少しでもアルコールが検出された場合は運転を控えるべきです。
安全運転管理の観点からは、アルコールが完全に抜けている状態での運転を徹底することが大事です。
アルコール検知器の校正頻度は?
アルコール検知器の精度を維持するためには、定期的なメンテナンスや校正が必要です。自社で行うか、外部業者に依頼して実施する必要があります。
検知器のメンテナンス・校正頻度は機種によって異なりますが、一般的には「使用開始から6ヶ月~1年半」または「使用回数1,000回~数万回」が目安とされています。検知器の取扱説明書やメーカー推奨の期間を必ず確認してください。
校正を怠ると、測定精度が低下して正確なアルコールチェックができなくなり、結果的に法令違反となるリスクがあります。
アルコールチェックアプリはクラウドなしでも使える?
アルコールチェックアプリの多くは、測定データをクラウド上に保存・管理することで、リアルタイムでの確認や一元管理を実現しています。
しかし、すべての端末がクラウド連携に対応しているわけではありません。クラウド非対応やオフラインで使えるアルコールチェッカーも多数市販されており、これは携帯型モデルが多いです。
クラウド非対応の端末は、検査日時や測定値を本体に一定件数(例:50件など)まで保存でき、ネット環境のない現場や小規模な事業所での利用に適しています。
ただし、データの自動集計や記録の一元管理ができないため、手作業での記録確認や報告が必要になり、長期的には運用の手間が増える可能性があります。
また、法令で求められる保存形式や提出要件を満たせない場合もあるため、導入時には注意が必要です。
まとめ:アルコールチェックアプリは測定方式や機能で選ぼう
アルコールチェックアプリのおすすめサービスや導入メリット、比較時のポイントについて解説しました。
アルコールチェックアプリは、義務化への対応だけでなく、安全運転管理の効率化にも役立ちます。アプリを選ぶ際は、検知精度と必要な機能が備わっているかをしっかり確認しましょう。
低価格でシンプルな機能のアプリから、IT点呼や車両管理といった周辺業務までカバーする多機能型アプリまで、選択肢は多いです。予算とのバランスも考慮しながら、自社がどこまで業務を効率化したいかを明確にしたうえで比較しましょう。
この記事を参考に、ぜひ貴社にぴったりのアルコールチェックアプリを見つけてください。

の口コミや評判は?選べる料金プランや導入メリットも解説-300x158.jpg)