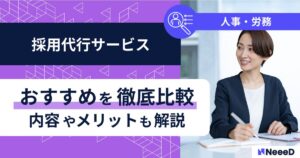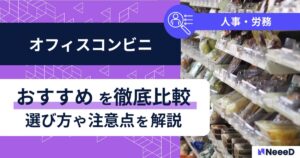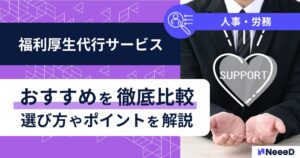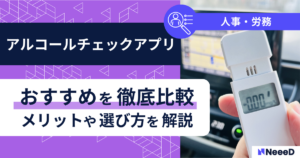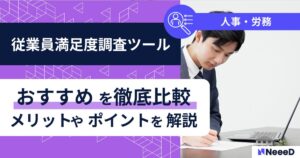【26年1月最新】給与計算ソフトおすすめ4選を比較!事業規模に合った選び方やタイプも解説
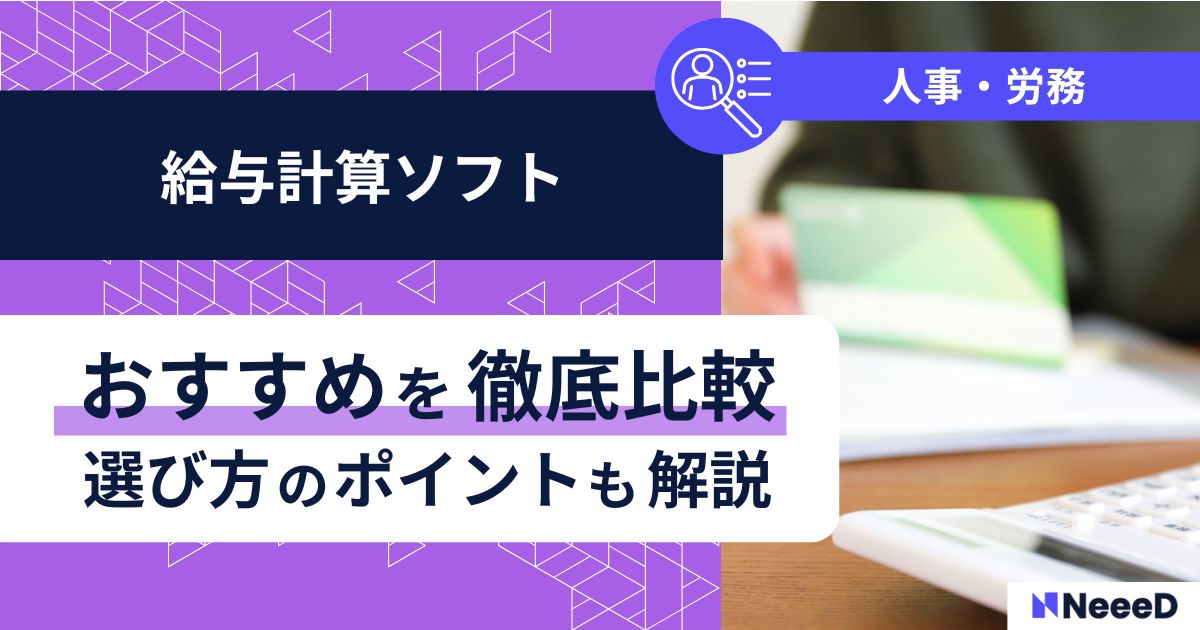
従業員の給与計算は、企業の業務の中でも特にミスが許されない業務です。そのため、計算の自動化によってヒューマンエラーを防止できる他、業務効率化にもつながる給与計算ソフトの導入を検討する企業が増えています。
しかし、「どの給与計算ソフトを選べばいいか分からない」という人も多いでしょう。
当記事ではおすすめの給与計算ソフトを紹介します。給与計算ソフトの選び方や導入メリット・デメリットなども解説しているので、当記事を読めば自社に合った給与計算ソフトを選べるようになります。給与計算ソフトの導入を検討している方はぜひご覧ください。
おすすめの給与計算ソフト4選

給与計算ソフトのおすすめを4つ紹介します。各製品の特徴は以下の通りです。
| おすすめの給与計算ソフト | 特徴 |
|---|---|
| ジョブカン給与計算 | 低コストで導入が可能 |
| freee人事労務 | 中小企業を中心に高い導入実績 |
| マネーフォワードクラウド給与 | 連携性の高さが最大の特徴 |
| Web明細くん | 給与明細の発行や管理に焦点を当てた製品 |
それぞれ異なる強みを持っているので、自社に合ったものを選択しましょう。
ジョブカン給与計算

| 料金プラン | 初期費用:無料月額費用:1ユーザーあたり440円~ |
|---|---|
| 機能 | ・同社サービスとの連携機能 ・給与規定グループ機能 ・自動アップデート機能 ・帳票作成・出力機能 ・マイナンバー管理機能 など |
| タイプ | 給与計算特化型 |
| 導入実績 | ・株式会社石橋楽器 ・湘南造機株式会社 ・株式会社ネクストリンク など |
| 会社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階 |
ジョブカン給与計算は中小企業でも導入しやすい給与計算特化型の給与計算ソフトです。
クラウド型なこともあり初期費用が無料で、月額料金も1ユーザーあたり440円から利用できるなど、中小企業でも導入がしやすい価格設定になっています。
給与計算特化型ということもあって、機能は給与計算業務に関するものに絞られています。しかし、同社が提供する他のシステムと連携することで、より給与計算業務を効率化することが可能です。
セキュリティについても情報の暗号化やログ管理機能など、必要な機能がそろっているため、安心して個人情報を扱えます。低コストで給与計算業務をピンポイントに効率化したい企業におすすめの給与計算特化型ソフトです。
freee人事労務
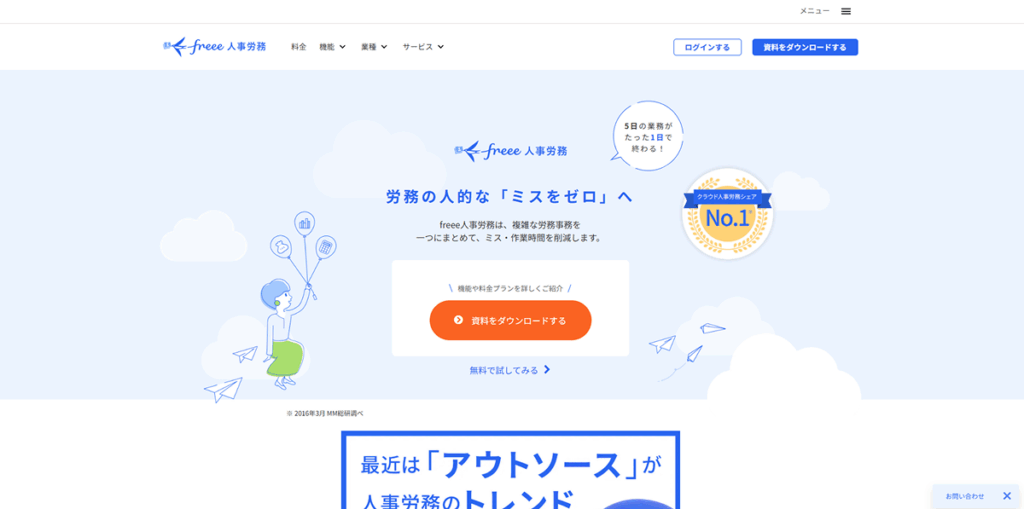
| 料金プラン | 初期費用:無料 月額利用料:2,000円~ |
|---|---|
| 機能 | ・給与計算機能 ・Web給与明細の作成機能 ・年末調整機能 ・勤怠管理機能 など |
| タイプ | 人事給与型 |
| 導入実績 | ・株式会社DNソリューションズ ・カーズ株式会社 ・株式会社PIGNUS など |
| 会社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 |
クラウド会計で知られるfreeeが展開するfreee人事労務は、人事・労務の煩雑な業務をまとめて管理できるサービスす。給与計算だけでなく、勤怠管理や社会保険料の自動計算、年末調整の電子申請、マイナンバーの取り扱いまで広くカバーし、管理業務の自動化を支援します。
また、法改正や保険料率の変更にも自動で対応する仕組みが整っており、運用中の設定変更やメンテナンスの必要性も少ないです。さらに、スマートフォンやSlackといった外部ツールとの連携にも対応し、テレワーク体制にも柔軟に対応できる点が評価されています。
中小企業を中心に高い導入実績を持ち、給与計算だけでなく、人事労務に関連する業務全般を効率化したい企業におすすめです。
マネーフォワードクラウド給与

| 料金プラン | 初期費用:無料 月額利用料:2,480円~ |
|---|---|
| 機能 | ・給与・賞与計算機能 ・所得税計算機能 ・各種控除額の自動計算機能 ・Web給与明細機能 など |
| タイプ | 給与計算特化型 |
| 導入実績 | ・株式会社デジタルキューブ ・株式会社FOR YOU ・バルス株式会社 |
| 会社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
マネーフォワードクラウド給与は、給与計算に関する作業を効率化できるクラウド型ソフトです。最大の特徴は連携性の高さで、同社の展開する各製品だけでなく、外部の勤怠管理システムや労務管理システムと連携できます。
ダッシュボードが見やすく、直感的な操作が可能なことも特徴で、前月比較機能など、分析に活用できる機能も豊富に搭載しています。
給与計算機能や年末調整機能、Web給与明細の作成・管理機能など、基本的な機能が網羅されているため、シンプルな給与計算ソフトとしても運用可能です。
Web明細くん

| 料金プラン | 初期費用:無料 月額費用:1ユーザーあたり40円~ |
|---|---|
| 機能 | ・給与明細 ・届出機能 ・アンケート機能 ・アカウント自動配布機能 など |
| タイプ | Web明細ソフト |
| 導入実績 | ・小野建株式会社 ・株式会社リフレッシュセンター ・梨湖フーズ株式会社 など |
| 会社所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-5-6 日本橋大江戸ビル9階 |
Web明細くんは、給与明細の電子化を超え、担当者の業務効率を大幅に向上させるソフトです。
給与計算業務の中でも給与明細の発行や管理に焦点を当てた製品となっており、給与明細の電子化によるペーパーレス化や、住所変更などの申請を円滑に処理する機能などが搭載されています。
従業員にはアカウントが自動配布され、社員番号や氏名の入力のみで明細を簡単に取得することが可能です。
また、特定の従業員に重要な通知を送信できる個別メッセージ機能や社内報配信機能、アンケート機能なども搭載されており、組織内のコミュニケーション強化にも活用できます。
1ユーザーあたり40円から導入できる手軽さも魅力で、コストを抑えて給与明細の発行や管理を効率化したい企業におすすめです。
給与計算ソフトを選ぶ際の13の比較ポイント
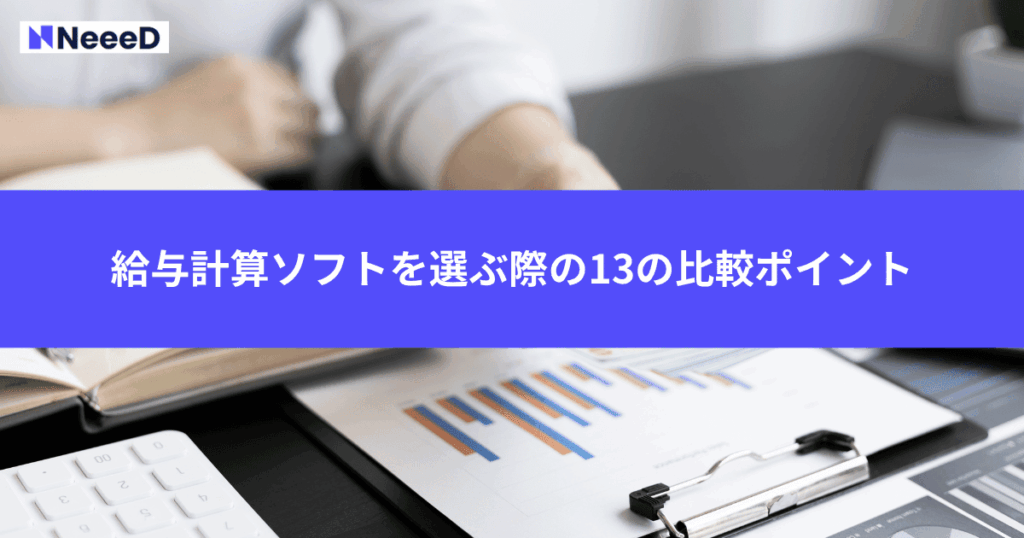
給与計算ソフトを選ぶ際には、以下のようなポイントを確認しましょう。
特に既存システムとの連携を考えている場合は、自社で導入しているシステムと連携が可能か、あらかじめ確認しておくことが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の事業規模に合っているか確認する
まずは導入を検討している給与計算ソフトが、自社の事業規模に合っているか確認しましょう。
給与計算や労務管理は事業の規模が大きくなるほど複雑化する傾向にあります。従業員数が増えることで参照するデータが増える他、階級や手当の種類なども多様化するため、要件定義が難しくなりがちです。
そのため、大企業や従業員の多い中小企業では、カスタマイズ性が高い給与計算ソフトを導入する必要性が高くなります。
一方で、小規模の企業の場合は給与計算のルールがシンプルであることが多いため、必要最低限の給与処理や社会保険対応が行えるソフトで十分なことが多いです。
給与計算ソフトを選定する際には、対応可能な機能範囲や拡張性を確認し、自社の体制に合ったものを選びましょう。
対応可能な業務範囲を確認する
給与計算ソフトを選ぶ際には、対応可能な業務範囲も確認しましょう。給与計算ソフトの中には、給与計算以外の業務にも対応しているものもあります。
例えば、ERP型の給与計算ソフトであれば、社内の業務全体の効率化につなげることが可能です。また、人事給与型の給与計算ソフトの場合は、人事関連の業務全般に対応できます。
加えて、業務範囲が広い給与計算ソフトを導入することで、それぞれの業務で必要なデータをシームレスに活用できるため、転記漏れや入力ミスを避けることが可能です。
給与計算ソフトを選ぶ際には、効率化したい業務範囲を明確にし、対応できるものを選択しましょう。
必要な機能は網羅されているか確認する
必要な機能が搭載されているかも、給与計算ソフトを選ぶ際の重要なポイントです。給与計算ソフトは製品によって搭載されている機能が異なります。
例えば、給与計算に特化しているソフトは導入・運用コストが抑えられる反面、人事に関する機能や基幹業務との連携機能などが搭載されていません。
そのため、あらかじめ利用できる機能を確認しておかないと、想定通りの運用ができないということがあります。
給与計算ソフトを選ぶ際には、自社に必要な機能を明確にし、必要な機能を利用できるサービスを選びましょう。
自社の体制や業務フローに適しているか確認する
給与計算ソフトを選ぶ際は、自社の体制や業務フローに適しているかも確認しましょう。既存の業務手順に無理なく組み込める設計であれば、導入後の混乱や業務負荷を抑えられます。
部門ごとの役割分担や承認プロセスの有無など、社内体制に応じて求められる柔軟性も異なるため、検討しているソフトが自社の体制に合致するかをあらかじめ確認することが重要です。
特に複数部門が関わるフローを汲んでいる場合や、イレギュラーな業務が多い企業の場合は、ソフトのカスタマイズ性や設定項目の豊富さを確認しておきましょう。
自動計算できる範囲を確認する
給与計算ソフトを選ぶ際には、自動計算できる範囲も確認しましょう。例えば、残業代や深夜手当、賞与などを自動で正確に算出できる機能があれば、担当者の手作業を大きく削減できます。
また、法改正に合わせて税率や保険料率が自動で変更されるサービスであれば、それぞれの計算方法で更新を行う必要もないので、給与計算業務を効率化することが可能です。
特に給与計算方法が特殊な業種の場合は、自社の給与計算業務をいかに自動化できるかに注目しましょう。
他のシステムとの連携性を確認する
既存システムとの連携を考えている場合は、それぞれの連携性についても確認しましょう。給与計算ソフトには外部システムと連携することで、より業務を効率化できるものがあります。
例えば、勤怠管理システムや会計ソフトと連携すれば、残業時間や休日出勤などのデータの給与計算への活用できる他、会計ソフトでの給与仕訳の入力も不要になります。
また、ERPと連携すれば、業務に関連するデータを一元管理し、各業務でシームレスに活用することが可能です。API連携に対応している製品であれば、連携も気軽に行うことができるため、給与計算ソフトを選ぶ際はあらかじめ確認してみましょう。
業界特有のニーズに対応しているか確認する
特殊な給与計算が必要な業界の場合は、業界特有のニーズに対応しているかも確認しましょう。
たとえば建設業では、日雇いへの対応や現場単位の支給管理が必要になります。また、医療業界のようにシフトや雇用形態が複雑な業種の場合も、一般的な給与計算ソフトでは対応が困難です。
業界特化型のソフトであれば、それぞれの業界の慣習に則った設定やカスタマイズが可能なので、スムーズな導入・運用が行えます。
そのため、上記のように給与計算が特殊な業界の企業の場合は、業界に特化した製品を選ぶのがおすすめです。
サポート・フォロー体制の充実度を確認する
給与計算ソフトを選ぶ際には、サービスのサポート体制も確認しましょう。給与計算ソフトの導入時には初期設定やデータの移行が必要になるため、トラブルが発生しやすいです。
また、運用時にも給与の振込日前日や年末調整にトラブルが発生し、重大な問題につながることが少なくありません。
導入支援やヘルプデスク、チャットサポートなど、サポート体制が充実している給与計算ソフトを選べば、迅速なトラブル対応が期待できます。特に24時間365日対応しているサービスであれば、急なトラブルでも迅速に対応が可能です。
コストが自社に合っているか確認する
自社の予算に合った料金体系になっているかも、給与計算ソフトを選ぶ際のポイントです。給与計算ソフトの料金体系は、サービスによって異なります。採用されていることが多い料金体系は以下の通りです。
- 買い切り型:初期費用のみで月額費用なし
- 月額固定型:初期費用と定額の月額料金
- 従量課金型:初期費用と機能に合わせた月額料金
買い切り型の給与計算ソフトはランニングコストが発生しないため、長期運用するほどコストパフォーマンスが高くなります。一方で、定額型や従量課金型の場合は、月額料金が発生するため、ランニングコストへの考慮が必要です。
ただし、定額型や従量課金型は買い切り型と比較すると初期費用が安い傾向にあります。また、従量課金型は後から機能を追加できるのが一般的なため、事業の成長に合わせて機能を充実させることが可能です。
自社のキャッシュフローや将来性なども考慮して、自社にあった料金体系の給与計算ソフトを選びましょう。
対応している帳票の種類を確認する
給与計算ソフトを導入する際は、対応している帳票の種類を確認することが重要です。給与計算業務に不可欠な帳票が自動で出力できれば、業務効率の向上につながります。特に自動作成できるか確認したいのは以下のような帳票です。
- 給与明細
- 賃金台帳
- 源泉徴収票
上記に加え、勤労統計調査票のような管理帳票に対応していると、より業務を効率化することが可能です。特に従業員数が多い企業では、手動対応が工数やヒューマンエラーの原因になるため、必要な提出書類をスムーズに生成できる仕組みが求められます。
また、フォーマットの柔軟性やカスタマイズ性も確認しておくと、後の帳票運用に支障が出にくくなります。給与計算ソフトを選ぶ際には、自社で扱っている帳票をあらかじめ洗い出し、対応しているサービスを選びましょう。
十分なセキュリティ対策が施されているか確認する
給与計算ソフトを選ぶ際には、セキュリティ機能にも注目しましょう。給与計算業務では従業員の個人情報を扱うことになるため、セキュリティ対策が重要です。
給与計算ソフトを導入すると、給与計算に関する情報をシステム内で管理することになるため、セキュリティの強度が製品に依存します。そのため、セキュリティ対策が万全なサービスを選べば、社内のセキュリティレベルを向上させることが可能です。
給与計算ソフトを選ぶ際には、情報の暗号化機能や不正アクセス防止機能など、個人情報保護機能が万全な製品を選びましょう。
多言語に対応しているか確認する
海外拠点がある企業の場合は、多言語対応しているかどうかも重要なポイントです。外国人労働者を多く雇用している現場では、UI表示や操作画面が英語や中国語などに切り替えられる機能があると、教育や日常業務の負担を軽減できます。
給与明細や各種帳票も翻訳機能を通じて母国語で提供できれば、従業員との認識齟齬を防ぐことが可能です。
また、現地の通貨で給与を支払う場合は、為替レートの変動を給与の計算式に盛り込む必要があります。他通貨対応している給与計算ソフトを導入すれば通貨換算も自動で行えるので、業務を効率化することが可能です。
無料トライアルが用意されているか確認する
給与計算ソフトを選ぶ際には、無料トライアルを利用できるかも確認しましょう。無料トライアルが利用できる給与計算ソフトであれば、実際に導入する前に操作感や自社のシステムとの連携が可能かを確認できます。
また、サポート体制なども事前に確認できるため、導入後に想定外の問題が発生するリスクを低減することが可能です。
また、複数のサービスの無料トライアルを利用すれば、自社に必要な機能を再度洗い出せます。最適なサービスを選択するためにも、まずは各サービスの無料トライアルを試してみるのがおすすめです。
給与計算ソフトとは

給与計算ソフトとは、従業員の給与を算出するためのソフトウェアのことです。給与の計算では就業規則に則った各種手当や社会保険料、各種税金や控除などを加味する必要があるため、計算式が複雑になります。
また、従業員ごとに参照する数値が異なるため、手動で行うと計算ミスなどのヒューマンエラーが発生しがちです。
給与計算ソフトを利用すれば、複雑な給与の計算を自動化できます。普段の給与計算だけでなく、賞与や年末調整の計算も行えるため、給与計算に関する業務を大幅に効率化することが可能です。
給与計算ソフトのシェアについて
給与計算ソフトの市場では、導入実績が豊富な大手ベンダーが高いシェアを維持しています。特に日本国内では、クラウド型サービスの普及に伴い、柔軟な機能と使いやすさを兼ね備えたソフトが中小企業を中心に人気です。
一方で、大企業向けには人事管理や勤怠管理と連携できる統合型の給与システムが選ばれる傾向があります。近年は多言語対応やグローバルな法制度への対応のために、海外製の給与計算ソフトを導入する企業も多いです。
市場シェアの高さは、単なる導入数だけでなく、継続利用されているかどうかにも注目する必要があります。給与計算ソフトを検討する際は、人気ソフトや主要ベンダーの実績を参考にし、自社に合ったものを選びましょう。
給与計算ソフトの提供形態

給与計算ソフトの提供形態は、基本的に以下の2種類に分類できます。
- クラウド型
- インストール型
それぞれの形態の特徴について詳しく解説します。
クラウド型
クラウド型の給与計算ソフトは、インターネット環境さえあれば場所や端末を問わず操作できる柔軟さが特徴です。専用ソフトのインストールが不要で、ブラウザやスマホからログインすれば即時に作業を開始できるため、リモートワークや外出先からの対応にも向いています。
常に最新版に自動アップデートされるため、税率改定や法令変更に伴う更新作業も不要となり、管理負担を軽減できます。また、月額課金での利用が一般的で、初期費用を抑えて導入できる点もメリットです。
一方で、利用時にはインターネットへの接続が不可欠なので、通信環境が不安定だと快適に利用できません。また、利用している回線のセキュリティが脆弱だと、情報流出のリスクがある点には注意が必要です。
インストール型
インストール型の給与計算ソフトは、社内のパソコンやサーバーに直接ソフトを導入して利用する方式です。ローカル環境で稼働するため、オフラインでも安定して運用できる点が特徴です。
インターネットに接続せずに利用できるため、クラウド型よりも強固なセキュリティ環境を構築できます。
また、買い切り型が主流で、月額課金が不要なケースが多いです。そのため、初期にまとまった費用が発生するものの、長期的なコストを抑えられる傾向にあります。カスタマイズ性が高く、自社独自の業務フローや帳票出力に柔軟に対応できる点もメリットです。
一方で、アップデートや保守はユーザー側の対応が求められるほか、Windows専用で他のOSに非対応な製品もあるため、導入前の確認が重要です。
給与計算ソフトの3種類のタイプ

給与計算ソフトには以下の3つのタイプが存在します。
それぞれ強みが異なるので、自社に合ったものを導入するのが重要です。それぞれ詳しく解説します。
人事給与型
人事給与型は、給与の計算や管理だけでなく、人事業務全般に対応しているタイプの給与計算ソフトです。単なる給与計算にとどまらず、勤怠管理機能や労務管理機能などを搭載しており、それぞれのデータをシームレスに活用できます。
特に従業員の異動・評価・採用といった人事管理情報と、毎月の給与や賞与に関するデータを連携できるのは利点が多く、業務の重複や入力・転記ミスといったヒューマンエラーを防止することが可能です。
中長期的な人事戦略を立案する際も、勤怠データや従業員の給与データなどを踏まえて総合的に判断が可能になるため、特に評価制度の導入や組織改編が頻繁に行われる企業に適しています。
ERP型
ERP型は、経営資源を統合管理できるERPシステムに組み込まれているタイプの給与計算ソフトです。ERPシステムでは、経営に関わる社内のデータを一元管理できます。管理できる項目には人材や財務会計なども含まれており、従業員の給与もまとめて管理することが可能です。
ERP型を導入すれば、給与や勤怠だけでなく、仕訳データや予算管理にもスムーズに反映できるため、部門間連携を促進し、業務の一貫性を高めやすくなります。
また、一つのプラットフォームで複数の業務が連携する構造により、人的ミスや情報の重複入力を減らせる点もメリットです。
ただし、全社導入を前提とした設計のため、導入に伴ってデータの管理体制や業務フローの見直しが必要になることが多く、運用開始まで時間がかかります。
基本的には多拠点展開している企業や複雑な経理処理が求められる大手企業におすすめのタイプです。
給与計算特化型
給与計算特化型は、給与計算に必要な最低限の機能だけを搭載しているタイプの給与計算ソフトです。給与明細の作成や年末調整、保険料や残業代・手当の算出といった業務に必要な機能のみに絞られているため、他のタイプと比較すると、対応範囲は狭くなっています。
一方、人事機能や勤怠管理機能などがない分、低コストでの導入が可能です。また、操作が直感的で、ITに不慣れな方でも使いやすい傾向があります。
クラウド型が主流であるため、インストール不要で利用開始までの手間が少ないのも特徴で、簡易操作で本格的な給与処理を行いたい小規模企業や個人事業主におすすめです。
事業規模ごとの給与計算ソフトの選び方

最適な給与計算ソフトは、導入する事業者の事業規模によっても変わってきます。当記事では以下の事業規模に分類した上で、それぞれの事業規模における給与計算ソフトの選び方を解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
小規模企業や個人事業主の場合
小規模企業や個人事業主が給与計算ソフトを選ぶ際は、低コストかつ必要最低限の機能を備えたシンプルな製品が適しています。
基本的な給与明細作成や源泉徴収、社会保険料の算出といった業務のみを効率化できる給与計算特化型の製品を導入すれば、導入時の学習コストも抑えられ、日々の運用もスムーズに行うことが可能です。
給与計算特化型の製品はクラウド型のものが多いため、アップデートや法令対応が自動で行われる点でも、業務に余裕がない小規模企業や個人事業主に適しています。
普段エクセルで行っている給与計算業務を効率化する目的で給与計算ソフトを選ぶのであれば、シンプルかつ低コストで導入できるものを選びましょう。
中小企業の場合
中小企業が給与計算ソフトを導入する際は、限られた人員でも業務効率化を図れる製品を選定することが重要です。
勤怠管理機能や労務管理機能も搭載された人事給与型の製品であれば、入力の手間や転記ミスを減らし、幅広い業務を効率化できます。
また、従業員数の増加や制度変更に応じて柔軟に機能を拡張できるかも選定時のポイントです。クラウド型の製品であれば、最低限の機能で運用を始め、必要に応じて追加機能を段階的に導入できるものも多いため、初期コストを抑えつつ長期的な活用を見込めます。
導入段階で必要な機能を網羅しつつ、スケーラビリティも期待できる製品を選ぶようにしましょう。
大企業の場合
大企業が給与計算ソフトを導入する場合、複雑な組織構造や多数の従業員を一括で管理できる機能が不可欠になります。
特に、複数の拠点や部門を横断した運用を想定するなら、拠点対応や人事部門とのデータ連携機能がある製品を選ぶことが重要です。ERP連携が可能な給与計算ソフトであれば、各部門の情報を統合的に扱えるため、管理業務全体の最適化が実現できます。
また、多人数の処理に伴う個人情報の取り扱いには高水準のセキュリティ対策も求められるため、アクセス制限や監査ログなどの機能が搭載されているか確認しておくことも重要です。
給与計算ソフトで使える7つの機能

給与計算ソフトでは、主に以下のような機能が利用できます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
給与の自動計算・一括振込機能
給与計算ソフトの肝となるのが、給与の自動計算機能です。勤怠情報や基本給・手当などのデータをもとに、給与額を自動計算できる他、残業代や控除、所得税などの細かな計算も自動で処理されるため、手作業での入力ミスや確認作業を大幅に削減できます。
また、一括振込機能があれば、作成した振込データを銀行と連携させ、複数従業員に一括で給与の振り込みを行うことが可能です。
給与処理のたびに発生する集計や個別振込といった煩雑な業務を効率化することで、担当者の負担を軽減しつつ、業務の正確性を高められます。
給与明細書の閲覧・発行機能
給与明細書の発行や閲覧も、給与計算ソフトの基本的な機能です。給与明細をPDFなどで自動発行し、Web上で従業員が確認できます。
従来の紙での配布に伴う印刷・封入・手渡しといった手間が不要になるため、明細発行に関する業務の負担を軽減できる上、ペーパーレス化によるコスト削減も可能です。
また、従業員自身がスマートフォンなどからいつでも明細を確認できるようになるため、利便性の向上にもつながります。
紛失などの心配もなく、セキュリティ対策が万全な環境で給与明細書を保存・閲覧できるため、個人情報保護の面でも重要な機能です。
勤怠管理機能
給与計算ソフトによっては、勤怠管理機能を備えているものもあります。勤怠管理機能がある給与計算ソフトでは、出退勤時の打刻や残業時間、有給休暇の取得状況などを記録・集計できる他、集計したデータをもとに給与を自動計算することが可能です。
結果として、給与計算に必要な工数を削減できる他、集計ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎやすくなります。
クラウド型の製品の場合、スマートフォンやPCから簡単に出退勤を打刻できることも多く、従業員の利便性を向上しつつ、リモートワークなどに対応することも可能です。
法定料率改定への自動対応機能
給与計算ソフトには法改正に合わせた自動アップデート機能を備えているものも多いです。
保険料率などの給与計算に関する数値は頻繁に変化することが多く、計算ミスの原因になることも少なくありません。
法定料率改定への自動対応機能が備わっていれば、社会保険料や所得税などが最新料率に即座にアップデートされ、制度変更のたびに設定を見直す手間を削減できます。
法定三帳簿の作成機能
給与計算ソフトでは、法定三帳簿の作成も自動で行えます。法定三帳簿とは、法令で作成と保存が義務付けられている以下の帳簿のことです。
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働者名簿
従業員情報や勤怠データと連動して法定三帳簿が作成されるため、常に最新の情報に基づいた状態にしておけます。帳票の形式が法令に準拠しているかも自動でチェックされるため、監査や労基署対応の備えとしても有効です。
また、源泉徴収票や勤労統計調査票をはじめとした管理帳票の自動作成に対応しているものも多く、導入すれば書類作成にかかる工数を削減できます。
年末調整機能
給与計算ソフトは年末調整にも対応可能です。各従業員の毎月の給与データや扶養控除申告書、保険料控除などの情報をもとに年末調整に関する計算を自動で行えます。
また、計算後の電子申告に必要なデータを自動で生成してくれるため、申告の手間も削減することが可能です。
特に従業員数が多い企業や年末に決算が重なるような企業の場合、年末調整に関する業務は大きな負担となるため、給与計算ソフトを導入するメリットは大きいといえるでしょう。
マイナンバー管理機能
マイナンバーの管理機能も、給与計算ソフトに搭載されていることが多い機能です。マイナンバー管理機能を搭載している給与計算ソフトであれば、マイナンバーの取得や利用履歴の記録、通知番号の管理まで自動で行えます。
マイナンバーは従業員の個人情報にあたり、情報漏洩や不正利用のリスクが常に伴います。給与計算ソフトでは、暗号化やアクセス制限といった安全管理措置でマイナンバーを安全に管理することが可能です。
給与計算ソフトを導入するメリット

給与計算ソフトを利用するメリットは以下の通りです。
給与計算に関する業務を効率化できるだけでなく、個人情報の保護も可能なのがポイントです。それぞれ詳しく解説します。
業務効率を改善できる
給与計算ソフトを導入することで、給与計算に関する業務効率を改善することが可能です。一般的に、給与計算業務では以下のような作業を行います。
- 給与処理
- 明細書発行
- 社会保険料処理
- 賞与処理
- 年末調整
- 法改正への対応
一口に給与計算業務といっても、実際には上記のように複数の作業を行わなければいけません。給与計算ソフトを導入すれば、手作業で行う上記のようなタスクを自動化できるため、担当者の工数を大幅に削減できます。
また、業務の標準化によって属人化も解消できるため、担当者の離職時にも円滑な引継ぎが可能です。
給与計算業務にかかるコストを削減できる
給与計算ソフトを導入することで、給与計算業務にかかる金銭的なコストもカットできます。従来の給与計算業務では、紙の明細書や台帳などを用いるため、印刷費や郵送費といったコストが発生します。
また、書類の保管なども必要になるため、保管スペースを確保するコストも必要です。加えて、毎月の処理を外部に委託している場合は、外注費が継続的に発生し、ランニングコストが発生します。
給与計算ソフトを導入すれば、関連書類をすべて電子データで管理できるため、ペーパーレス化によるコスト削減が可能です。加えて、業務効率化によって内製化がしやすくなるため、外注費の削減にもつながります。
結果的に給与計算業務にかかる金銭的なコストを削減することが可能です。
従業員の個人情報を保護しやすくなる
給与計算ソフトは社内のセキュリティ強化にも役立ちます。給与計算業務では従業員の個人情報管理が必要になるため、社内の業務の中でも特にセキュリティ対策が必要です。特に近年はマイナンバーの管理も必要なため、今まで以上にセキュリティが重要になります。
給与計算ソフトを導入すれば、従業員の情報を1つのシステム上で管理できるため、セキュリティ対策がしやすくなります。製品によってはアクセス権限や暗号化機能など、さまざまな機能を搭載しているので、強固なセキュリティ環境を構築することが可能です。
正確かつ迅速な給与支払いができる
給与の支払いをミスなく迅速に行えるのも、給与計算ソフトを導入するメリットです。勤怠データや各種手当・控除の情報をもとに給与を自動計算できるため、手作業による入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを最小限に抑えられます。
また、給与の支払い日は休日などの兼ね合いで変わることも多いため、日付設定を間違えてしまうことも少なくありません。給与計算ソフトのスケジュール管理機能や自動振込機能を活用すれば、支給遅延も回避しやすくなり、給与支給日を厳守できます。
加えて、支払い後の確認もシステム上で簡単に行えるため、給与の支払いでトラブルがあった場合でも問題点をすぐに発見することが可能です。
従業員が簡単に給与明細を確認できる
給与計算ソフトを導入することで、従業員が自身の給与明細をスマホやPCから簡単に確認できるようになります。
Web上で給与明細を管理することで、発行や配布の手間がなくなり、担当者の負担を軽減できます。また、従業員からの明細内容に関する問い合わせも削減できるため、対応工数の削減も可能です。
従業員側としても必要な時に時間や場所を問わず明細を確認できるため、利便性が向上します。紙の明細と異なり紛失のリスクもなく、セキュリティが確保された環境で明細を管理できるのもメリットです。
蓄積されたデータを経営判断や人事に活用できる
給与計算ソフトに蓄積される勤怠や人件費に関するデータは、単なる記録にとどまらず、経営や人事戦略の意思決定を支える有効な情報源になります。
例えば、部署別の人件費を定量的に把握すれば、業務量とリソースのバランスを見直すきっかけになります。また、勤怠の傾向から残業の多い部門を特定して、業務配分や人材配置の最適化にもつなげることも可能です。
さらに、月次や年次でのKPIとして給与計算ソフトのデータを定点的にモニタリングすれば、経営課題の早期発見にも寄与します。
以上のように、給与や勤怠情報をもとにしたデータ分析は、勘や経験に頼らない経営判断や人事を行うための客観性のある判断材料として活用することが可能です。
法改正に素早く対応できる
給与計算ソフトを導入することで、法改正への対応も効率化することが可能です。給与の計算に利用する税率などの数値は、税制や社会保険料に関する法令の改正によって頻繁に変化します。
そのため、給与計算業務を行う際には関連する法令の最新版を確認し、逐一対応していかなければいけません。
法改正に関する通知機能や自動アップデート機能を搭載している給与計算ソフトを導入すれば、法改正があっても自動で税率や社会保険料率が変更されるので、対応漏れでミスにつながる心配がありません。改正された法令を逐一確認する必要もなくなるため、業務に集中できます。
給与計算ソフトを導入するデメリット

給与計算ソフトを導入する際のデメリットは以下の通りです。
特にカスタマイズできる範囲に限度がある点は留意しておく必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
導入や運用にコストがかかる
給与計算ソフトの導入や運用には金銭的なコストが発生します。初期費用はもちろん、運用時にも月額利用料がかかることが多いので、ランニングコストが発生することを把握しておかなければいけません。
特にカスタマイズ性の高い製品やサポート範囲が広いサービスを選ぶ場合、月々の費用が想定以上に膨らむこともあるため注意が必要です。
給与計算ソフトを導入する際は費用の内訳を事前に確認し、あらかじめ設定した予算の範囲内で特に費用対効果の高い製品を選択するようにしましょう。
導入後の初期設定やデータ移行に時間がかかる
導入後の初期設定やデータ移行に時間がかかることも、給与計算ソフトを導入する際のデメリットです。給与計算ソフトの導入時には、今までの給与計算のルールをシステムに適用させる必要があるため、運用開始まで時間がかかります。
具体的には、社員情報のマスタ登録や勤務データ、控除項目などの設定に加え、過去の履歴データの取り込みや整合性の確認も必要です。
特に設定工数が多いソフトでは、業務開始までに想定以上の期間が必要になることもあるため、余裕を持ったスケジュールの設定が重要になります。
また、サポートが充実していないサービスを導入した場合は、初期設定でトラブルが発生した際に解決まで時間がかかることも多いです。導入時の工数を抑えたいのであれば、サポート体制が万全な給与計算ソフトを検討しましょう。
担当者に操作方法の研修などが必要になる
給与計算ソフトを導入する際は、担当者に操作方法の研修などが必要になることも把握しておきましょう。
給与計算ソフトに限らず、業務効率化のためのソフトやシステムを導入した際には担当者が操作に慣れるまでの時間を確保することになります。
そのため、給与計算ソフトの導入時には、操作に慣れるまでの期間をスケジュールに盛り込むことが重要です。また、マニュアルの作成をはじめとした社内教育ができる環境の構築や、運用ルールの構築も、中長期的な運用を行っていく上で必要になります。
無料トライアルがある製品を選べば、導入前に操作感を確認できるため、ある程度のスケジュール感を把握することが可能です。
セキュリティリスクが発生するおそれがある
給与計算ソフトはクラウド型が主流になりつつあり、インターネットへの接続が不可欠なものが多いです。結果として、セキュリティリスクが発生するおそれがあります。
具体的には、外部からの不正アクセスやマルウェアによる情報漏洩などが発生するおそれがあり、対策を講じていなければ重大な被害につながりかねません。
特に暗号化に未対応な製品や、セキュリティホールが存在する製品を導入した場合は、従業員の個人情報や給与データが漏れる危険性が高まります。
給与計算ソフトを導入する際には、従業員の個人情報を扱うことを考慮し、特にセキュリティ性能にこだわることをおすすめします。
カスタマイズできる範囲には限度がある
給与計算ソフトは多くの業務に対応していますが、すべての企業に完全対応できるわけではありません。特に、独自フローや特殊な勤務体系を採用している場合、カスタマイズ制限により理想的な運用が難しくなる可能性があります。
また、機能の柔軟性に乏しい製品では、入力項目の変更や処理ロジックの調整ができず、結果的に別のツールや手作業との併用が必要になることも少なくありません。
そのため、給与計算ソフトを選ぶ際は、導入前に必要な機能や運用条件を整理し、独自要件への対応可否を事前に確認することが重要です。
定期的なアップデートが必要な場合がある
インストール型の給与計算ソフトを運用する場合、基本的に自動アップデート機能が搭載されていないため、定期的なアップデートが必要です。
法改正やOSの仕様変更などに追従するためにソフトの更新を行う際には、一時的にソフトの利用を停止しなければならないため、業務が遅延する可能性があります。
アップデートの対応に遅れると、社会保険や税制の変更に適切に対応できず、法令違反につながりかねません。自動アップデート機能がない製品を導入する場合は、更新漏れを予防するための施策を考えましょう。
給与計算ソフトの価格・費用相場
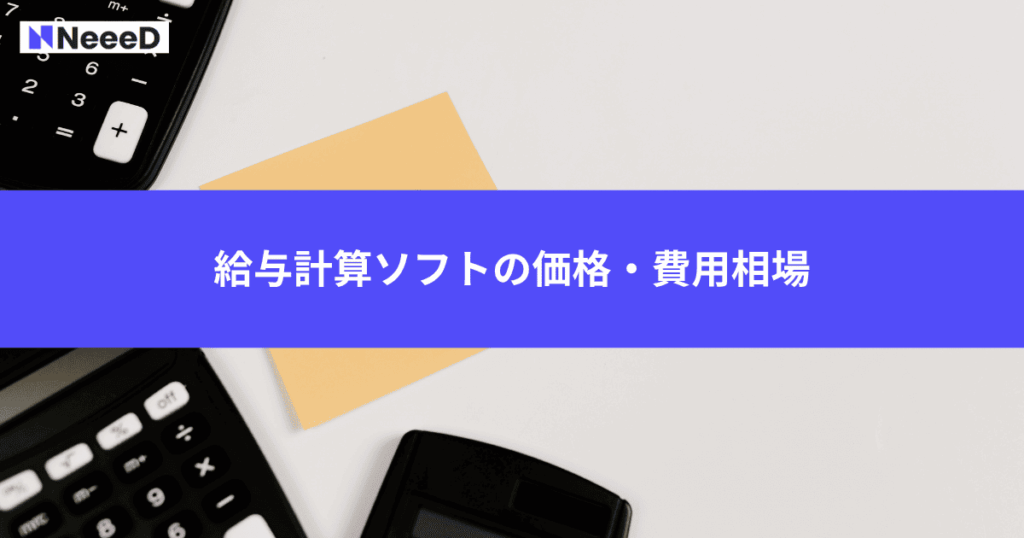
給与計算ソフトの価格・費用相場は以下の通りです。
| 提供形態 | 料金相場 |
|---|---|
| クラウド型 | 月額300円〜600円程度(1ユーザーあたり) |
| インストール型 | 初期費用:数十万円~数百万円程度 ※別途保守・管理費用が発生する場合あり |
基本的には、クラウド型は従量課金制が採用されていることが多く、インストール型は買い切りで利用できることが多いです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
クラウド型の料金相場
クラウド型の給与計算ソフトは、初期費用が無料~5万円程度、月額利用料が1,000円〜15,000円程度のものが多いです。
従量課金制を採用している製品の場合は、基本料金に加えて1ユーザーあたり月額500円程度が加算される傾向にあります。
少数ながら無料プランを提供している製品も存在し、機能は少ないものの、コストを抑えてスモールスタートしたい企業にとっては有力な選択肢となるでしょう。
インストール型の料金相場
インストール型の給与計算ソフトは、一括購入による買い切り型が主流で、数万円から数十万円まで価格帯に幅があります。
初期費用は高めですが、基本的には月額費用が不要なため、中小企業や大企業が長期的に利用するのにおすすめです。
一方で、法令改正や制度変更に対応するには更新作業が必要になることがあり、保守費用が別途発生することも多いので注意しましょう。
【まとめ】自社のニーズに合った給与計算ソフトを選ぼう
給与計算ソフトのおすすめや選び方、導入するメリット・デメリットなどについて解説してきました。
給与計算ソフトを導入すれば、複雑な給与計算を自動化できるため、ヒューマンエラーの低減と業務効率化が期待できます。ただし、導入・運用にコストがかかることや導入時の設定に時間がかかる点には注意が必要です。
給与計算ソフトを選ぶ際は、まず自社の規模に合っているか確認しましょう。そのうえで機能やサポート体制の充実度をもとに吟味していけば、自社に合ったサービスを選びやすくなります。
当記事を参考に、ぜひ自社に合った給与計算ソフトを探してみてください。

の口コミや評判は?選べる料金プランや導入メリットも解説-300x158.jpg)