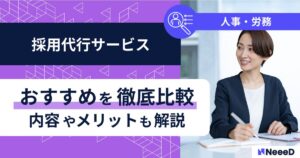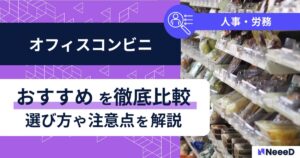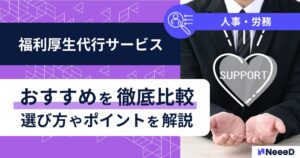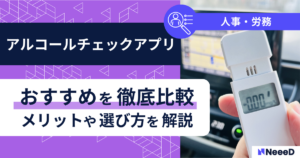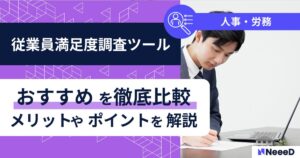【2025年6月最新】人事評価システムのおすすめ4選を比較!無料トライアルできる製品や選び方も解説
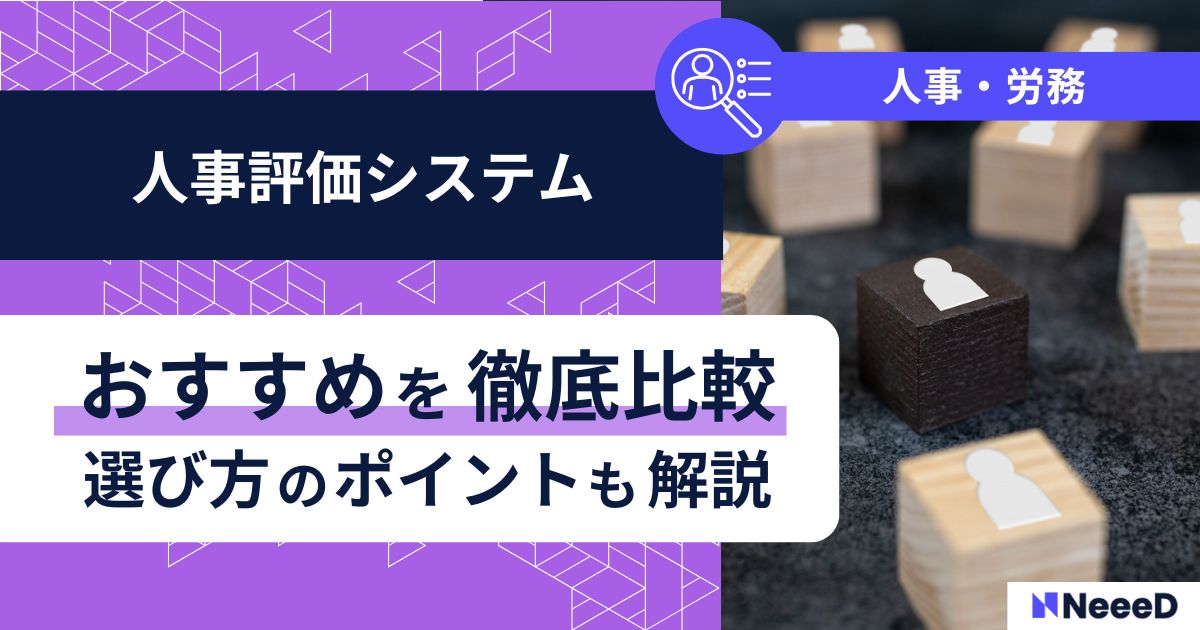
生産性の高い強固な組織を形成するために重要な人事評価ですが、現場の各従業員と個別にやり取りが必要な都合上、どうしても工数が多くなりがちです。そこで人事評価に関する業務を効率化できる人事評価システムが注目されています。
しかし、「どの人事評価システムを選べばいいか分からない」という人も多いでしょう。
当記事ではおすすめの人事評価システムを紹介します。人事評価システムの比較ポイントや機能、導入するメリット・デメリットについても解説しているので、当記事を読めば自社に合った人事評価システムを選べるようになります。人事評価システムの導入を検討している方はぜひご覧ください。
おすすめの人事評価システム4選

人事評価システムのおすすめを4つ紹介します。各製品の特徴は以下の通りです。
| おすすめの人事評価システム | 特徴 |
|---|---|
| カオナビ | 優れたUIと豊富な機能が特徴 |
| HRMOSタレントマネジメント | 人事評価業務の効率化から人材管理、マネジメントまで対応 |
| 人事評価型ナビゲーター | 低コストで十分な機能を搭載 |
| JOB Scope | 日本企業の組織課題解決に特化して設計 |
それぞれ異なる強みを持つので、自社に合ったものを選択しましょう。
カオナビ(株式会社カオナビ)

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | 人材データベース 組織ツリー作成 評価ワークフロー スキル管理 AI分析など |
| タイプ | タレントマネジメント型 |
| 導入実績 | 日精株式会社 富士フィルムメディカル株式会社 群馬県庁など |
| 会社所在地 | 〒150-6138 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F |
カオナビは人事評価からタレントマネジメントまで対応している人事評価システムです。人事評価業務の効率化だけでなく、人材情報の管理や育成計画の策定、離職分析なども行えます。人事評価業務については評価シートの作成や従業員への通知を半自動化できるため、分析やフィードバックにリソースを割くことが可能です。
また、タレントマネジメント機能としては人材配置シミュレーションやスキル管理機能だけでなく、離職分析なども行えるため、人材流出の予防も行えます。UIは直感的に操作できるものになっており、担当者が操作に慣れるまで時間がかかることもありません。人事関連業務を総合的に効率化したい企業におすすめの人事評価システムです。
HRMOSタレントマネジメント(株式会社ビズリーチ)

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | 人材データベース 情報検索 組織シミュレーション 1on1支援機能など |
| タイプ | タレントマネジメント型 |
| 導入実績 | auコマース&ライフ株式会社 トラボックス株式会社 株式会社ユニークワン 株式会社デジタル・ナレッジなど |
| 会社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
HRMOSタレントマネジメントは株式会社ビズリーチが提供する人事評価システムです。サービス名の通りタレントマネジメント型の人事評価システムとなっており、人事評価業務の効率化から人材管理、マネジメントまで活用できます。
特に人事評価では1on1ミーティングなどの面談を評価に活用できるのが特徴で、実施状況の可視化や内容の記録だけでなく、目標設定やフィードバックに関する機能が搭載されています。
対応している評価制度も幅広く、OKRやMBOだけでなく、コンピテンシー評価や360度評価にも対応しているので、導入できる企業は多いです。eラーニングの管理機能など、人材育成に関する機能も豊富で、自社の人事業務に合わせて多様な活用が可能な人事評価システムとなっています。
人事評価型ナビゲーター(株式会社日本経営)

| 料金プラン | 初期費用:110,000円~ 月額料金:5,500円~ |
|---|---|
| 機能 | 面談記録 報告書自動生成 人事評価集計 評価制度の無料診断サポートなど |
| タイプ | 人事評価特化型 |
| 導入実績 | ピルボックスジャパン株式会社 アストマックス株式会社 株式会社CADネットワークサービスなど |
| 会社所在地 | 〒561-8510 大阪府豊中市寺内2-13-3 日本経営ビル |
人事評価型ナビゲーターは低コストで導入が可能な人事評価特化型人事評価システムです。特に月額費用については5,500円からと割安で、資金繰りに不安のある小規模事業者でも導入しやすくなっています。
機能面はシンプルではあるものの、人事評価業務に必要な機能は余すことなく備えているため、物足りなさは感じません。また、面談の記録機能や報告書の自動生成機能など、痒い所に手が届く機能も搭載されています。
運用サポートも無料で提供しているため、運用時にトラブルが発生しても安心です。さらに、評価制度の無料診断も行っており、現状の人事評価制度の改善案などを提示してくれます。創業して間がなく評価制度が確立していない企業にもおすすめの人事評価システムです。
JOB Scope(デフィデ株式会社)

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | 採用管理 適職性診断 1on1面談 各種サーベイ 評価結果と賃金テーブルとの連動など |
| タイプ | タレントマネジメント型 |
| 導入実績 | 株式会社山川自動車 株式会社GLBBジャパン アウンコンサルティング株式会社 など |
| 会社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1-4F 新東京ビル Shin Tokyo 4TH |
JOB Scopeは、日本企業の組織課題解決に特化して設計されたクラウドサービスです。従来型の能力ベースの人事管理から、職務ベース(日本企業に最適化したジョブ型)の管理に移行させることで、社員が組織目標に基づいた成果を最大化できる環境を提供します。
機能面では、基本的な人事評価に関する機能や1on1ミーティングの内容を記録できる機能の他、採用管理や適職性診断など、採用活動に利用出来る機能も豊富に搭載しているのが特徴です。
他にも基本給与の自動算出機能など、人事評価の枠を超えた機能が搭載されており、幅広い業務を効率化できます。これから職務ベースの人事管理に移行したい企業に特におすすめのシステムです。
人事評価システムを選ぶ際の11の比較ポイント
人事評価システムを比較する際には、以下のようなポイントに注目しましょう。
特に自社の既存システムと連携できるかはサービスを比較する際に重要なポイントになります。また、自社の人事評価制度との相性も確認しておくことが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の人事評価制度と相性が良いか
まずは自社の人事評価制度と相性が良いか確認しましょう。企業が採用する一般的な人事評価制度には以下のようなものがあります。
- 能力評価制度
- 成果評価制度
- 情意評価制度
- コンピテンシー評価制度
- バリュー評価制度
- 360度評価制度
- 目標管理制度(MBO)
- OKR
上記の評価制度は、それぞれ求められる運用設計や評価フローが異なります。そのため、人事評価システムを検討する際は、自社の制度に合わせて評価基準のカスタマイズやテンプレート変更を柔軟に行えるかを確認することが重要です。
導入後に評価制度との不一致が発覚すると、評価の公平性が損なわれるおそれがあり、制度自体の信頼性にも影響しかねません。自社の評価手法に沿った設計が可能なシステムを選ぶことで、制度の運用定着が進みやすくなり、成果の最大化につながります。
事業規模や組織体制に合っているか
続いて、検討している人事評価システムに自社の事業規模や組織体制に対応できる柔軟性があるかを確認しましょう。特に事業規模に関しては製品を検討する上で重要です。
事業規模が大きい企業では、組織体制が複雑になりがちなため、評価プロセスの分岐や部門ごとに異なる評価基準に対応できるようなカスタマイズ性が求められます。
一方、従業員数が少ない中小企業の場合は、必要な機能が少なく済むことが多いです。不要な機能が多いと、むしろ運用が複雑化して業務効率が落ちる場合があります。
人事評価システムを選ぶ際は、事業規模や組織体制を再確認し、対応可能なものを選びましょう。
自社と同じ業界での導入実績は豊富か
人事評価システムを導入する際は、自社と同じ業界での導入実績が豊富かどうかを確認することも重要です。業界特有の人事評価基準がある場合、対応できるシステムでなければ運用時に手間や不具合が生じやすくなります。
事前に業界別の導入事例や他社の成功事例を確認すれば、具体的なベンチマークが得られ、運用イメージを明確化することが可能です。
特に業界特化型のテンプレートを搭載している製品や、機能の柔軟性が高い製品であれば、スムーズに導入できます。
人事評価システムを選ぶ際にはサービスの導入実績を確認し、自社に近い企業への導入事例が多いサービスを選びましょう。
既存システムの流用余地や連携性はあるか
既存システムの流用余地や連携性はあるかも、人事評価システムを選ぶ際のポイントです。人事評価システムの中には他のシステムと連携することで、対応範囲を拡張できるものがあります。
例えば、勤怠管理システムや労務管理システム、給与計算システムと連携できれば、人事業務全般を効率化することが可能です。
また、人事評価システムの導入目的が人事評価業務の効率化のみの場合、既存システムを流用できるかを確認しましょう。
特にシステムの導入・運用に予算を割けない企業の場合、機能は少なくても低コストなサービスを導入し、足りない部分は既存システムを使いまわすことで、低予算での業務効率化を狙えます。
人事評価システムを検討する際は、APIなどで既存システムと円滑に連携できるか確認しましょう。
操作性は高いか
操作性の高さも、人事評価システムを比較する際の重要なポイントです。人事評価システムの操作性が良ければ、導入後に担当者がシステムに慣れるまでの時間を短縮できます。操作性の面で特に確認しておきたい内容は以下の通りです。
- 評価シートの作成しやすさ
- データの検索項目
- 管理画面のUIの良さ
まず、評価シートが作成しやすいサービスを選択すれば、工数がかかりがちな評価シートの作成業務を効率化できます。また、データの検索項目も確認しましょう。人事評価システムでは膨大なデータを管理することになるので、データの検索機能の性能も重要です。
さらに、管理画面のUIが優れているサービスを導入すれば、必要な情報を短時間で把握できます。以上のような点に注目して人事評価システムを選べば、より人事評価を効率化することが可能です。
必要な機能は網羅されているか
人事評価システムを選ぶ際は、必要な機能は網羅されているかも確認しましょう。自社にとって必要な機能が搭載されていなければ、導入しても効果的な業務効率化は実現できません。
例えば定期的な1on1ミーティングの内容を評価対象としているのであれば、面談の内容を記録できる機能を搭載した人事評価システムが候補になります。
一方で、定量的な評価が行えるような制度を採用している場合は、データの集計や分析に特化したサービスを導入した方が、業務を効率化しやすいです。
他にも社内全体での相対評価を行う場合は、集計したデータを基に相対値で可視化してくれるような機能があると、効率よく業務を行えます。まずは検討している人事評価システムの機能を比較し、自社に合ったものに選択肢を絞りましょう。
セキュリティ性能は高いか
セキュリティ性能の高さも、人事評価システムを選ぶ際のポイントです。人事評価システムでは従業員の個人情報を扱うことになります。特に人事における情報は社内の人材配置にも関わるので、外部だけでなく社内での流出にも気を配らなければいけません。
例えば従業員ごとにアクセス権限を付与する機能や、データの暗号化といった機能が搭載されていれば、従業員も必要以上の情報を確認できなくなります。また、自治体などの行政機関の場合は、LGWANやISMAPといった、行政向けのセキュリティ要件を満たしているかを確認することが重要です。
人事評価に関する情報流出は従業員の信頼を失いかねません。セキュリティ面で優れた人事評価システムの導入は内部統制の強化にもつながるので、妥協せずに選定しましょう。
サポート体制は万全か
人事評価システムを選ぶ際には、サポート体制も確認しましょう。人事評価システムの導入時には社員情報の整理や人事評価制度の見直しなどが必要になることもあるため、工数がかかります。加えて、情報の紛失や流出をはじめとしたトラブルが発生しやすいです。
また、運用時にトラブルが発生してシステムが使えなくなると、人事評価業務が大幅に遅れ、人材配置などに影響が出るおそれがあります。
そのため、人事評価システムの検討時にはカスタマーサポートの対応時間や、サポートの内容を吟味することが重要です。
電話やチャット、メールなど、多様な手段で時間を問わず問い合わせできる製品や、FAQやヘルプデスクが充実している製品を選べば、万が一トラブルが発生しても迅速に対応できます。
導入後の機能拡張やカスタマイズは可能か
導入後の機能拡張やカスタマイズができるかも、人事評価システムを選ぶ際のポイントです。人事評価制度は、組織の成長や環境の変化に応じて見直しが必要になるため、導入するシステムにも柔軟な対応力が求められます。
将来的に目標管理や360度評価などの新たな評価手法を取り入れる場合に備えて、機能追加のしやすさやカスタマイズ性を確認することが重要です。
たとえば、モジュール単位での機能追加やオプション機能によるバージョンアップに対応していれば、業務要件の変化にもスムーズに適応できます。
導入後に長期にわたって利用するためにも、スケーラビリティの高さも吟味して人事評価システムを選びましょう。
コストは適正か
コスト面も人事評価システムを選ぶ際の重要なポイントです。人事評価システムの導入時には基本的に初期費用が発生します。また、運用時にも月額料金が発生することがほとんどです。特に小規模の事業者の場合、人事評価システムのコストが自社のキャッシュフローに悪影響を与えかねません。
一方で、低コストなサービスは機能が少なく、想定していた運用ができない可能性があります。人事評価システムを選ぶ際には、自社に必要な機能を洗い出した上で予算を見積もり、費用対効果の高いものを選定しましょう。
無料トライアルは利用できるか
人事評価システムを選ぶ際は、無料トライアルは利用できるかも確認しましょう。人事評価システムの中には無料トライアルを提供しているものもあります。また、クラウド型の製品では、機能が制限された無料プランを利用できることも多いです。
無料トライアルや無料プランがあれば、UIや自社の評価制度との相性を実際に検証できるため、導入後のギャップを最小限にできます。
特に確認しておきたいのはサービスの操作性です。実際に業務を行う担当者が使いやすいサービスを選べば、導入後の設定や運用に慣れるまでにかかる工数の削減が可能です。
検討している候補の中に無料トライアルや無料プランがある場合は、本格導入前に利用して、担当者が使いやすいものを選びましょう。
人事評価システムとは
人事評価システムとは、社内の人事評価に関する業務を効率化できるシステムのことです。人事評価シートの作成や管理の他、各従業員の目標設定や自他の評価、上司のフィードバックなどをシステム上で一元管理できます。
また、人事評価の定義や評価基準をシステム上で統一し、機械的に評価を行うことができるため、担当者の主観を排除でき、客観的な評価を下すことが可能です。
単なる人事評価業務の枠を超え、人材配置や人材育成計画などに活用できるものも多く、経営資源としての人材の有効活用につながります。
そのため、近年ではデータ管理体制の強化や生産性向上の目的で導入する企業が増えています。
人事評価システムのタイプ

人事評価システムは以下の4種類に分類できます。
タイプによって搭載している機能の傾向が異なるので、自社に合ったものを選択するのが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
人事評価特化型
人事評価特化型の人事評価システムは、文字通り人事評価業務の効率化に特化したタイプです。基本的には評価シートの作成から配布、集計やフィードバックといった機能のみを搭載しています。
搭載している機能が少ないので、操作がシンプルで使いやすいものが多いです。また、導入時に影響を与える範囲が狭いため、導入がしやすいのもメリットといえるでしょう。
加えて、人事評価特化型は低コストで導入・運用できるものが多いです。そのため、小規模事業者が評価制度をシステム化する際にも適しています。すでに評価制度や評価基準が確立されている場合でも導入しやすく、柔軟性の高いタイプです。
人事情報一元管理型
人材情報管理型の人事評価システムは、人事評価業務の効率化だけでなく、人材情報の一元管理が行えるタイプです。従業員の基本情報や異動履歴、過去の評価などを管理でき、必要に応じて確認できます。扱うデータ量が多いため、データの検索機能が充実しているサービスが多いです。
人材が多く複雑な組織構造を持つ中小企業や大企業におすすめで、必要な人材情報をすぐに確認できます。また、自社の人材情報から必要な人材を効率良く洗い出せるため、採用活動にも活用可能です。
将来的な拡張性に優れているものも多く、戦略的な人材活用を行いたい企業におすすめです。
タレントマネジメント型
タレントマネジメント型の人事評価システムでは、人事情報一元管理型の機能に加え、集計したデータをもとにした人材の分析や将来的な人材活用計画の策定が可能です。
従業員のスキルや志向性を把握することで、各従業員にとって最適な人材配置を分析できる他、今後のキャリアパスの設計などが行えます。
また、ストレスチェック機能など、従業員のモチベーションチェックを綿密に行える機能を搭載しているものもあり、従業員の離職防止や、モチベーション向上による生産性向上につなげることも可能です。
他のタイプと比較するとコストが割高なことが多いため、中長期的な視点で人材資源を活用したい大企業で採用されることが多いタイプです。
1on1ミーティング対応型
1on1ミーティング対応型の人事評価システムは、文字通り1on1ミーティングを効果的に実施できるような機能を搭載しています。
具体的には定期面談の記録機能やフィードバック履歴の管理機能などが利用でき、頻繁に行うことになる1on1ミーティングの内容を忘れることなく、次回以降の生産的な会話につなげることが可能です。
また、会話内容やフィードバックの履歴から客観的なミーティングの分析も可能になり、より効果的なミーティング内容にアップデートできます。
人事情報一元管理型やタレントマネジメント型の製品に機能が内包されていることも多く、他の機能も加味して導入を検討したいタイプといえるでしょう。
人事評価システムの主な8つの機能

人事評価システムの主な機能は以下の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
評価シート作成機能
評価シート作成機能では、人事評価に必要な評価シートの作成を効率化できます。多くのシステムではテンプレートが用意されており、評価制度に合わせたフォーマットを簡単に作成することが可能です。
入力項目のカスタマイズにも対応しているのが一般的で、項目の追加や削除をすることで、組織ごとの運用ルールや職種別の評価基準に合わせた評価シートを容易に作成できます。
さらに、一部の製品では評価シートの自動生成機能も搭載されており、導入すれば評価シート作成業務の大半を自動化することも可能です。
評価シートの配布・集計機能
評価シートの配布・集計機能では、作成した人事評価シートの配布や回収、集計を効率化できます。評価シートの配布や回収は、従業員が多いと工数がかかりがちです。
人事評価システムでは評価対象者にシートを自動送信できるため、評価シートの配布業務を効率化できます。また、提出期限のリマインド通知を設定できるため、従業員の対応忘れを抑えることが可能です。さらに、提出状況のステータス管理ができる製品も多く、未提出者の把握や再通知の対応も容易に行えます。
集計時には回収したシートの内容が自動集計されるため、手動入力によるヒューマンエラーの心配もありません。集計結果もグラフや一覧で可視化できる場合が多いため、管理者や評価者が全体の傾向を把握しやすくなるのもメリットです。
評価業務の進捗管理機能
評価業務の進捗管理機能では、評価業務の進捗状況を確認できます。各評価タスクのステータス確認をリアルタイムで行えるため、提出の遅れや未対応の担当者を即座に把握することが可能です。
また、担当者ごとにタスク管理やスケジュール設定を行える製品も多く、リマインド通知機能などでタスクの期日を知らせてくれます。結果として、評価フローの全体像を可視化した上で、ワークフローに沿って業務を進行しやすくなり、評価業務全体を効率化できます。
評価データの分析機能
人事評価システムでは評価データの集計・分析が可能です。回収した評価シートの内容を集計し、データベース化した上で、指標をグラフで可視化できます。各従業員の従業員のスキルの把握やパフォーマンスの比較などが容易になるため、人材育成や育成方針の改善に繋げることが可能です。
また、各従業員のモチベーションの傾向も可視化できるため、離職防止施策や採用活動にも活用できます。現場ごとの評価のばらつきをデータ化することも可能で、評価基準の標準化を図ることも可能です。
組織図の可視化機能
組織図の可視化機能は、人事評価の前提となる組織構造や社員構成を可視化する機能です。階層構造や上司部下の関係性を直感的に把握できる他、部署間の連携状況も確認できるため、評価の公平性や一貫性を確保しやすくなります。
製品によってはリアルタイムで組織図を反映できる機能を搭載しているものもあり、導入すれば人事異動や組織構造の変更にも即座に対応可能です。
表示形式をカスタマイズできる製品も多く、組織構造が複雑な企業でも経営層から現場まで共有しやすい形式に整えられます。
人材データベース機能
人事評価システムではデータベースによる人材管理を行うことも可能です。従業員の基本情報や移動履歴、過去の人事評価などをシステム上に集約できるため、各従業員のデータをすぐに確認できます。
アクセス権限を付与すれば担当者以外もデータを確認できるため、経営陣や上司などに権限を与えれば、人事全般の業務を効率化することが可能です。
また、人事評価システムによっては人事管理だけでなく、採用管理を行うことも可能です。採用管理ができる製品では、自社の人材データから将来的に必要になる人材の洗い出しができる他、説明会や面接の調整、選考状況の管理などが行えます。
社内の人材データを採用活動に活かしたいのであれば、活用を検討してみても良いでしょう。
360度フィードバック機能
人事評価システムの中には、360度フィードバックに対応しているものもあります。360度フィードバックとは、上司や部下、同僚など複数の立場から評価対象となる従業員の評価を集約し、個人のパフォーマンスを多面的に把握する評価方法です。
多角的な視点から公平な人事評価をできるのがメリットですが、1人の従業員の評価を複数の人物から集計することになるため、どうしても工数がかかります。
360度フィードバック機能を搭載した人事評価システムであれば、評価者をグループ化した上での評価シートの配布・集計や、専用のレポートの作成などが可能です。結果として、360度フィードバックを効率良く実施できます。
MBO(目標管理制度)機能
MBOに関する機能を搭載している人事評価システムを導入すれば、MBOの効率的な運用が可能です。MBOとは「目標管理制度」のことで、企業の経営方針と各従業員が主体的に立てた目標をすり合わせ、従業員ごとの目標を設定した上で進捗から人事評価を行う手法のことを指します。
従業員の主体性やモチベーションの向上が期待できる上、主体的な目標設定をもとにしたフィードバックができるため、従業員の成長につながりやすいのがメリットです。一方で、従業員単位での目標管理や、進捗の把握に工数がかかりやすい欠点があります。
MBOに関する機能を搭載している人事評価システムであれば、個々の従業員の目標設定や進捗の可視化を最適化されたフォーマットで行えます。また、設定した目標と評価項目を連動できるため、効率良く生産性の高いフィードバックを実施することが可能です。
人事評価システムを導入するメリット

人事評価システムを導入すると以下のようなメリットがあります。
基本的には人事評価に関する業務を効率化できるのが大きなメリットです。それぞれ詳しく解説します。
人事評価やマネジメント業務を効率化できる
人事評価システムを導入する最大のメリットは、人事評価やマネジメント業務を効率化できることです。人事評価では主に以下のような業務工程を踏みます。
- 人事評価シートの作成
- 人事評価シートの配布
- 従業員による評価シートの記入
- 人事評価シートの回収
- データの集計・分析
特に工数がかかりがちなのが、人事評価シートの作成と回収です。特に従業員数が多い場合、評価シートの回収状況の把握や進捗が難しく、業務工程全体が遅れることも少なくありません。
人事評価システムを導入すれば、上記の業務を全体的に効率化できます。評価シートはテンプレートなどを利用して簡単に作成できる他、配布や回収もシステム上で行えるので、配布状況や回収状況を一目で確認することが可能です。
加えて、データの集計や分析も自動で行えるので、結果的に人事業務全体の業務効率を向上させられます。
人事関連のデータを一元管理できる
人事関連のデータを一元管理できることも、人事評価システムを導入するメリットです。従来、人事情報はExcelや紙資料で管理する場合が多く、情報が部門ごとの管理台帳に分散していることも少なくありません。
人事評価システムを導入すれば、形式や保管場所などが統一できていなかった人事評価に関する情報を、システム上に集約することが可能です。
結果として、情報の検索や更新がしやすくなり、人事評価業務を効率化できます。また、システムを軸にした情報管理体制を取ることで、部署間の情報共有や人材育成に関する連携がスムーズに行えるようになります。
加えて、情報の一元管理はセキュリティ対策の面でもメリットが大きいです。システム自体のセキュリティを万全にすれば、個人情報が流出するリスクを抑えられる他、バックアップを取ることでデータ消失のリスクにも備えられます。
以上のように、人事評価システムで情報を一元管理することで多くのメリットを享受することが可能です。
データを活用した人材育成が行える
タレントマネジメント機能が搭載された人事評価システムを導入すれば、人事評価のデータを人材育成に活用することが可能です。効果的な従業員の育成を行うためには、それぞれの従業員の持つスキルや経験を把握することが重要になります。しかし、事業規模の大きい企業では、従業員全員の能力を正確に把握するのが困難です。
一方で、画一的な手法で従業員の育成を行うと、従業員によっては効果がないことも少なくありません。人事評価システムを導入すれば、各従業員のスキルや経験、将来的なビジョンなどを効率的に集計・分析できます。
結果的に各従業員の改善点を把握した上で育成計画を立てられるので、効率良く組織全体のパフォーマンスを底上げすることが可能です。また、実際に育成に当たる上司も従業員が持つ課題を把握できるので、戦略的に従業員の育成が行えます。
適材適所な人員配置を戦略的に行える
人事評価システムの導入は人材配置にもメリットをもたらします。先述の通り、人事評価システムでは従業員全員のスキルや経験を可視化することが可能です。結果として、それぞれの従業員を最適なポジションに配置できます。
人事評価システムを利用しない場合、人材配置を決める際には現場の主観的な意見に頼らざるを得ないことも少なくありません。そのため、現場の上司などが従業員のスキルを完全に把握できていなかった場合、配属先で従業員がパフォーマンスを発揮できないリスクがあります。
人事評価システムを導入すれば、従業員の能力を客観的に把握できるようになるため、従業員と配属先のミスマッチを避けることが可能です。従業員としても自分の能力が活かせるポジションに配置されることになるので、モチベーションの向上にもつながります。
公正な人事評価ができる従業員のモチベーションを向上できる
評価が可視化されることで従業員のモチベーションアップにつながることも、人事評価システムを導入するメリットです。
従来の人事評価では工数の多さから従業員へのフィードバックがおろそかになりがちで、評価基準も明確にされていないことが少なくありません。そのため、従業員が自身の評価を明確に把握できず、モチベーションの低下につながる可能性があります。
人事評価システムを導入すれば、人事評価にかかる工数を削減できるため、従業員のフィードバックに時間をかけることが可能です。
また、システム上で評価基準や評価の根拠が確認できるため、従業員が評価に納得しやすくなります。結果的に従業員のモチベーションアップが上がり、組織全体の生産性向上につながります。
離職率の低下につながる
人事評価システムを導入して適切な人事評価を行うことは、離職率の低下にもつながります。先述の通り、人事評価システムを導入すれば、透明性の高い人事評価を実現することが可能です。そのため、従業員が評価に対して不公平感を感じることがなくなり、納得感を持って業務に取り組めるようになります。
さらに、人事評価業務の効率化によってフィードバックや面談に時間が掛けられるようになるため、従業員のモチベーションを継続的に維持し続けることが可能です。結果として、従業員が離職する理由が少なくなり、人材定着率の向上につながります。
人事評価システムを導入するデメリット

人事評価システムにはデメリットも存在します。主なデメリットは以下の通りです。
特に必要以上に多機能な人事評価システムを導入してしまうと、運用が複雑になり業務効率が低下するおそれがある点には注意が必要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
導入や運用にコストがかかる
人事評価システムを導入する際には、導入費用やランニングコストがかかることも覚えておきましょう。特に人事評価だけでなく、タレントマネジメントにも対応できるような多機能な人事評価システムの場合、費用が割高になることが多いです。
一方で、導入費用やランニングコストを抑えようと低コストなサービスを導入すると、必要な機能が搭載されておらず、想定通りの運用ができないことも少なくありません。
人事評価システムを導入する際には、まず必要な機能を洗い出した上で、費用対効果の高いものを選びましょう。
評価制度自体の見直しが必要になる場合がある
人事評価システムの導入にあたっては、評価制度自体の見直しが必要になる場合があります。特に紙やExcelでの運用を前提に評価制度を構築していた場合、評価基準や運用ルールがシステム上の仕様と大きく異なる場合も多く、制度自体の大幅な改修が必要になりがちです。
そのため、人事評価システムを導入する際は、導入費用やランニングコストといった金銭的なコストだけでなく、人的リソースや時間的なコストも考慮しなければいけません。
一方で、近年はリモートワークの普及や働き方改革、専門職の重要性向上などによって、従業員の評価基準が変化してきています。そのため、既存の人事評価制度が時代に合っていないことも多いです。
そのため、人事評価システムの導入に合わせて、人事評価制度をアップデートするのも有効な手段といえます。将来的な組織体制の変化も加味しつつ、時間をかけて評価制度の見直しを行うことで、今後の時代の変化にも柔軟に対応できる人事評価体制を実現しましょう。
社員情報の収集や整理が必要になる
人事評価システムの導入時には、評価制度の見直しだけでなく、社員情報の収集や整理に時間がかかることも考慮しておく必要があります。システムを導入しても、システム上に人事評価に必要な情報が集まっていなければ、業務効率化につなげることができません。
そのため、人事評価システムを導入する際には、システム上に従業員の情報や人事評価に関する情報を移行する作業や、自社の組織体制や運用方法に合わせた初期設定などが必要になります。
初期設定や情報の移行に十分な時間を設けないと、転記ミスや入力ミスによるトラブルに発展しやすいため、導入から運用開始までの間には十分な期間を設けるようにしましょう。
機能過多で運用が複雑になる場合がある
人事評価システムにおける機能の多様性は、コストだけでなく業務効率にも影響します。一見すると多機能なサービスを導入した方が導入するメリットが高いと考えがちですが、実際には機能が多いことで運用が複雑化し、かえって業務効率が低下してしまうことも多いです。
そのため、人事評価システムを選ぶ際には、必要以上に機能が搭載されたものを選ばないことが重要になります。
定性的な人事評価が難しくなる
人事評価システムを導入すると、評価制度のデジタル化により定量的な評価がしやすくなる一方で、定性的な評価が難しくなる側面があります。
システムを活用して人事評価を行うと、数値化しやすい項目が優先されやすく、主観的な視点や行動評価、コンピテンシーといった人物の本質に関わる要素が軽視されがちです。
たとえば感覚的な成長やチーム内での影響力といった側面は、評価シートや記録だけでは捉えにくく、納得感を得にくい結果につながることもあります。
そのため、人事評価システムを運用する場合は、面談の実施やフィードバックによって、定性的な評価を補完することが不可欠です。
また、360度フィードバック機能を搭載している製品であれば、多面的な意見を評価に取り入れられるため、定量的な側面を軽減できます。
人事評価システムを利用する場合は、数字だけに依存しないバランスの取れた評価体制を意識しましょう。
従業員のモチベーション低下を招くリスクがある
人事評価システムは従業員のモチベーション維持に活用できますが、使い方によってはかえってモチベーションを低下させてしまうリスクがあります。
評価制度の透明性が高まることがモチベーションになる従業員がいる一方で、評価が可視化されることがプレッシャーとなり、精神的な負担やストレスにつながることも少なくありません。
そのため、人事評価システムを導入する際は、自社の従業員の特性も把握し、データドリブンな評価制度が適切か確認する必要があります。また、導入後も従業員がストレスを感じないよう、フォロー体制を構築することが重要です。
人事評価システムの導入事例

人事評価システムの導入事例を紹介します。紹介する事例は以下の通りです。
それぞれ事例について詳しく見ていきましょう。
人事異動検討方法の刷新とペーパーレス化を達成した事例
人事考課も以前はすべて紙で管理していましたが、いまは評価ワークフロー機能「スマートレビュー」に集約しています。
目標管理、自己申告、人事考課表の3つのシートを運用していますが、作成者本人と管理者と人事ですぐに確認できますし、修正も即時に反映できます。紙ベースでは時間がかかっていた捺印の手間も省略化され、内容修正もカオナビなら簡単ですね。
今までは手間がかかるため修正自体に躊躇することがありましたが、期中に目標を変更するなど、今まであまり手をつけられなかったこともできるようになって来ました。
関西大学は紙ベースで人事異動や人事評価を管理しており、年間約1,500枚もの書類が発生していました。そのため、書類への捺印や手修正に膨大な時間がかかり、人事異動検討方法の刷新に工数が割けない状況でした。
そこで、人事異動検討方法の刷新と人事評価業務のペーパーレス化を実現するためにカオナビを導入しました。カオナビの導入後は教職員の情報が一元管理できるようになり、適切な人材配置や円滑な研修計画の立案を実現しています。
また、評価業務もカオナビ上で完結できるようになったことで、人事異動検討方法の刷新を実施することに成功しました。
1on1ミーティングの実施効果を高めた事例
1on1の実施記録や、目標変更の履歴も蓄積されるので、従業員個人も人事も状況をすぐに把握できます。現在、1on1実施率は100%で全社に浸透していますが、それがしっかり継続できているのも、HRMOSタレントマネジメントによる運用実態の「見える化」が影響していると思います。
ユニークビジョン株式会社では1on1による目標管理を人事評価の軸としています。しかし、従来の1on1では、議事録の管理や内容の共有が属人的で、情報が分散しがちだったため、人事評価への活用が難しいという課題がありました。
そこで、1on1の属人化解消と質の向上を目指して、1on1の記録をシステム上で一元化できるHRMOSタレントマネジメントを導入します。
結果、1on1の内容が記録によって可視化され、各従業員の課題抽出や目標達成までの進捗を把握しやすくなりました。組織としてのフォローもしやすくなったため、従業員の成長支援の効率化も実現しています。
人事評価業務の工数を年間150時間程度削減した事例
HRMOSタレントマネジメントの「ワークフロー」機能を活用したことで、提出したかどうかをすぐにチェックできるようになり、問い合わせ対応にパワーを割くことがなくなりました。評価点数の合計値や部署ごとの点数を取締役に報告する際も、すぐに集計できるようになりましたね。
合計で年間150時間程度の工数削減につながっており、わたしたちも各種認定取得に向けた取り組みや、内部監査の支援、また取締役会の資料作成といった業務範囲の拡大にも対応できています。
株式会社デジタル・ナレッジでは、紙やExcelを用いた従来の人事評価運用に多くの手間がかかっており、特に評価シートの配布・回収・管理に時間が取られていました。
そこで、HRMOSタレントマネジメントを導入し、評価シートの配布や提出状況の確認で確認できるようにしました。結果、人事評価業務の大幅な効率化に成功し、年間の工数を150時間程度削減することに成功しています。
評価結果の集計や分析が自動化されたことで、評価データを人材育成や配置検討に有効活用できるようになったことも、導入の大きなメリットとなっています。
人事評価システムの価格・料金相場
人事評価システムの価格・料金相場は、システムの提供形態によって違いがあります。
それぞれの費用相場は以下の通りです。
| 提供形態 | 費用相場 |
|---|---|
| クラウド型 | 初期費用:無料~20万円程度 月額利用料:1万円~6万円程度 |
| オンプレミス型 | 初期費用:数百万円程度 保守・管理費用:年間10万円~20万円程度 |
それぞれの費用相場の傾向について詳しく解説します。
クラウド型の費用相場
クラウド型の人事評価システムでは、提供企業が用意したサーバーに接続してサービスを利用することになります。
初期費用は高くても20万円未満であることが一般的で、製品によっては無料で利用できることも多いです。また、別途1万円~6万円程度の月額利用料が発生するのが特徴で、料金は機能や利用者数によって変動します。
段階的な機能追加や利用者数の増加にも対応している場合が多いため、企業の成長に合わせてアップグレードしやすいのも特徴です。
オンプレミス型の費用相場
オンプレミス型の人事評価システムは、社内に設置したサーバーにインストールする形で提供されます。サーバーの導入やシステムの構築が必要になるため、初期費用が高額になりがちで、数百万円かかることも少なくありません。
一方で、社内インフラ上でシステムを完結できることからセキュリティ性能が高く、自社の評価制度や業務フローに合わせた細やかなカスタマイズがしやすい点がメリットです。
また、クラウド型のような月額利用料が基本的に発生しないため、長期的な視点では費用対効果に優れています。
ただし、サーバーやシステムの保守・管理を外注する場合は、別途年間10万円~20万円程度の費用が必要になるので注意しましょう。
【まとめ】人事評価システムは自社の体制に合わせて選ぼう
人事評価システムのメリットやデメリット、比較ポイントなどを解説してきました。人事評価システムを導入すれば、工数がかかりがちな人事評価業務を効率化できます。サービスによってはタレントマネジメントや採用管理なども可能なので、人事業務全般の効率化が可能です。
人事評価システムを比較する際には、まず機能やコストについて確認しましょう。多機能なサービスは対応範囲が広いですが、高コストで運用が複雑化するおそれがあります。一方、必要な機能が絞れていれば、低コストのサービスも選択肢に入れることが可能です。また、サポート体制や既存システムとの連携性が自社に合っていれば、円滑に運用できるでしょう。
当記事を参考に、ぜひ自社に合った人事評価システムを探してみてください。

の口コミや評判は?選べる料金プランや導入メリットも解説-300x158.jpg)