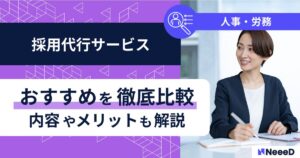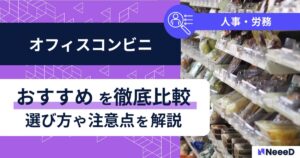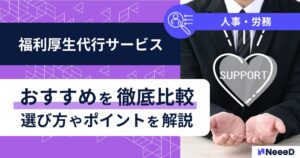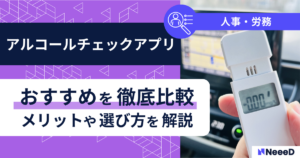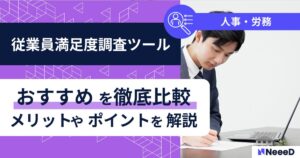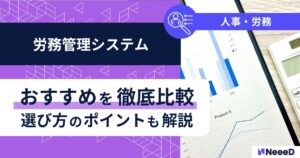【26年1月最新】社食サービスおすすめ4選を比較!選び方や費用相場も解説
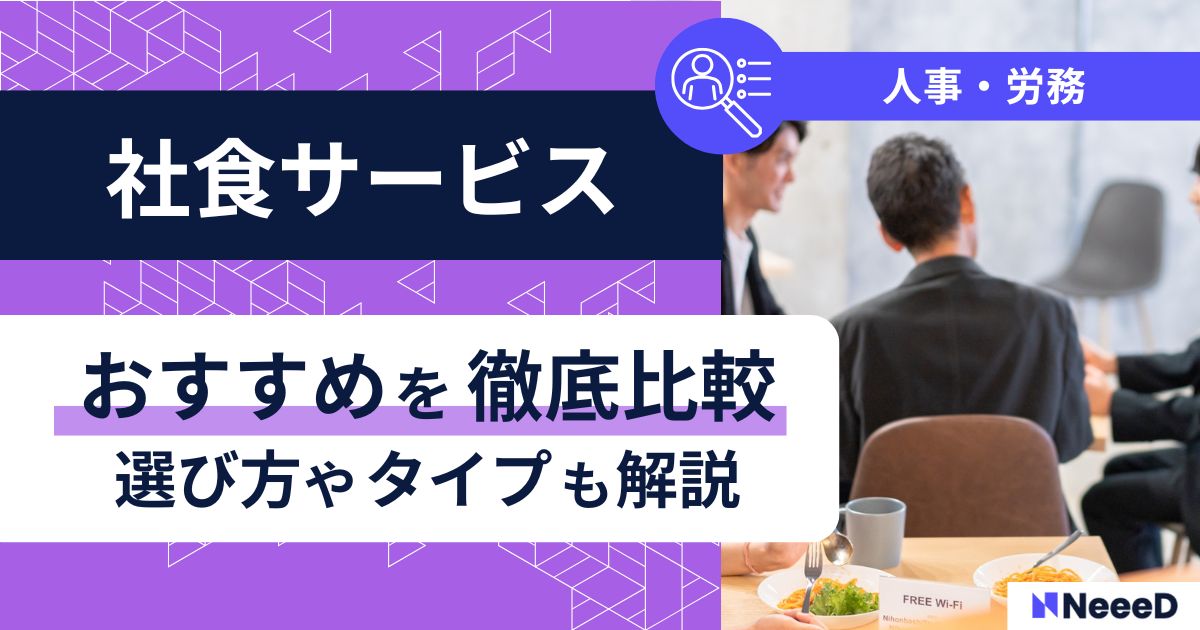
社食サービスは、従業員の健康サポートから企業イメージの向上まで、多くのメリットをもたらす福利厚生として、近年注目を集めています。
従来の社員食堂にとどまらず、オフィス設置型やデリバリー型、チケット型など、多様なサービス形態が登場しており、企業のニーズに合わせて選択できるようになりました。
この記事では、社食サービスの種類や導入のメリット・注意点、費用相場、そして失敗しないための選び方のポイントを詳しく解説します。自社に最適な社食サービスを見つけ、従業員の満足度向上と企業価値の向上を目指しましょう。
社食サービスおすすめ4選を比較
数ある社食サービスの中でも、特におすすめの4社をご紹介します。
| 社食サービス | 特徴 |
|---|---|
| チケットレストラン | 全国25万店舗で利用可能。30年以上提供され続けているサービス |
| OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)「ごはんプラン(冷凍)」 | 管理栄養士が監修した、健康的な旬のお惣菜メニューが食べられる |
| ごちクル | 多様なジャンルのお弁当をデリバリー。イベントや会議にも対応 |
| 社食DELI | 専用ブース必要で管理業務も最低限 |
それぞれの特徴を比較し、自社に合ったサービスを見つける参考にしてください。
チケットレストラン
| 料金プラン | 要お問い合わせ |
|---|---|
| タイプ | 代行サービス(チケット)型 |
| メニューの事例 | 全国チェーンの飲食店、大手コンビニ、Uber Eatsなど |
| 導入実績 | ・日本生活協同組合連合会 ・エステー株式会社 ・オーデマ ピゲ ジャパン株式会社 など |
| 会社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目4-5 アークヒルズサウスタワー7階 |
チケットレストランは、約150,000人に利用されている、代行サービス(チケット)型の社食サービスです。
全国25万店舗以上の飲食店、コンビニ、Uber Eatsなどで利用できるため、利用者の選択肢が非常に広いのが特徴です。
ICカードにチャージされた残高を飲食店で利用できます。そのうちの一定額を企業が補助することで一部がカバーされ、実質的な食事補助として機能します。
専用冷蔵庫などの設置スペースが不要なため、様々なオフィス環境に対応可能です。出社・在宅勤務問わず、どんな従業員も公平に利用できるため、勤務地を問わず食の福利厚生を提供したい企業に最適です。
OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)「ごはんプラン(冷凍)」

| 料金プラン | 初期費用:70,000円 月額料金:35,000円(80個パック) 追加注文(40個パックごと):17,500円(税別) |
|---|---|
| タイプ | 設置型 |
| メニューの事例 | サラダごはん、ビーフハヤシ、こだわり肉惣菜、野菜グラノーラなど |
| 導入実績 | ・日本マクドナルド株式会社 ・阪急阪神不動産株式会社 ・医療法人社団せいおう会 鶯谷健診センター など |
| 会社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目28番5号 第2オークラビル5階 |
OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)の「ごはんプラン(冷凍)」は、健康に気遣った食事をリーズナブルにオフィスで提供できる、設置型サービスです。
管理栄養士が監修した栄養バランスの良いお惣菜が、毎月約40種類届きます。メニューは毎月入れ替わるため、飽きずに楽しめるでしょう。
健康的な食事がオフィス内で安価に購入でき、食事を買いに行く手間が省けるため、コンビニや飲食店が近隣にない勤務地でも便利です。
冷凍惣菜のため、オフィスで解凍して持ち出せば、外勤の従業員も外出先で手軽に食べられます。
ごちクル
| 料金プラン | 要お問い合わせ |
|---|---|
| タイプ | デリバリー型(お弁当型) |
| メニューの事例 | 日替わり弁当、幕の内弁当、洋食弁当、オードブル、サンドイッチなど |
| 導入実績 | 非公開(多数の企業・団体に導入実績あり) |
| 会社所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山 2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F |
「ごちクル」は、全国の厳選されたお弁当やケータリングをオフィスに届けるデリバリーサービスです。
日替わり弁当からイベントや会議用の豪華なお弁当まで、和食、洋食、中華、エスニックなど豊富なジャンルと価格帯から選べます。
毎日のランチだけでなく、社員イベントや会議など、多様なシーンで活用できます。事前予約で指定の時間にオフィスまで届けてくれるため、準備の手間がかかりません。
アレルギー対応やベジタリアンメニューなど、個別のニーズにも対応可能な場合が多く、多様な食の好みにも応えられます。
社食DELI

| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| タイプ | デリバリー型(お弁当型) |
| メニューの事例 | 和食洋食 中華料理 エスニック料理 日替わり弁当など |
| 導入実績 | ダイキン工業株式会社 ヤマハ株式会社 森永製菓株式会社など |
| 会社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル11F |
社食DELIは管理業務の負担を抑えて従業員満足度を向上させたい企業におすすめの社食サービスです。
福利厚生制度に合わせた価格設定で従業員が弁当を購入できるシステムになっており、企業としては経費を増やしつつ、手頃な価格で社食の提供ができます。
また、社内の空きスペースやカウンターテーブルなどで弁当を販売できるため、専用ブースが必要ありません。加えて、発注から回収・生産まで一括で代行してくれるため、管理業務も抑えられます。
売れ残りの費用負担も発生せず、コストを最小限に抑えることも可能です。累計導入社数は700社を超えており、中小企業から大企業まで、業種を問わず利用されています。
サービスの導入によって部署を超えた社内交流が活性化した事例もあるため、社内連携を強化したい企業にもおすすめの社食サービスです。
社食サービスとは?

社食サービスとは、企業が従業員に提供する食事の福利厚生全般を指します。単に食費を補助するだけでなく、健康支援や働きやすさの向上が目的です。
従来の「社内に食堂を構える形態」だけでなく、多様な働き方に対応できる様々なスタイルの社食サービスが登場しています。
近年、在宅勤務やフレックスタイムの普及により、食事のタイミングやスタイルも多様化しています。社食サービスは、こうした変化に柔軟に対応できる福利厚生として注目を集めています。
社食サービスの4つの形態
社食サービスには様々な形態がありますが、大きくは以下の4つに分類できます。
それぞれの特徴を見ていきますので、自社に合う形態の社食サービスを探しましょう。
設置型(置き型)
設置型(置き型)は、オフィスに専用の冷蔵庫や冷凍庫を設置して、従業員が好きな時に食事を摂れる形態の社食サービスです。
オフィス内に常に食事が用意されているため、買いに行く手間が省け、自分のタイミングで休憩・食事ができるのがこの形態のメリットです。
シフト制勤務で休憩時間が不規則な職場や、朝食や夕食として利用したい場合にも柔軟に対応できます。出勤前後にも利用できるので、多様な働き方に対応できます。
設置スペースは必要ですが、従業員同士のコミュニケーション促進にもつながるサービスです。
デリバリー型(お弁当型)
デリバリー型は、毎日決まった時間にオフィスにお弁当などが配達される社食サービスです。事前に注文しておけば、できたての食事がオフィスに届きます。
当日分の食事を一時的に保管するだけのため、多くのスペースを必要としないのが特徴です。
設備投資を抑えたい企業に向いていますが、利用できるサービスは地域によって異なるため、自社がサービス提供エリア内か事前に確認が必要です。
提供型(ケータリング型)
提供型は、オフィス内の会議室などを活用し、決まった時間に温かい食事やお弁当を一斉に提供する、ケータリング形式の社食サービスです。
社内に調理場がなくても利用できて、準備や片付けの手間が少ないのがメリットです。全従業員が同時に休憩を取る職場に適しており、温かい食事が手軽に楽しめるため、ランチの満足度が大きく向上します。
デリバリー型との大きな違いは、配膳までスタッフが行い食事の場を提供する点です。社員の一体感を醸成する機会としても活用でき、イベント時など大人数での食事会にも柔軟に対応可能です。
チケット型・代行サービス型
チケット型・代行サービス型は、提携している飲食店やコンビニを社員食堂の代替として利用できる社食サービスです。
オフィスに食品が配達されたり常設されるタイプと比べて、メニューの選択肢が格段に広がります。加盟店の中から好きな店舗を選んで利用できるため「好みのメニューがない」といった不満が起こりにくいのが特徴です。
全国で利用できるため、特に外勤者の多い職場や在宅勤務の従業員に喜ばれます。また、食事スペースや備品の確保が不要なため、初期費用や導入後の手間を大幅に削減できるのも大きなメリットです。
失敗しない社食サービスの8つの比較ポイント
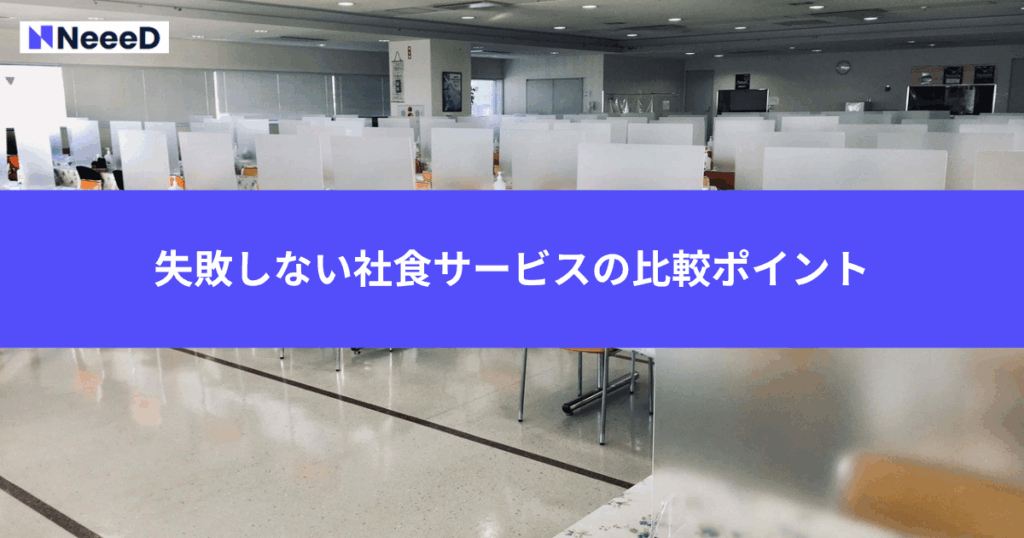
社食サービスを選ぶ際は、以下の8つのポイントに注目して比較しましょう。
これらのポイントを押さえることで、自社に最適な社食サービスを見つける近道になります。
社員のニーズ(食事の好み)
社食サービスは、社員の満足度と利用促進に直結するため社員のニーズに合わせた内容を選ぶことが重要です。
食事の好みは人それぞれに異なります。「ボリュームのあるお弁当が食べたい」という人もいれば、「健康に配慮した食事がいい」という要望もあるでしょう。
ニーズを反映したサービスを選ぶことで満足度が高まり、結果として社食サービスの利用が促進されます。反対に、ニーズに合わないサービスは利用されにくいため、事前の確認が不可欠です。
導入前にはアンケートなどを実施し、社員が求めるメニューをしっかりと把握しましょう。
メニューの品数(サイクル・季節イベントなど)
社食サービスのメニューが単調だと、社員が飽きてしまい利用率が低下することがあります。
継続的に多くの社員に利用してもらうためには、飽きさせない工夫があるサービスを選ぶことが大切です。
メニューの数だけでなく、日替わりや週替わりなどのローテーションや、季節ごとのイベント、期間限定メニューがあるサービスなどは、長く利用しても飽きにくい傾向があります。
豊富な選択肢から毎日のランチを選べることは、社員のモチベーション維持や満足度向上にもつながります。
提供形態と利用可能な時間帯
近年は働き方が多様化していますが、自社の社員がいつ、どこで食事をとっているかを把握しているでしょうか。
外勤の社員が多い職場では、コンビニや飲食店で利用できる代行サービスやチケット型が便利です。一方、内勤主体の職場には、オフィス内で食事が完結する設置型や、デリバリー型が適しています。
昼食の休憩時間が決まっている職場であれば、できたての食事が届く提供型が喜ばれるでしょう。
社員の働き方に合った提供形態と利用時間帯のサービスを選ぶことで、利便性が向上し、利用率もアップします。
コスト(予算内で収まるか)
社食サービスの導入には、初期費用や月額費用、企業側が負担する食事代補助などのコストが発生します。予算を明確にし、その範囲内で継続できるサービスを選ぶことが大切です。
単に価格が安いだけではなく、会社が補助する金額や、福利厚生費として非課税となる条件(1人あたり月3,500円以下)なども考慮して、トータルコストで比較しましょう。
また、費用が発生するタイミングや項目などを事前に整理し、導入後のランニングコストも把握することで、安心して継続できます。
配達エリア
社食サービスの配達エリアが自社の拠点に対応しているか、必ず事前に確認しましょう。全国展開しているサービスもあれば、特定の地域に限定されているサービスもあります。
支社や工場など複数の拠点を持つ企業では、本社以外の拠点にも同じ条件でサービスを提供できるか、などもポイントです。
また、交通事情や天候による配達遅延時の代替策や返金ポリシーについても確認しておけば、万が一の際もスムーズに対応できるでしょう。
サポート体制
社食サービスを導入する際は、サービス内容だけでなく、サポート体制の充実度も非常に重要です。
たとえば、ゴミの回収方法、トラブル発生時の問い合わせ窓口の有無、急な追加注文やキャンセルへの対応可否などは、事前に確認しておくべきでしょう。
また、QRコードやICカードなどの決済手段への対応状況や、在庫管理システムの使いやすさも、担当者の業務負担を左右する重要な要素です。
これらの運用面での支援が充実しているかどうかが、導入後にスムーズに社食サービスを運用できるかの鍵となります。
条件(契約期間や違約金など)
多くの社食サービスでは、一定期間の契約が前提となっており、途中で解約すると違約金が発生するケースもあります。
契約を結ぶ前に、契約期間、解約条件、違約金の有無と金額を必ず確認しておきましょう。
またサービスによっては、最低注文数の設定や、短期解約時のペナルティが設けられている場合もあります。
万が一の解約時にも大きな負担とならないよう、柔軟な契約条件を提供しているサービスを選ぶとよいでしょう。
導入までの手間や社内の負担
社食サービスを選ぶ際は、導入から運用開始までにかかる「社内担当者の負担」も検討すべきポイントです。
導入から開始までにかかる手間や、日々の注文方法や精算の手順、在庫管理など、担当者の負担がどの程度発生するかを事前に把握しておきましょう。
サービスによっては、導入手続きが非常に簡単で、担当者の手間を大幅に削減できるものもあります。
スムーズにサービスを立ち上げ、社員が快適に利用を開始するためには、サービス会社のサポート体制やマニュアルの有無も確認しておくことをおすすめします。
社食サービスにかかる費用の相場

社食サービスにかかる費用は、サービスの形態によっても異なりますが、主に以下の3つに分けられます。
サービスを決める際は、これらの費用をトータルで比較し、自社の規模や予算に合わせた最適なサービスやプランを選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの費用の相場などについて解説します。
初期費用
社食サービスの初期費用は、形態によって大きく異なり、無料から数十万円まで幅があります。
設置型やデリバリー型のサービスでは、初期費用ゼロで導入できるものもあります。提供(ケータリング)型やチケット型でも、初期費用がかからない場合が多いです。
一方で、初期導入費用が発生するケースもあります。特に、大規模な食堂スペースを新設したり、キッチン設備を整備するような場合は、高額な初期投資が必要になることがあります。
導入形態によって初期費用が大きく異なるため、自社の予算と照らし合わせて検討することが大事です。
月額費用(ランニングコスト)
社食サービスの月額費用(ランニングコスト)は、サービス形態によって変わります。
設置型(置き型)では、固定費として月額25,000円〜50,000円程度が発生するサービスが多く、それに食事の購入代金(100円〜500円/個)が加算されます。定額制プランがあるサービスもあります。
デリバリー型・提供型は、1食あたり300円〜1,000円程度の食事代が中心で、利用頻度や注文数によって変動します。配送料が別途かかる場合もあります。
チケット・代行型サービスは、システム利用料と企業が従業員へ補助する金額(1食500円〜1,000円が目安)が発生します。
その他費用
上記の初期費用や月額費用以外にも、社食サービスには様々な費用が発生する可能性があります。
たとえば、特定のメニュー追加や栄養相談などの追加オプション費用、配送費、在庫管理費用などです。他にも、追加注文やキャンセル手数料が別途発生する場合もあります。
また、机や電子レンジなどの備品レンタル料や、一部のサービスでは専用システムのシステム利用料が必要となるケースもあります。
これらの費用項目はサービス提供会社ごとに異なるため、契約前に全ての費用を確認し、トータルコストを把握することが重要です。
社食サービスを導入する6つのメリット

社食サービスを導入することにより、以下のようなメリットが得られます。
自社が社食サービスに何を求めるのか、イメージと照らし合わせながら最適なサービスを選びましょう。
食生活が充実して健康管理がしやすくなる
社員が栄養バランスの取れた食事を摂りやすくなることは、社食サービス導入の大きなメリットです。ファストフードやコンビニ弁当が多いと、生活習慣病のリスクを高めます。
社食サービスには管理栄養士監修のもと、栄養バランスが考慮されているメニューが多いため、リスクを低減できます。旬の食材を取り入れたり、カロリー表示を行うことでも、健康的な食生活のサポートが可能です。
体の健康は心の健康にも直結し、バランスの取れた食事はメンタルヘルスにも良い影響を与えます。社員が健康に働ける職場環境にすることは、企業の健全化にもつながるでしょう。
社員の満足度や働きやすさがアップする
社員のニーズに合った社食サービスは、会社への満足度と働きやすさを大きく向上させます。
手軽に食事ができる環境があると、社員は日々の「ランチ選び」から解放されます。特に、健康を意識した栄養バランスの良いメニューが選択肢にある満足度は高く、結果として働くモチベーションアップにもつながります。
ランチタイムが充実することで社員に活力が生まれ、全体的な働きやすさの改善も期待できるでしょう。
仕事の生産性や効率性が高まる
食生活の充実は、仕事のパフォーマンスにも直結します。健康的な食事は午後の眠気を防いだり、集中力を維持したりする上でも大切です。
企業が成果を上げるためには、社員の健康増進やモチベーション向上が欠かせません。その中でも「食事」は、日々のコンディションを左右する重要な要素です。
社食サービスがあると、社員は必要な栄養素を摂取しやすくなります。バランスの取れた食事は社員の体調を整え、結果的に業務効率の改善も期待できます。
社食サービスで福利厚生を充実させることは、社員の健康を支え、ひいては企業の生産性向上にも役立つでしょう。
社内コミュニケーションが活性化する
社内コミュニケーションの活性化も、社食サービス導入の大きなメリットのひとつです。食事スペースには自然と社員が集まるため、部署を超えた会話や交流が生まれやすいです。
フレックスタイム制や在宅勤務の普及により、社員同士が顔を合わせる機会が減少している企業にとって、社食サービスは貴重な交流の場となります。
共に食事をすることで社員の関係性が深まり、信頼やチームワークの向上にもつながるでしょう。
良好な人間関係と活発なコミュニケーションは、企業の一体感を促進し、業務の質を高めることに繋がるため、社食サービスはそのためにも有効な手段です。
採用率や定着率が向上する
社食サービスが充実していることは、求職者にとって非常に魅力的な福利厚生の一つです。「社食完備」は、求人訴求力を高める効果があります。
また、働きやすさが向上することで、既存社員の定着率向上も期待できます。職場で不満に思うことの理由として、「食事を適切な時間に十分な量摂れないこと」があり、それが離職理由となるケースもあります。
社食サービスによって社員の食生活や食事環境を整えることは、ワークライフバランスを重視する現代において、優秀な人材の離職を防ぎ、企業に定着させるための有効な人事戦略となるでしょう。
企業イメージの向上につながる
社食サービスが充実している企業は、求職者にとって「働きやすい会社」というポジティブなイメージを与えやすくなります。
福利厚生は、求職者が企業を選ぶ上で、給与や業務内容と並んで重要視する項目です。
充実した社食サービスがあることは、企業にとって大きなアドバンテージです。SNSや採用サイトでのビジュアル訴求も可能となり、採用ブランディングの強化にもつながります。
これにより他社との差別化を図り、優秀な人材の獲得に貢献するだけでなく、社員を大切にする企業としてのイメージ向上にも大きく寄与するでしょう。
社食サービスを導入する5つの注意点
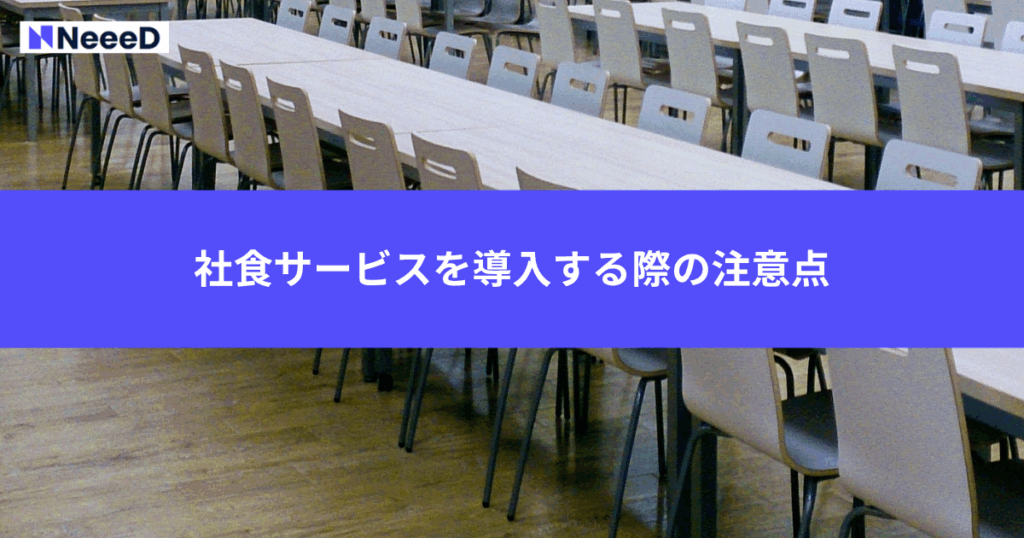
社食サービスを導入する際には注意点があります。主に以下の5点に気をつけることで、失敗を防ぎやすくなるでしょう。
導入前に「実際に社員がどのように使うか」「誰が管理するか」まで具体的にイメージしておくことで、失敗を回避できます。
費用対効果の検証不足
社食サービスの導入では、初期費用や月額費用、食事補助の負担など様々なコストが発生します。福利厚生の支出が経営に与える影響を考慮することも重要です。
社食サービスには社員の健康増進や満足度向上、生産性向上といった効果が期待できます。しかし、発生する費用と効果が見合っているか、費用対効果を慎重に検証する必要があるでしょう。
また、企業と従業員が負担する費用のバランスを明確にし、どちらにもコストをかけすぎないようにするなど、導入前に検討して決めておくことをおすすめします。
社員の追加業務が発生
社食サービスを利用すると、食事の提供や維持などで社員の追加業務が発生する可能性があります。
例えば、割り箸や醤油などの補充、食事スペースの清掃やテーブル拭きなどです(設置型の場合)。デリバリー型では、注文や集金、利用状況の管理や在庫確認などが発生することがあります。
これらは、ひとつずつは重い業務ではありませんが、特定の社員がまとめて担当するようになると大きな負担となる可能性があります。担当を当番制にするなど、工夫が必要になることもあるでしょう。
できるだけ簡単な運用方法や、手厚いサポート体制が整っているサービスを選ぶことで、社員への負担を最小限に抑えることができます。
メニューのマンネリ化
固定化した食事メニューに社員が飽きてしまうリスクは、社食サービスの重要な注意点です。場合によっては、ほとんど利用されなくなってしまうこともあります。
不人気を避けるためには、メニューの多様性と定期的な入れ替えが有効です。社員の好みに対応したメニューを増やしたり、季節の食材を取り入れたりするなど、飽きさせない工夫も必要です。
メニューのマンネリ化を避けられるサービスを選ぶことで、利用率の低下を防げます。提供される食事の種類や、メニュー更新の頻度を確認し、多くの社員が継続して満足できるラインナップであるか見極めましょう。
利用率の偏り
社食サービスを導入しても、従業員全員が均等に利用するとは限りません。
設置型やデリバリー型はオフィス出勤者が主な対象となります。在宅勤務や外勤の社員はメリットを感じられず、それが不公平感や不満につながる場合があります。
利用率を偏らせないためには、リモートワークやシフト勤務など多様な働き方に対応できるサービスを選ぶことが重要です。
社員のワークスタイルが多様な企業では、自宅や営業先近くの店舗を利用できる代行型社食サービスを導入することで公平感を保てるでしょう。
スペースの制約
社食サービスを導入する際、オフィス内に専用の冷蔵庫や棚などを設置するための十分なスペース確保が課題となることがあります(特に設置型の場合)。
スペースが不足していると、従業員の動線が悪くなったり、既存の休憩スペースが狭まったりして、かえって快適性を損ねてしまうかもしれません。
また、既存の設備の移設・撤去が生じる場合は、それに伴う費用や手間も発生します。導入前に設置場所を確認し、それに伴う影響も考慮することが重要です。
社食サービス・比較 に関するよくある質問(FAQ)

社食サービスの導入や比較に関する「よくある質問」をまとめました。
社員のニーズに合ったサービスを見つけるための参考にしてください。
社食が安い理由は何ですか?
社食が安価に提供できる主な理由は、スケールメリットによるコスト圧縮と、会社の補助や福利厚生の非課税枠を活用している点にあります。
中央キッチンで大量に調理することで、仕入れコストを削減し、効率的なルート配送によって物流コストを抑えます。これにより、一般の飲食店では難しい低価格を実現しています。
また、企業が食事代の一部を補助し、その補助金が一定の条件を満たせば福利厚生費として非課税になります。このような理由で、社員は市場価格よりもはるかに安い値段で食事を享受できる仕組みです。
社食の値段相場はいくら?
社食の値段相場は、サービス形態や地域、企業の規模によって異なりますが、一般的には1食あたり250円から800円です。
具体的な内訳としては、置き型社食は軽食中心で250円から500円、デリバリー弁当は400円から700円程度が主流です。
サブスクリプション型の場合は、1人あたり月3,000円から5,000円が目安となります。都心部の大手企業では1食あたり500円から800円程度が多い一方、地方の中小企業や工場などでは250円から400円程度が一般的です。
置き型社食のデメリットは?
置き型社食のデメリットは、温かい料理を提供するためには電子レンジが必須となることです。設置には冷蔵庫や電源スペースの確保が必要になります。
また、メニューのマンネリ化も起こりやすく、社員が飽きてしまう可能性があります。
ほかにも、食事スペースの確保や衛生管理の手間、決済方法の選択肢が限られるといった課題があります。
「サブスク型社食」とは何ですか?
サブスク型社食とは、従業員1人あたりに定額料金を支払うことで、食事が無制限、または上限回数まで利用できるサービス方式です。
この形態では、オフィス内に冷蔵庫や棚が設置され、社員が自由に食事や軽食、飲料などを利用できます。
一定料金で定期的に食事を提供することで、社員は費用を気にせず食事を摂ることができ、企業側も管理の手間を軽減できるメリットがあります。
社食は福利厚生費にできますか?
社食にかかる費用は福利厚生費として計上可能です。
ただし、税務上の非課税扱いとなるには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、従業員が食事代の半分以上を負担していること、そして会社の補助額が月額3,500円(税抜)以下であることです。
これらの条件を満たせば、会社が負担した分を福利厚生費として計上し、税務上の優遇を受けられます。企業のコストを抑えつつ、社員の食生活を支援できる制度です。
昼ごはん代を福利厚生費にできますか?
昼食代も特定の条件を満たせば、福利厚生費として処理できます。
社食と同様に、従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ会社の補助額が月額3,500円(税抜)以下であれば、非課税の福利厚生費として認められます。サブスクリプション型社食や食事補助カードのように、会社が一律で補助金を支給する場合に適用できます。
ただし、昼食代を個別に現金で支給してしまうと、給与課税の対象となります。
社員食堂が有名な会社はどこですか?
社員食堂が有名な会社としては、Google Japan、サイバーエージェント、メルカリ、LINE、楽天などがあります。
これらの企業は、単においしい食事を提供するだけでなく、無料または非常に低価格で提供したり、管理栄養士監修の健康的なメニューを豊富に揃えたりしています。
また、SNS映えするような内装や、社員の交流を促すイベントメニューなども特徴です。
「社食 すごい 会社」と検索すると出てくる企業にはどんな特徴がありますか?
「社食 すごい 会社」と検索して出てくる企業は、主に3つの特徴があります。まず、無料提供や100円均一など、価格に強いインパクトがある点。
次に、管理栄養士監修のメニューや地元食材の活用により、社員の健康増進やSDGsへの貢献を打ち出していること。最後に、SNS映えするようなおしゃれな内装や、季節ごとのイベントメニューなどによって、企業ブランディングを強化している点です。
こういった企業の取組みによって、社食は単なる食事提供を超え、社員の満足度向上や企業イメージアップのためのコンテンツとなっています。
健康経営と社食サービスの関係は?
社食サービスの充実は、近年話題の「健康経営」においても重要です。
栄養バランスの取れた食事によって、従業員の健康維持に貢献し、生活習慣病のリスクを低減させます。結果として生産性向上や離職率の低下にも寄与します。
社食サービスは健康経営優良法人の評価項目の一つとして、企業価値を高めるための施策といえるでしょう。
助成金や補助金はありますか?
社食に特化した直接的な助成金はありませんが、自治体や国の一部補助制度が利用できるケースがあります。
具体的には、健康経営や福利厚生促進を目的とした補助金制度の一部が社食サービス導入に適用できる可能性があります。各自治体の健康づくり施策や中小企業向けの支援制度を確認してみましょう。
また、経済産業省の「健康経営度調査」の加点施策として評価されることで、間接的に税制優遇を受けられる可能性もあります。
小規模オフィスでも導入できますか?
小規模オフィスでも社食サービスを導入することは十分可能です。
特に置き型社食やサブスク型社食は、初期コストがほとんどかからず、手軽に導入できるため、従業員が10名から30名程度のオフィスにも適しています。
置き菓子ボックスや冷蔵庫1台を設置するプラン、週1回程度の少量デリバリーサービスなど、小規模オフィス向けのプランもあります。
トライアル期間や試食はありますか?
多くの社食サービスでは、トライアル期間や試食サービスを提供しています。
実際のサービスの品質や運用方法を体験し、自社のニーズに合っているかを確認できます。無料試食や、1週間〜1か月程度の割引トライアルが用意されていることが多いです。
興味のあるサービスがあれば、まずは直接問い合わせて、トライアルの有無や詳細を確認してみることをおすすめします。
【まとめ】多くの従業員に満足してもらえる社食サービスを選ぼう
社食サービスは、従業員の健康維持から企業イメージ向上まで、多様なメリットをもたらします。
しかし、単に導入すればよいわけではなく、従業員の食の好みや多様な働き方に対応できる提供形態、そして費用対効果を十分に考慮することが重要です。
この記事で解説したポイントを踏まえ、自社のニーズに最も合ったサービスを選ぶことで、多くの従業員に喜ばれ、企業価値を高める社食サービスを実現できるでしょう。


の口コミや評判は?選べる料金プランや導入メリットも解説-300x158.jpg)