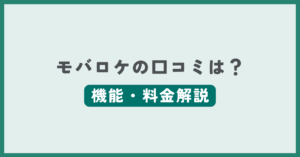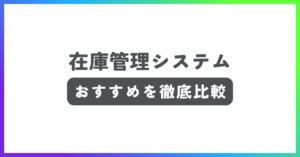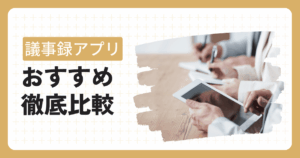車両管理システムのおすすめ4選比較!【料金無料〜人気No.1もあり】
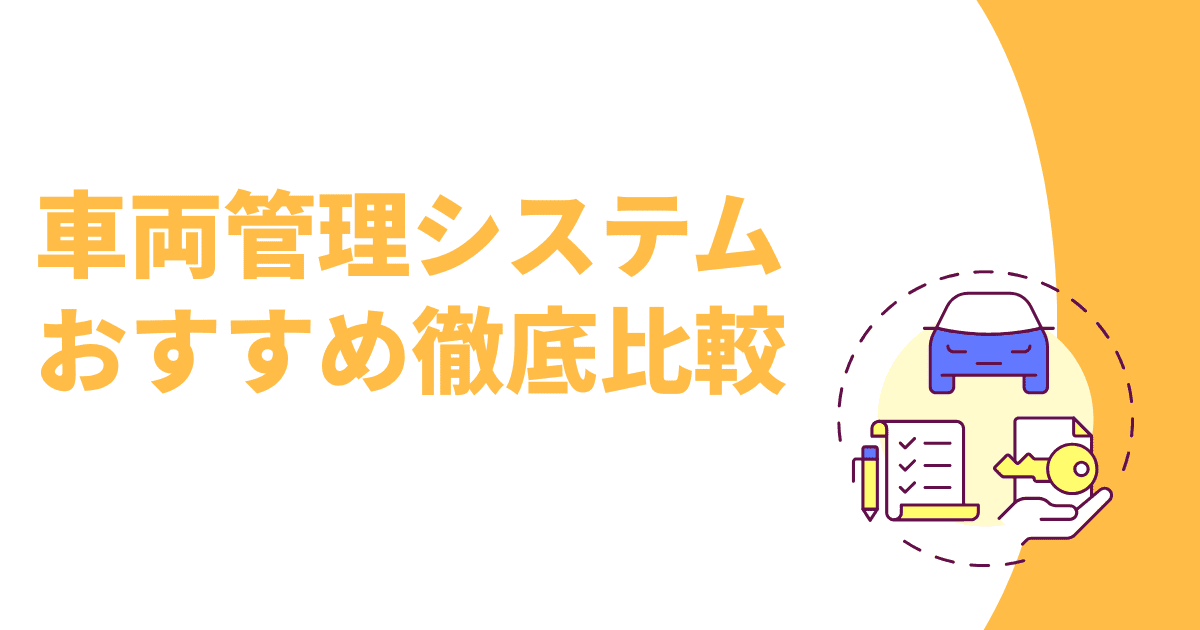
社用車やドライバーごとの情報を効率的に管理し、業務の負担を減らしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
車両管理システムを使えば、車両の保険や車検などに加え、ドライバーの免許期限や運転傾向といったさまざまな情報を一元管理できます。
また、GPSを介してドライバーの位置情報がリアルタイムでチェックできるため、道路状況に応じた指示出しなど、効果的なバックアップも可能です。
この記事では、おすすめの車両管理システム4選、導入時の比較ポイントや導入メリットについて解説します。
費用相場なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です
車両管理システムを比較する際の選び方

車両管理システムの導入を検討する際は、いくつかの判断基準を設けておけば、自社に適したシステムを見つけやすくなるでしょう。
ここではシステム比較時のポイントを8つ解説します。
車両管理業務や運転業務を最短で効率化するシステムを選ぶための参考にしてください。
位置情報の精度は高いか
ドライバーや車両ごとへの適切な指示出しには、正確な情報が必要です。道路状況がリアルタイムで更新されれば、管理側とドライバー側とのコミュニケーションも円滑に行えます。
位置情報の精度や速報性を重視し、ドライバーへのサポートが十分に行えるシステムを導入しましょう。
デバイス設置が簡単か
導入時の手間やコストを削減するためには、なるべくデバイス設置が簡単なシステムを選びましょう。
車両管理システムにはデバイスの種類が豊富にあり、企業によっては大規模な工事が必要なケースがあります。
車両に設置した小型デバイスに差し込むだけのタイプだったり、スマホと連携させるだけのタイプであったりすれば、自社の担当者でも簡単に設置できるでしょう。
システム導入時は、自社の限られた業務時間の中で、いかに手間を省けるかが重要なポイントです。
自社の課題に対応できるか
車両管理システムを選ぶ際は、「自社の抱える課題にそのシステムが対応できるか」を見極めましょう。
「おすすめ」や「人気」だけで選んでしまうと、本来の目的は達成されません。
たとえば、車両コストの見える化が課題であれば、燃費や走行距離、メンテナンス履歴などを詳細に管理できる機能が備わっているかを確認する必要があります。
他にも、下記のような課題がある企業も多いでしょう。
- ドライバーの安全管理を強化したい
- 帳票出力などの事務処理を効率化したい
システムの導入効果を最大限に引き出すには、各社が抱える課題や改善したい業務内容を洗い出したうえで、それにマッチした機能を持つ製品を選ぶことが大切です。
システムの操作性は優れているか
システムの使いやすさは、あらゆる車両管理機能を最大限生かすことに直結します。
複雑で操作しにくいシステムは日常業務でうまく利用できず、教育にも時間がかかってしまいます。新入社員でも直感的に操作できるくらいの分かりやすいシステムが理想的と言えるでしょう。
また操作性に優れていれば、担当者が変わっても引き継ぎしやすく、長期運用を前提とする場合も安心です。
無料版で機能性を確かめられるか
無料お試し期間があるツールは、実際の使用感を事前に確認できて便利です。有料導入後に「自社に合わないかも」と気づくのでは、時間もお金も無駄になってしまいます。
無料版で機能をしっかり確かめつつ、現場ドライバーなどの声も聞きながら慎重に検討すれば、理想と現実のギャップがない運用が実現できるでしょう。
他システムと連携できるか
車両管理システムを導入する際は、他システムとの連携ができるかも重要なポイントです。
API連携が可能なシステムであれば、データをリアルタイムで共有でき、業務の手間を削減できます。
特に、勤怠管理・会計ソフト・配送管理システムなどとスムーズに連携できるかを確認しましょう。
データの連携ができれば、経費管理や予算策定の精度が高まり、業務効率の改善につながります。
またデータを、CSVやエクセルなどの一般的な形式でエクスポートできれば、会議資料などにも活用可能です。
ドライバーに指示が出しやすいか
ドライバーへの指示の出しやすさは、業務の円滑化に直結します。物理的な距離が出来てしまう管理者とドライバーとの間には、どうしても意思の疎通が難しい場面が多くなります。
そのため、双方向のメッセージ機能を備えていれば、管理者とドライバーの円滑なコミュニケーションを促せます。
また多くの車両管理システムは、リアルタイムで情報を取得できるため、危険運転時にはアラートで呼びかけることも可能です。
直感的に操作できるシステムを選ぶことで、より迅速な指示出しと業務効率化の実現が目指せるでしょう。
サポート体制は優れているか
優れたサポート体制は、システムの安定的な運用や安全な運転支援、突発的なトラブルへの対応に欠かせません。
特に、システムトラブルの発生時は迅速に解決しないと取引先を待たせてしまい、損失を生み出す可能性があります。
システム担当者でも対応できない場合、頼れるのは提供企業のサポートチームのみです。夜間に営業することも多い運送会社などは、24時間365日対応のサポート体制が整ったシステムを導入すると、急なトラブルにも対応しやすいでしょう。
また、FAQ欄やAIチャットサポートが充実していれば、小さな疑問などはすぐに解決できます。
車両管理システムの比較表
 |  | |||
| 機能 | リアルタイムの車両位置情報可視化 顧客データと運行情報を一元管理 | 走行記録の管理 運転日報の自動作成 アルコールチェックの記録 ドライバーの運転評価 | 車両データの一括管理 車両コストの比較 アルコールチェックの点呼 | リアルタイムの車両位置確認 運転日報の自動作成 アルコールチェックの記録 |
| 価格 | 初期費用:無料 費用:要見積もり | 初期費用:デバイス費用のみ 費用:5年間無料 | 初期費用:無料 管理機能:無料 運転手:550円/人 | 費用:要見積もり |
| サポート | ・オンラインマニュアル ・カスタマー窓口 ※有料サポートもあり | ・オンラインマニュアル ・電話での導入サポート | 有料による導入支援 | 要問い合わせ |
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です
おすすめの車両管理システム4選を比較

ここでは、おすすめの車両管理システム4選を紹介します。初期費用の有無や特徴などをわかりやすく解説しているので、参考にしてください。
| 車両管理システム | 特徴 |
|---|---|
| C-Portal | スマホを活用して簡単に車両管理ができる |
| KIBACO | 初期費用無料・管理者機能も永年無料 |
| SmartDrive Fleet | 連携できる外部システムが豊富 |
| Cariot | 3秒ごとに全車両の状況をリアルタイム表示 |
C-Portal

- アルコール検査の管理が楽になる
- 安全運転の意識が向上する
- 日常業務を効率化できる
- 取り付け作業は対応していない
- 無料トライアルはない
| 初期費用 | デバイス費用のみ ※費用は要見積もり |
|---|---|
| 利用費用 | 5年間無料 ※以降は登録デバイス数により変動のため、要見積もり |
| 無料サポート | あり |
| 無料トライアル | なし |
| 運営会社 | 株式会社コムテック |
C-Portalは、業界シェア率No.1の車両管理システムです。※
車両に設置した運転管理装置とスマートフォンをBluetoothで接続し、ドライバーと管理側の連携が簡単に行えます。
運転前に必須の日報作成やアルコールチェックも、スマホと専用のアルコール検知器を使ってスムーズに実施可能です。
これまで手書きだった多くの作業をデジタル化し、クラウド上にデータとして一元管理できる点が大きな魅力でしょう。
関連記事>>C-Portalの評判・口コミ
KIBACO

- 業務の進捗を管理しやすい
- コスト削減がしやすい
- ドライバーの安全意識を高められる
- 保険契約の一元管理ができる
- 契約は10アカウント単位
- 導入支援オプションは有料
- 一部ブラウザに非対応
| 初期費用 | 無料 |
|---|---|
| 利用費用 | 〈管理機能〉 永年無料 〈運転手オプション〉 1アカウント550円 ※申し込みは10アカウント単位 |
| 無料サポート | あり ※有料サポートもあり |
| 無料トライアル | 〈運転手オプション〉 新規申し込み後、3ヵ月間は無料 |
| 運営会社 | キムラユニティー株式会社 |
KIBACOでは、車両データの管理や保険証券フォルダといった管理者側の機能を無料で利用できます。
アルコールチェックや点呼、スマホでの日報作成など、運転手側の機能はオプションとして1アカウントあたり550円で追加可能です。
これらの機能はスマートフォンアプリ「KIBACO Link」を通じて利用できるため、現場との連携もスムーズに行えます。
関連記事>>KIBACOの評判・口コミ
SmartDrive Fleet

- 実績が豊富で安心感がある
- 管理者とドライバーのやり取りを削減できる
- サポート体制が充実している
- OBDには非対応
- 見積もりなしでは料金が不明
- 問い合わせ対応は平日のみ
| 初期費 | 要見積もり |
|---|---|
| 利用費用 | 要見積もり |
| 無料サポート | 要問合せ |
| 無料トライアル | 要問合せ |
| 運営会社 | 株式会社スマートドライブ |
SmartDrive Fleetは、主要な車両管理システムの中で上位のシェア率を占めている信頼性の高いシステムです。※
専用アプリ「Fleet Driver」の活用で、リアルタイムの車両位置確認、運転日報の自動作成、アルコールチェックの記録などがスマートフォンから簡単に行えます。
また「LINE WORKS」や「kintone」などの外部システムとも連携が可能なため、業務の効率化と法令遵守の強化が期待できるでしょう。
関連記事>>SmartDrive Fleetの評判・口コミ
Cariot

- コミュニケーションコストが削減できる
- 業務効率化できる
- 安全運転につながる
- 取り付け依頼は別途費用がかかる
- 個別カスタマイズは別途費用がかかる
| 初期費用 | 無料 |
|---|---|
| 利用費用 | 要見積もり |
| 無料サポート | ・オンラインマニュアル ・カスタマー窓口 ※有料サポートもあり |
| 無料トライアル | 要問合せ |
| 運営会社 | 株式会社キャリオット |
Cariotは、車両位置情報の把握や、運転日報の自動作成、アルコールチェック記録などをクラウド上で実現する車両管理システムです。
車載デバイスや専用スマートフォンアプリを活用して3秒に一度位置情報を取得します。それにより全車両の位置・状態をリアルタイムで可視化でき、効率的な配車指示や、社内外関係者とのスムーズな情報共有が可能になります。
さらに、Salesforceプラットフォームを基盤としているため、顧客データと運行情報を一元管理することができます。
関連記事>>Cariotの評判・口コミ
【無料あり】車両管理システムの料金・費用相場

車両管理システムの費用相場は、初期費用と月額料金の2つが主なコスト対象となります。
初期費用は、車載デバイスの購入や設置にかかり、1台あたり2万~10万円程度が一般的です。
月額料金は、システムの機能やデバイスの種類によって異なり、1,000~5,000円程度が相場です。
高度な機能を搭載したシステムや、カスタマイズ可能なプランでは、さらに費用がかかる場合があります。
なかには、初期費用無料や特定の条件下で一部機能を無料で提供しているサービスもあり、導入のハードルは低くなりつつあります。
導入コストと業務効率化によるコスト削減効果を比較し、自社にとって最適なシステムを選びましょう。
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です
車両管理システムを導入時の6つのメリット
車両管理システムの導入で、従来では把握しきれなかった部分が可視化され、ドライバーをより高いレベルで支援しやすくなります。
また、これまで手作業で行っていた事務作業を自動化すれば、業務時間の短縮にもつながるでしょう。
ここでは車両管理システムを導入する6つのメリットを解説します。
導入を検討中の方は参考にしてください。
管理業務の自動化や効率化が図れる
車両管理システムの導入により、車両やドライバーの管理業務を自動化・効率化できます。管理する車両や在籍するドライバーが多いと、それぞれの情報を正しく把握するのも難しく、業務の負担も大きくなります。
車両管理システムは、このような統合できていないデータや業務を1カ所に集約し、できるだけ少ない労力で日々の仕事をこなすサポート役として最適です。
費用を削減できる
車両管理システムを導入すれば、運転状況の把握や車両の状態を常に把握できます。
これにより、道路状況による最短ルートの案内や素早い修理・点検が可能になり、結果的にさまざまな面にかかるコスト削減が可能です。
たとえば、常日頃から最短距離での運転ができれば走行距離も減少し、燃料代をカットできます。
また管理者による運転支援や、点検による車両状態の維持は交通事故のリスクを減らし、保険料の削減につなげられるでしょう。
他にも、車両ごとの稼働状況を正しく把握すると、自社にとって余分な車両の存在が浮かび上がります。不要な車両を売却したり、リース契約を解除したりすれば、車1台分の維持費を節約できます。
事故予防やコンプライアンス遵守に繋がる
交通事故を未然に防ぎ、ドライバーのコンプライアンス遵守につなげられるのも、車両管理システムの魅力的なポイントです。
集計データからドライバーごとの運転傾向をチェックし、定期的な運転指導によって安全への意識を常に高く持ってもらいやすくなります。
またシステムによっては、運転前のアルコール検査を実施し、結果を送信しないと車両を解錠できない仕組みとなっています。
このように、システムの制御機能を使って、条件を満たさないと運転できない環境を構築できるのも、車両管理システムの導入メリットです。
業務全体の生産性を高められる
車両管理システムを導入すると、管理側とドライバー双方の生産性が高まります。
無駄のない運転が実現できれば、ドライバーはもちろん、管理側も早く業務を終えられるでしょう。
たとえば、マップで詳細な道路状況を把握しながらドライバーを追跡できると、最短ルートを提案しやすいです。
他にも、状況に応じて車両を向かわせたり、目的地までの到着時間を短縮したりできれば、さらなる生産性の向上を目指せます。
また、アプリとシステムで集計したデータを用いれば、日報作成や管理も自動化でき、煩雑な事務作業にかける時間を削減できるでしょう。
従業員のパフォーマンスが高まる
車両管理システムにより、これまで可視化できなかったドライバーの働きぶりが明確になります。
走行距離、燃費効率、配達時間などの詳細な分析で客観的に評価できるため、個々のドライバーの強みや改善点を特定しやすくなるからです。
データに基づいた的確なフィードバックやトレーニングを行えば、ドライビングスキルや業務パフォーマンスは高い確率で向上します。
車両管理システムでスキルアップできる環境を整えれば、ドライバーのモチベーションも高めやすくなるでしょう。
長時間労働を解消しやすくなる
車両管理システムの導入は、業務プロセス全体の効率化をもたらします。
管理業務や事務作業を効率化すると、バックアップに割ける時間が増え、ドライバーには本来の業務である運転や配達により集中してもらいやすくなります。
運転時間の短縮によって他業務にも迅速に取り掛かりやすくなれば、ドライバーの労働時間も削減されるでしょう。
車両管理システムの導入で、ワークライフバランスの改善や過労運転による交通事故リスクを下げることも可能です。
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です
車両管理システムを導入時のデメリット

さまざまな業務を効率化し、管理側とドライバーの双方が働きやすい環境作りができる車両管理システムですが、決して懸念点がない訳ではありません。
ここでは車両管理システムを導入するデメリットを解説します。
ひとつずつ確認をしましょう。
運転手がストレスを感じやすい
車両管理システムは、GPSや管理デバイスによって常に追跡し続けることで、業務効率化を叶えるバックアップが可能です。
しかし、ドライバーによっては「ずっと見られている気がする」「監視されているようで落ち着かない」といったように、業務中のストレスが増大する恐れもあります。
システムで業務課題の解決や改善を図るには、ドライバーを追跡してあらゆるデータを集計しなければなりません。
車両管理システムの導入時は、決して監視目的で追跡しているのではなく、「ドライバー自身の安全や正しい評価のために実施している」ということを伝え、理解を得る必要があります。
新しいシステムを導入する際は、現場への配慮も大切です。
定着までに時間がかかる
車両管理システムの導入後、定着するまでに時間がかかる場合があります。その主な要因は、従業員の理解不足や運用ルールの未整備です。
対策としては、現場の声を反映した運用ルールを策定し、適切なトレーニングを実施することです。
システム導入時にサポート担当者へ「システム操作に関する説明会を実施してもらえないか」などの相談を持ち掛けてみるのも良いでしょう。
企業担当者は、導入後のフォローアップを徹底し、新たなシステムの定着を促進していく努力が必要となることを視野に入れておきましょう。
他社への移行が困難
一部の車両管理システムでは、システム専用デバイスを車両に設置する必要があります。
特定デバイスへの依存は、他社システムへ移行したい場合に、新たなデバイス設置の必要があるため、費用がかさみやすいです。
また、移行時に一から構築する必要があり、身動きが取りづらくなることもあるでしょう。
このように、時間やコストがネックとなって乗り換えができない「ベンダーロックイン」に陥る危険性があります。
車両管理システムの導入で、今後の選択肢が狭くなってしまう可能性があることを視野にいれておきましょう。
車両管理システムとは

車両管理システムとは、企業の車両を効率的に管理するためのシステムです。
GPSやセンサーを活用し、車両の位置情報や運行状況、燃費、メンテナンス情報などをリアルタイムで把握できます。これにより、効率的な運行ルートの提案やコスト削減、安全運転の促進が可能です。
また、ドライバーの運転データを分析し、急ブレーキや速度超過などを可視化できるため、安全管理も行えます。車両管理システムは、企業の業務効率向上に役立つ重要なツールのひとつです。
車両管理システムの主な5つの種類

ここでは、車両管理システムの主な5つの種類について解説します。
自社が抱える課題やコストにより、選ぶ種類はさまざまです。ぜひ参考にしてください。
OBD-Ⅱポート型
OBD-IIポート型は、車両のOBD-IIにデバイスを差し込むだけで利用できる手軽なタイプです。
取り付け工事が不要で、スピード・燃料消費量・エンジン回転数などのデータをリアルタイムで取得できます。また、デバイスの着脱が容易なため、複数の車両での使い回しが可能です。
OBD-IIは運転席周辺に設置されるため、ドライバーの視界や操作を妨げる心配がないのもメリットと言えるでしょう。低コストで導入しやすいため、多くの企業で採用されています。
シガーソケット型
シガーソケット型は、車両のシガーソケットにデバイスを差し込むだけで使用できる手軽なタイプです。配線工事が不要なため、導入コストを抑えられるのがメリットです。
GPSやモバイル通信機能を備え、リアルタイムでの位置情報や走行データの取得ができます。デバイスの着脱が容易で、複数の車両で運用しやすい点も特徴です。
ただし、シガーソケットの位置によっては通信感度が低下する可能性があります。
アプリ型
アプリ型は、スマートフォンやタブレットに専用アプリをインストールして利用するタイプです。
専用の車載器が不要なため、導入コストを抑えやすく、手軽に運用できるのが特徴です。直感的な操作が可能で、GPSによる位置情報の取得や運行記録の管理ができます。
ただし、バッテリー切れやGPS設定の影響を受けやすく、取得データが限定される場合もあります。コストと機能のバランスを考慮し、導入を検討することが重要です。
ドライブレコーダー型
ドライブレコーダー型は、車両の前方や車内の映像を記録し、安全運転管理や事故時の証拠保全に活用できるタイプです。
急ブレーキや急加速などの危険運転を検知し、ドライバーへリアルタイムで警告できる機能を備えたものもあります。AI搭載モデルでは、注意散漫運転の検知や顔認証によるドライバー識別も可能です。
通信機能を持つ機種では、リアルタイムでの位置情報や映像確認ができ、安全性の向上と効率的な運行管理が期待できるでしょう。
デジタルタコグラフ搭載型
デジタルタコグラフ搭載型は、車両の運行データをデジタル形式で記録・管理できるタイプです。
速度・走行距離・エンジン回転数・急加速・アイドリング時間などの詳細なデータを記録し、安全運転管理を強化できます。
法令遵守の徹底にも役立ち、記録の改ざんが困難なため、信頼性の高い運行データを管理できます。
車載機の設置が必要のため、導入コストも高くなりますが、ドライバーの労務管理などに重点を置きたい場合には最適でしょう。
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です
車両管理システムの8つの機能

ここでは、車両管理システムに搭載された8つのメイン機能を解説します。
ひとつずつ確認しましょう。
【車両予約】車両の空き状況をチェック
社用車の利用に事前予約を必要としている企業は多いのではないでしょうか。紙やホワイトボードでの車両予約は、記入ミスによるダブルブッキングや、無許可での社用車利用の原因になりかねません。
しかし、車両管理システムの車両予約機能なら、システムやアプリで社用車の予約や変更ができます。
予約情報はデータでわかりやすく管理されることから、見間違い・書き間違いによる管理ミスも防げるでしょう。
また、ネット接続があれば外出先でも予約・変更ができるため、効率良く働くサポート役にもなります。
【車両走行記録】GPSで車両の位置情報をチェック
車両走行記録機能では、GPSを用いて車両の位置情報をほぼリアルタイムでチェックできる点がポイントです。
Googleマップや独自マップに走行中の社用車が表示されるため、交通状況や業務状況を考慮して素早く指示を出せます。
配送車両への最短ルートの指示出しにも活用できるため、業務効率の向上にもつながるでしょう。車両ごとの運転状況を把握できれば、配送時刻の予定も立てやすくなります。
万が一配送が遅れそうな場合は、管理者側から取引先に事前連絡もできるなど、取引を円滑に進めるための手段としても活用できます。
【アルコールチェック】運転手のアルコール度数をチェック
2023年12月1日から、社用車や営業車などの白ナンバーもアルコール検知器によるドライバーの酒気帯び有無の確認が義務付けられました。
車両管理システムでは、運転前後に必ず実施すべきアルコールチェックと、その結果の管理も効率的に行えます。
特に、システム用の専用検知器を利用する場合は測定結果が自動的にアップロードされるため、手入力の必要や書面による管理の手間が省けます。
また、未測定のドライバーにはシステムが通知を発信するため、未測定のまま業務に移ることもありません。
アルコールチェックと同じく義務付けられているのが「測定結果の1年間の保管」です。
紙での保管は紛失リスクを高めますが、システムを導入すれば結果をデータとして保管でき、さらにエクセル形式で出力もできるため、より保管しやすくなります。
【免許・車検証期限管理】免許・車検失効前に通知
免許証期限管理機能は、ドライバーや車両の免許・車検期限が迫ってきた際に通知する機能です。
会社に大人数のドライバーが在籍する場合、一人ひとりの免許期限や、一台ごとの車検期限を把握・管理する作業は大きな負担になるでしょう。
しかし、この機能にあらかじめ免許期限や車検期限を登録しておけば、通知で更新漏れを防げるうえに、ドライバーの車両予約や利用に自動的に制限もかけられます。
無免許運転による摘発や車両の不具合による事故を起こさないために役立つ機能です。
【安全運転支援】運転手の危険運転を防止
車両管理システムは、安全運転管理者の業務や指導をサポートする機能です。ドライバーの危険運転や居眠り運転の検知、運転傾向の見える化を行い、事故を防ぎます。
急ブレーキや急ハンドルを行った場合は管理者にリアルタイム通知が発信されるため、スマホなどを介して状況把握や注意を行えます。
ドライブレコーダー型機器を搭載している場合は、ヒヤリハットの瞬間を映像でチェックできるため、ドライバーの運転意識向上にも活かせるでしょう。
また、交通事故が多い場所をマークしておく機能を活用すれば、業務前のドライバーに効果的な注意喚起も可能です。
【日報のデジタル化】日々の報告をスムーズに
必要ながら手間も大きい「日報作成」をデジタル化できるのも、車両管理システムの魅力です。車両管理システムを導入すれば、ドライバーはスマホアプリからどこからでも日報作成が行えます。
会社に戻ってから作成する必要がなくなるため、空き時間を活用できたり、リアルタイムでの入力によって情報の正確性が増したりと、さまざまなメリットがあります。
また、日報に記載が必要なアルコールチェックの測定結果や走行距離はシステムが自動的に集計して日報に反映するため、作成時間の削減も可能です。
日報データはクラウドで保管できるので、これまで紙日報を利用していた企業にとってはペーパーレス化によるコスト削減などの効果も期待できます。
【デジタルキー機能】スマホで施錠可能
車両管理システムのデジタルキー機能を活用すれば、車両ごとに異なる鍵を貸し出したり、返却したりする手間を省けます。
専用アプリなどを搭載したスマホで車両を解錠・施錠できるので、鍵を渡すプロセスをなくせるのです。物理キーを携帯する必要がないので、紛失による作り直しの心配もいりません。
ちなみに、類似機能である「スマートキー」も車に近づく、もしくは触れることで解錠・施錠できますが、物理キーは持ち運ぶ必要があります。
デジタルキー機能は、実質的に「鍵を使わず車に乗ること」を実現する機能とも言えるでしょう。
【稼働状況集計機能】車両の稼働状況を管理
稼働状況集計機能では、それぞれの車両がどのくらい使われているか確認できます。
「Aの車は誰に多く使われているか?」「車両予約されたのに結局使われていない」といった稼働状況を集計データをもとに確かめることで、車両の有効活用を促進できます。
また、指定期間内の走行距離や走行時間もチェックできるため、整備や点検の目安としても利用可能です。
GPSや管理デバイスを用いて正確な稼働状況を把握し、ドライバーの利用状況や車両の異変などに気づけるのが稼働状況集計機能の強みでしょう。
車両管理システム選びにお悩みの方へ
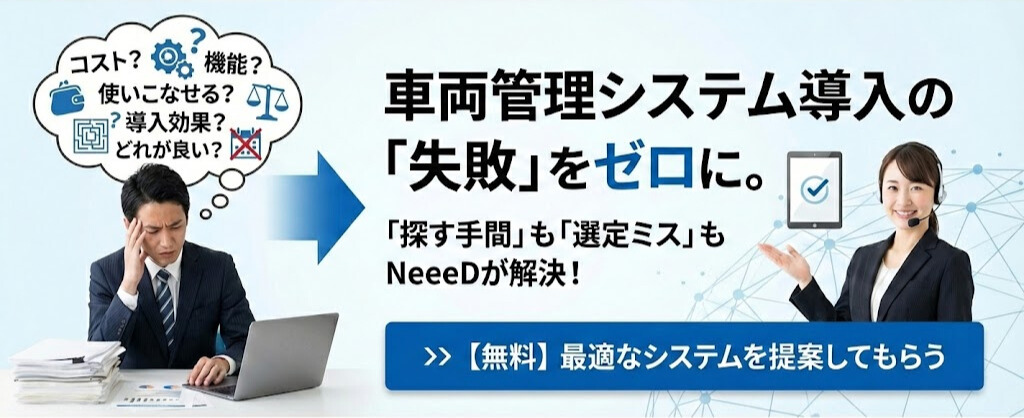
「多機能すぎて使いこなせない」「コストが見合わない」といった失敗を防ぎませんか?
NeeeDは、貴社の運用ルールや課題を丁寧にヒアリングし、数ある製品の中から「本当に使いこなせる車両管理システム」を中立的な立場で厳選します。
比較検討の時間を大幅にカットしたいご担当者様は、ぜひ一度ご活用ください。
まとめ
車両管理システムは、その性質上ドライバーのすぐ近くにデバイスを設置して常に運転状況を把握する必要があります。
ドライバーによっては仕事がしづらくなり、モチベーションの低下や退職にもつながりかねません。
管理側にメリットがあってもドライバーの理解が得られないとスムーズな導入は難しいため、無料お試しプランなどで使用感を確かめてから本格検討すると良いでしょう。
うまく利用できれば可視化されにくいドライバーの頑張りがデータ化でき、スキルアップやさらなる安全運転を叶える味方となります。
「どの車両管理システムが自社に合うかわからない」という方は、ぜひNeeeDへご相談ください。
完全無料で貴社に最適な車両管理システムをご提案いたします。
\最短当日に紹介可能!/
※無料でご利用可能です