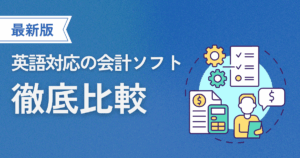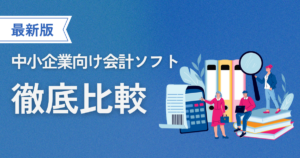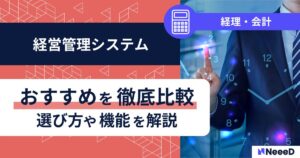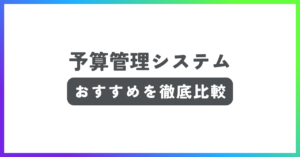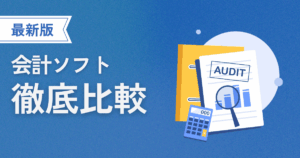【26年1月最新】電子帳簿保存システムおすすめ3選を比較!選び方や導入のメリットも解説
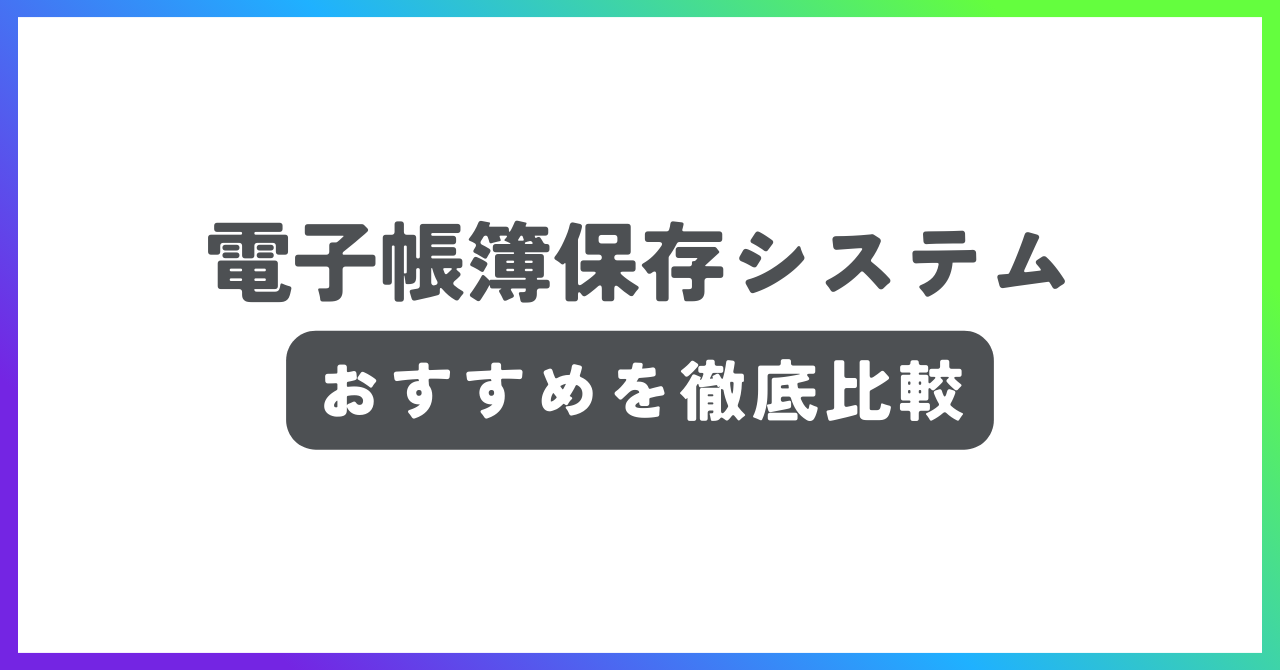
2022年に改正された電子帳簿保存法により、2024年1月1日から電子取引の記録を電子データで保存することが義務化されました。その結果、法人や個人事業主は電子帳簿保存システムを導入することが急務になっています。
しかし、「その製品を選べば良いか分からない」「比較検討する際の基準が分からない」という人も多いでしょう。
そこで当記事では、おすすめの電子帳簿保存システムを紹介します。電子帳簿保存システムの選び方や導入するメリット・注意点などについても解説しているので、当記事を読めば自社に合った電子帳簿保存システムを選べるようになります。電子帳簿保存システムの導入を検討している方はぜひご覧ください。
電子帳簿保存システムおすすめ3選を比較

電子帳簿保存システムのおすすめを3つ紹介します。それぞれの製品の特長をまとめると以下の通りです。
| おすすめの電子帳簿保存システム | 特徴 |
|---|---|
| invox電子帳簿保存 | 国税関係書類の保存が効率的に可能 |
| マネーフォワード クラウドインボイス | 幅広い業務に対応可能な請求書発行システム |
| 経費BANK | 中小企業でも導入しやすい経費精算システム |
それぞれ対応している業務範囲なども異なるので、自社に合ったものを選ぶことが重要です。それぞれの製品について詳しく見ていきましょう。
invox電子帳簿保存
| 料金プラン | ミニマム:2,178円/月 ベーシック:10,780円/月 プロフェッショナル:32,780円/月 |
|---|---|
| 機能 | AI OCR セルフ入力 オペレーター入力 ワークフロー機能など |
| タイプ | 電子帳簿保存法の対応に特化したタイプ |
| 導入実績 | パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 株式会社レコチョク 株式会社アソビバなど |
| 会社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS |
invox電子帳簿保存は株式会社invoxが提供する電子帳簿保存システムです。国税関係書類の保存に特化しており、AIを搭載したOCR機能によって自動で高精度なデータ化を行えます。データ化した国税関係書類は、電子帳簿保存法の法令に遵守した検索要件を満たすように記録されるため、書類の管理業務の効率化が可能です。
また、書類の申請・承認に関するワークフロー機能が搭載されているため、大規模な企業でも円滑に承認・申請のフローを行えます。データ情報の手入力も可能など、イレギュラーにも対応しやすい電子帳簿保存システムです。
マネーフォワード クラウドインボイス
| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 機能 | 帳票成形機能 PDFファイルの分割・読み取り機能 帳票送付機能 ワークフロー機能 API連携機能など |
| タイプ | 請求書の保存に特化したタイプ |
| 導入実績 | 株式会社学情 天藤製薬株式会社 株式会社ガイアドリームなど |
| 会社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
マネーフォワード クラウドインボイスは株式会社マネーフォワードが提供する請求書発行システムです。紙媒体や電子データで送られてきた請求書を一括で受領でき、AIを搭載したOCR機能やオペレーター入力で自動的かつ高精度にデータ化できます。
さらに、CSVまたはPDFの帳票データをアップロードすれば、自動で振り分けが可能です。
また、見積書や納品書などの保存も可能なので、対応できる業務範囲が広いのも特徴です。既存システムと連携方式も多様で、導入がしやすいシステムといえるでしょう。
経費BANK

| 料金プラン | 3,000円~/月 |
|---|---|
| 機能 | AI-OCR 交通費精算機能 出張旅費精算機能 クレジットカード連携機能 ログ情報管理機能など |
| タイプ | 領収書の保存に特化したタイプ |
| 導入実績 | フォントワークス株式会社 株式会社西新宿ホテルアンドリゾート 株式会社網屋など |
| 会社所在地 | 〒106-6013 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー |
経費BANKはSBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供する経費精算システムです。中小企業をターゲットにしており、初期費用0円、月額利用料3,000円からとリーズナブルな価格に設定されています。
低価格ながらAIを搭載したOCR機能を搭載しており、画像情報の読み取りでエラーが頻発する心配もありません。対応範囲は経費精算業務に限られますが、ICカードの読み取りが可能など、痒い所に手が届くシステムとなっています。
電子帳簿保存システムの選び方

電子帳簿保存システムを選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
国税庁関係書類を一元管理できるか
まずは、国税庁の関係書類を一元管理できるかチェックしましょう。電子保存できる書類の範囲は、電子帳簿保存システムごとに異なります。例えば請求書の保存に特化したタイプであれば、請求書のみにしか対応していないことも少なくありません。
気になるシステムがどの書類に対応しているか、事前に必ずチェックしましょう。 ペーパーレス化による業務効率化をより効果的に行いたいのであれば、国税庁関係書類を一元管理できるものを選ぶのがおすすめです。
対応可能な書類の範囲は広いか
電子帳簿保存システムを選ぶ際には、自社で扱う電子データの形式に対応しているかも確認しましょう。電子データはPDF形式で管理されることが多いため、電子帳簿保存システムはPDFに対応していることが一般的です。
しかし、中にはExcelやWordなど、別の形式に対応しているものもあります。将来的に別の形式の電子データを取り扱うことも考えられるので、電子帳簿保存システムを選ぶ際には対応しているデータ形式にも注目しましょう。
タイムスタンプ機能があるか
スキャンしたデータにタイムスタンプを付与できるかも、確認したいポイントです。タイムスタンプとは書類に時刻情報を付与する機能で、書類の真実性を確保するために必要になります。
タイムスタンプ機能がない製品を導入した場合、万が一製品の切り替えが必要になった際に電子データを移行できないトラブルが発生するリスクがあります。将来的なリスクヘッジのためにも、可能な限りタイムスタンプのある製品を選ぶのがおすすめです。
請求書を集約して一元管理できるか
請求書の保存に対応した電子帳簿保存システムを導入する場合は、受領ページとは別に請求書を集約して管理できる機能があるか確認しましょう。請求書を一元管理できる機能があれば、書類管理にかかる工数を削減することが可能です。
特に請求書を一覧で確認でき、検索も可能な製品を導入すれば、電子帳簿保存法の要件である可視性の確保につながります。製品によっては取引ごとに関連する書類を紐づけて管理できるものもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
JIIMA認証を満たしているか
電子帳簿保存システムを導入する際には、「JIIMA認証」を満たしているかも確認しましょう。JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が付与している認証制度のことで、電子帳簿保存法の要件を満たす製品に付与されます。
JIIMA認証を受けている製品を導入すれば、電子帳簿保存法に関する知見がなくても法令に遵守した税務処理を行うことが可能です。結果的に税務処理業務の属人化を防ぐことも可能なので、電子帳簿保存システムを選ぶ際には、JIIMA認証を受けているか確認しておきましょう。
OCR機能が搭載されているか
OCR機能の有無も電子帳簿保存システムを選ぶ上での重要なポイントです。OCR機能とは電子データに記載されている情報を読み取る機能で、利用すれば自動的にデータ内の文字情報を取得できます。
OCR機能の性能は製品によって差があり、精度が低いものを導入してしまうとエラーが発生することも珍しくありません。エラーによって工数が増えるリスクを抑えたいのであれば、OCR機能の性能が高い電子帳簿保存システムを選びましょう。
コストパフォーマンスがよいか
電子帳簿保存システムを選ぶ際には、コストパフォーマンスも重要です。電子帳簿保存システムは製品によって料金体系に違いがあります。一見初期費用が安くても、必要な機能をオプションとして追加した結果、割高になることも少なくありません。
電子帳簿保存システムを比較する際には、それぞれの機能をよく確認した上で、機能に見合った料金になっているか確認しましょう。また、電子帳簿保存システムは基本的に長期運用するのが前提なので、ランニングコストが自社のキャッシュフローを圧迫しないかも確認することが重要です。
既存システムと連携できるか
既存システムと連携できるかも、電子帳簿保存システムを選ぶ際のポイントです。電子帳簿保存システムは会計システムなどと連携することで、より税務処理業務を効率化できます。一方で、導入した製品が社内の既存のシステムに対応していなかった場合、システム連携による恩恵を受けることができません。
電子帳簿保存システムを選ぶ際には、自社の既存のシステムと連携が可能か、あらかじめ確認しましょう。特に既存システムがWeb APIに対応している場合は、Web APIで連携できる製品を選ぶことで、シームレスなデータ管理が行えます。
簡単に操作できるか
操作性も電子帳簿保存システムを選ぶ際に重要になるポイントです。電子帳簿保存システムに限らず、社内に新しいシステムを導入する時は担当者が操作を理解するまで時間がかかります。仮にシステムのUIが見づらかったり、操作方法が複雑だった場合、円滑に運用できるまで時間がかかるだけでなく、担当者のストレスにもなりかねません。
電子帳簿保存システムを選ぶ際には、可能な限り操作方法が簡単なものを選ぶようにしましょう。既存のシステムと操作性が類似しているものを選べば、無用な時間をかけずにスムーズな運用が可能になるでしょう。
管理・保存できる書類の数が多いか
電子帳簿保存システムを選ぶ際には、保存できる容量も重要になります。製品によっては容量に制限があり、保存できる書類の件数に上限があることも少なくありません。また、データ1件あたりの容量が制限されている場合もあります。
特に規模の大きい企業の場合、管理する書類も膨大になるため、容量の確認は重要です。加えて、業務に関わる人数が多い場合は、アカウント数に制限がないかも確認しておきましょう。
必要なセキュリティ対策が施されているか
最後にシステム自体のセキュリティ面も確認しましょう。電子帳簿保存システムでは会社の経理情報や決算情報などの重要な情報を扱うため、セキュリティには特に注意する必要があります。電子帳簿保存システムで採用される主なセキュリティ機能は以下の通りです。
- アクセス制御機能
- ログ管理機能
- データ通信暗号化機能
アクセス制御機能やログ管理機能が搭載されていれば、物理的にシステムにアクセスして情報を抜き取る行為を防止できます。また、データ通信暗号化機能があれば、データの送受信の安全性を確保することが可能です。電子帳簿保存システムを選ぶ際には、以上のような機能を搭載しているものを選ぶことをお勧めします。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、決済に関連する書類や帳簿などを電子データで保存する際の取り扱いについて定めた法律です。仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係帳簿を保存する義務のある事業者すべてが対象で、区分ごとに定められた要件に従って書類を保存する必要があります。
2023年12月31日までは電子取引のデータ保存への対応に猶予期間が設けられていましたが、2024年1月1日に猶予期間が終了しています。そのため、2024年1月1日以降に受け取った電子取引の記録は、先述の要件を満たした状態で電子データとして保存しなければいけません。
保存期間は法人と個人で異なるので注意が必要です。それぞれの保存期間は以下のようになっています。
- 法人の場合:7年または10年
- 個人事業主の場合:5または7年
なお、給与所得者が副業している場合でも、前々年分の収入が300万円を超える場合は電子データを上記の期間保存する必要があります。
電子帳簿保存法の3つの区分
電子帳簿保存法では電子データが3つの区分で分類されています。それぞれの区分と該当する書類は以下の通りです。
| 区分 | 該当する書類 |
|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 仕訳帳総勘定元帳現金出納帳貸借対照表損益計算書請求書領収書発注書など |
| スキャナ保存 | 紙で受け取ったのちにスキャンや撮影によって電子データに変換した領収書や請求書など |
| 電子取引データ保存 | 電子取引で受領した書類や電子明細 |
まず、「電子帳簿等保存」は仕訳帳や総勘定元帳など、自社の会計ソフトなどで作成した帳簿や書類、請求書などが該当します。要件としては以下のようなものがあります。
- 内容の変更や削除を行った履歴が確認できること
- 関連書類との紐づけ
- 検索要件の付与
- システム関係書類等の備え付け
- 出力が迅速に行えるマニュアルの備え付け
次に「スキャナ保存」です。スキャナ保存には紙で受け取った請求書や領収書をスキャンや撮影などで電子データ化したものが区分されます。スキャナ保存に区分されるデータは検索要件の付与の他、改ざんされていないことを証明するため、タイプスタンプの付与などが必要です。また、解像度の要件なども細かく設定されているので、詳しくは国税庁の資料をご覧ください。※1
最後に「電子取引データ保存」です。電子取引データ保存には電子取引で受領した書類や電子明細が区分され、以下のような要件が適用されます。
- 改ざん防止のための措置をとること
- 検索要件を付与すること
- ディスプレイやプリンタ等を備え付けること
ただし、電子取引データ保存に区分された資料については、一定の条件を満たすことで要件が不要になります。※2
電子帳簿保存法の対象書類
電子帳簿保存法では、先ほど説明した3つの区分に沿ったものが保存の対象書類となります。電子データで取引や税務関係書類の保存を行う場合、基本的にすべてが電子帳簿保存法の対象となると考えておきましょう。
なお、電子データとしての保存が義務付けられているのは、あくまでもコンピュータを用いて作られた書類です。紙で受け取った書類や紙で作成した書類については、スキャナ保存しない限りは従来通りの方法で保存しても問題ありません。
電子帳簿保存法の対応条件
電子帳簿保存法においては、対象の書類が「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの条件を満たす必要があります。
真実性の確保とは、改ざんや削除が行われない状態を指します。具体的には、タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の保存、相互けん制が働く運用体制の整備などが求められます。信頼性の高いデータ管理を行うことで、電子データが紙の原本と同等の証拠力を持つことが可能です。
可視性の確保とは、保存したデータを容易に確認できる状態を指します。日付や金額、取引先名などを検索できる機能、帳簿と証憑を相互に確認できる仕組み、見読可能な画面表示や印刷が必要です。必要なときに速やかに参照できる環境を整えることで、税務調査にも対応しやすくなります。
システム導入の際は、上記両方の条件を満たしたものであるか必ずチェックしましょう。
電子帳簿保存システムとは
電子帳簿保存システムとは、請求書や領収書を電子的に保存するためのシステムです。請求書や領収書は紙面で管理すると紛失のリスクがある上、物理的にかさばるので保管場所に困ることも少なくありません。
電子帳簿保存システムを利用すれば、PC上で書類を管理できるため、紙のデメリットを回避することが可能です。また、確認のたびに保管場所で紙の資料を探す手間がなくなるので、業務効率化にもつながります。
2022年に改正された電子帳簿保存法の影響で、2024年1月1日以降、すべての事業者に電子取引の電子データ保存が義務付けられました。結果、電子帳簿保存法の要件を満たした電子帳簿保存システムの必要性が増しています。
電子帳簿保存システムの種類
電子帳簿保存システムは、大きく3タイプに分けられます。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 電子帳簿保存法の対応に特化したタイプ | 電子帳簿保存法の法令を遵守して書類を保存可能 |
| 請求書の保存に特化したタイプ | OCR機能で請求書の電子保存を効率化 |
| 領収書の保存に特化したタイプ | 領収書の保存だけでなく、経費精算業務の効率化が可能 |
基本的には電子帳簿保存法の対応に特化したタイプをベースに、製品によってOCR機能や経費精算機能が追加されていることが多いです。運用目的に合わない電子帳簿保存システムを導入してしまうと、業務効率化につながらないおそれがあるので注意しましょう。
電子帳簿保存システムで使える機能
電子帳簿保存システムで使える機能には、以下のようなものがあります。
基本的には、電子帳簿保存法の要件を満たすための機能が利用可能です。それぞれ詳しく解説します。
スキャン機能
続いてスキャン機能です。スキャン機能は「スキャナ保存」に区分される紙の書類を要件を満たす基準で電子データ化する際に必要な機能となります。スキャナ保存に区分される書類は、紙のまま保存するのであれば電子保存法に則って保存する必要がありません。
しかし、電子データとして保存することで保管場所の確保が必要なくなる上、検索も可能になるので、業務効率化につながります。
OCR機能
OCR機能とは、スキャンしたデータの文字情報を読み取る機能です。通常、スキャンしたデータは画像形式で保存することになるので、文字情報の取得ができません。そのため、データに関する情報を手入力する必要があります。
しかし、電子帳簿保存システムはOCR機能によって画像の文字情報を自動的に取得してくれるので、情報を手入力する必要がありません。結果的に入力のための工数を削減でき、入力ミスも防止できます。
電子帳簿保存システムによってはAIによって認識精度を向上させているものもあり、認識結果をもとに仕分けなども行ってくれます。
タイムスタンプ機能
電子帳簿保存システムには、タイムスタンプをはじめとした書類の真実性を確保するための機能が備わっています。タイムスタンプは書類に時刻情報を付与することでデータの改ざんを防ぐ機能です。タイムスタンプの自動付与機能がある製品を選べば、付与し忘れるミスを予防できます。
また、真実性の確保のためには、タイムスタンプだけでなく、訂正・削除の履歴を残さなければいけません。そのため、多くの電子帳簿保存システムには、操作履歴を確認できる機能も備わっています。
検索機能
検索機能は、各電子データを電子帳簿保存法の要件に則って検索できる機能です。電子帳簿保存法に則るためには、以下のような項目での検索が可能である必要があります。
- 取引年月日をはじめとした日付
- 取引金額
- 取引先
上記のうち、日付や取引金額は原則として範囲を指定して検索できなければいけません。また、2つ以上の項目を組み合わせて検索できることも、原則的な要件となっています。電子帳簿保存システムでは基本的に、以上のような要件を満たす検索機能が搭載されていることが多いです。
電子帳簿保存システムを使うメリット

電子帳簿保存システムを使うメリットは以下の通りです。
電子取引データの保存義務化により、導入の必要性が増している電子帳簿保存システムですが、法律の要件を満たす用途以外にもさまざまなメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
アナログ作業が減り業務効率化につながる
電子帳簿保存システムを導入すると、紙の請求書や領収書をファイリングする作業や、仕訳入力の転記作業が不要になります。さらにデータは自動で保存・整理されるため、検索機能を活用すれば必要な情報をすぐに確認できます。
紙の保管や手作業による入力に費やしていた時間が減れば業務時間が短縮され、担当者はより付加価値の高い業務に集中することが可能です。
書類保管のコストを減らせる
書類保管に必要なコストを減らせる点もメリットです。国税関係帳簿や請求書などは最長10年間の保管が必要になるため、場所を取りがちです。しかし電子帳簿保存システムがあれば、物理的な保管場所を確保する必要がなくなるうえ、書類破棄の費用も不要となります。
また、システム導入により紛失リスクも減少します。特に領収書やレシートはサイズが小さいこともあり、間違えて捨ててしまうことも少なくありません。
一方、 PC上で書類を管理できるようになれば、上記のような理由で紛失するリスクを抑えられます。特にクラウド上にデータを保存している製品であれば、災害に遭った場合でも別のPCでデータを管理できるため、よりリスクの少ない書類管理が可能です。
書類の改ざん・差し替えのリスクが防止できる
電子帳簿保存システムの導入は、書類の改ざんや差し替えの対策になります。電子帳簿保存システムには書類の真実性を確保するために、タイムスタンプの付与機能や履歴の確認機能などが備えられています。
そのため、従業員がデータの改ざんや差し替えを行ったとしても隠蔽が困難です。結果的にデータの真実性が確保され、健全な管理体制を構築できます。
また電子帳簿保存システムを導入すればシステムを利用するだけで法令を遵守できるため、専門知識がない従業員でもミスの少ない税務処理が可能です。
セキュリティ強化に役立つ
電子帳簿保存システムの導入は、セキュリティの強化にもつながります。紙で書類を保管する場合、従業員やオフィスを出入りする第三者によって書類を持ち出されるリスクがあります。
対して、電子帳簿保存システムでデータを管理している場合は、上記のようなリスクがありません。代わりにネットを介した情報漏洩のリスクが懸念されますが、閲覧制限をはじめとしたセキュリティ機能が充実しているものが多いので、紙で管理するよりも情報漏洩のリスクを低減できます。
電子帳簿システムを使う際の注意点

電子帳簿保存システムを利用する際には、以下の点に注意しましょう。
特に、業務フローの見直しが発生する可能性があることはあらかじめ把握しておく必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
システム導入にコストがかかる
まずはシステムの導入にコストがかかることです。一般的に、電子帳簿保存システムの導入には初期費用がかかります。また、運用時にも月額費用がかかることが多いです。初期費用が安い製品でも、月額費用が割高なことがあるので、双方の金額をよく確認することが重要です。
同じ製品でも利用する機能や対応範囲によって金額が変動することも多いので、電子帳簿保存システムを導入する際は、導入を検討している製品の料金体系をあらかじめ把握しておきましょう。
システム運用に慣れるまで時間がかかる
電子帳簿保存システムを導入すれば、専門知識がなくても法令に遵守した電子データの保存が可能になります。しかし、システムの操作方法については担当者が新たに覚える必要があるので、慣れるまでは業務効率が落ちることも少なくありません。
また、将来的に業務の引継ぎが発生することを考えると、運用マニュアルの作成なども必要になります。結果として担当者の業務が一時的に増えるので、業務量に合わせてスケジュールの調整などが必要です。
システム連携を前提とした業務フローの見直しが求められる
電子帳簿保存システムは他のシステムと連携することで、より業務効率を向上することが可能です。しかし、システム連携を行った場合、電子帳簿保存システムを運用する従業員だけでなく、既存のシステムを利用している従業員にも業務フローの見直しが求められる可能性があります。
該当する従業員は業務フローの見直しによって大きなストレスがかかるので、可能な限り作業工数が少なく、業務への影響が少ないものを選ぶことが重要です。
電子データにも消失リスクがある
電子データは紙より安全と思われがちですが、サーバ障害や誤操作、ウイルス感染による消失リスクが存在します。法定保存期間を満たすため、バックアップ体制を整えておきましょう。
クラウド保存や外部ストレージへの定期的な複製を行うことで、万一のトラブル発生時にも迅速に復旧できます。消失リスクを軽視せず、堅実なデータ管理を実現することが安定運用の前提条件です。
電子帳簿システムに関するよくある質問
ここからは、電子帳簿システムに関する次のよくある質問に回答します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人事業主でも電子帳簿保存法への対応は必要?
電子帳簿保存法は法人だけでなく個人事業主も対象です。青色申告や白色申告を問わず、電子取引のデータは必ず電子で保存する必要があります。
紙で保存を継続する選択肢もありますが、取引先からの請求書や領収書が電子で届くケースが増えているため、電子データでの対応は避けられません。法対応のため、早めにシステムを導入しましょう。
無料で利用できる電子帳簿システムはある?
クラウド会計ソフトやストレージサービスの中には、無料プランや試用版が用意されているものもあります。まずは無料プランを利用して操作性や機能を確認してみてください。
ただし、無料プランでは保存容量や機能に制限があることが多いため、長期利用や税務調査に備えるなら有料プランへの移行がおすすめです。コストだけでなく、要件適合性やサポート体制も含めて検討しましょう。
電子帳簿保存法でNGなのは?
電子帳簿保存法においてNGとなるのは、改ざん可能な形での保存や検索性を欠いた保存方法です。具体的なNG例は、次の通りです。
- タイムスタンプを付与せずに取引データを保管する
- 日付・金額・取引先名で検索できない形式で保存する
- システム障害によりデータの復元ができない状態となる
税務調査に備え、適正な運用と定期的なチェックを行いましょう。
【まとめ】自社の導入目的・タイプに合う電子帳簿保存システムを選ぼう
電子帳簿保存システムのおすすめや選び方、導入するメリットなどについて解説してきました。
電子帳簿保存システムには3つのタイプがあり、それぞれ対応する業務範囲が異なります。そのため、自社での運用目的に合ったものを選ぶことが重要です。製品を選ぶ際には機能や操作性に注目しましょう。
操作性が良い製品を選べば、円滑に運用を開始を開始できます。ただし、システム連携を行う場合は、大幅な業務フローの見直しが必要になる可能性があるので注意が必要です。
当記事を参考にして、ぜひ自社に合った電子帳簿保存システムを探してみてください。