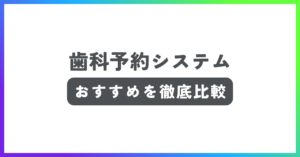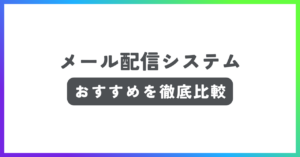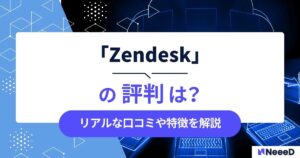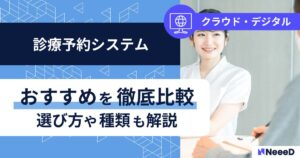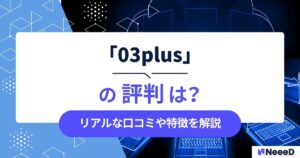健康診断システムおすすめ3選【26年1月最新】システムの選び方や基本機能を解説
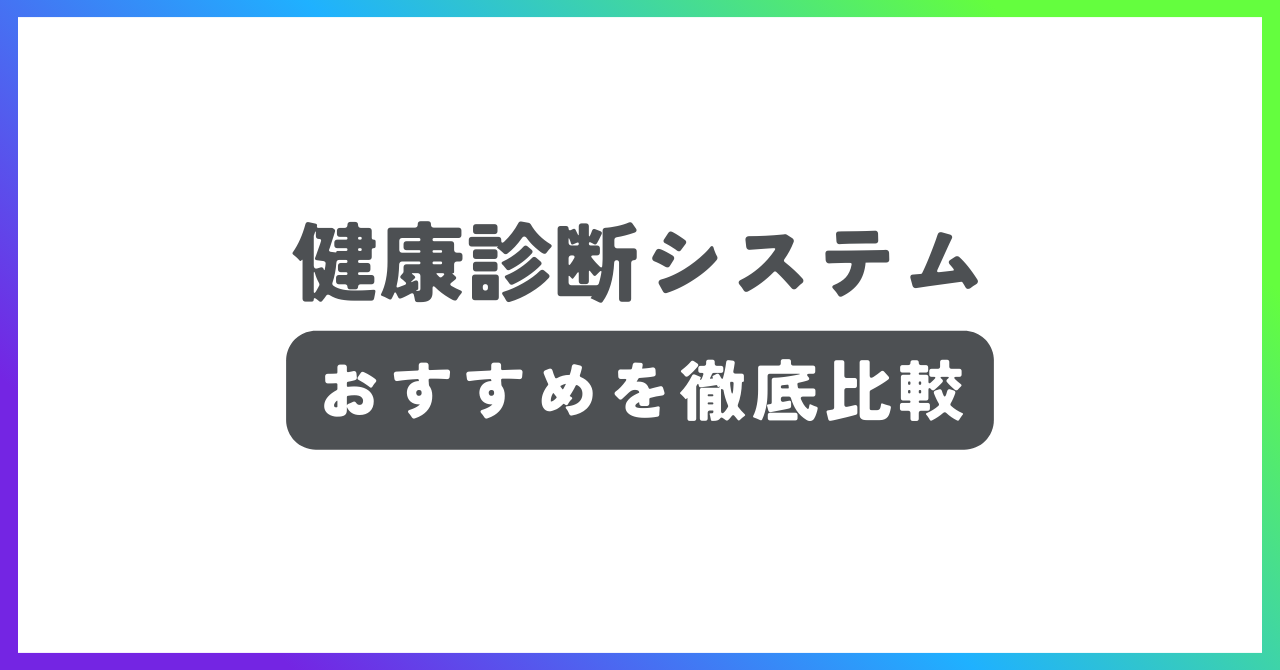
健康診断に関わる業務を効率化したい医院にとって、健康診断システムの導入は有効な手段です。
しかし、各システムの特徴や強みを把握しないまま導入すると、かえって作業負担が増えてしまうリスクもあります。日々の診療と並行して健康診断業務を効率的に管理するためには、機能性、操作性、コストなど様々な観点からの比較が必要です。
本記事では健康診断システムおすすめの3つを比較し、選び方や基本機能、導入するメリットなどについて解説します。
「自院に合った健康診断システムを導入したい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
健康診断システムおすすめ3選を比較

医療機関向けの健康診断システムは多数ありますが、その中でも特に機能性や使いやすさで評価の高い3つのシステムを比較してみましょう。
| 健康診断システム | 特徴 |
|---|---|
| iD-Heart | 院内システムとの連携性が高く、診療報酬改定へ自動対応可能 |
| HealthECO | 現場の意見を反映した操作性で、経年管理機能も搭載 |
| タック総合健診システム | 1,000施設以上の導入実績あり。専任スタッフによるサポートデスク完備 |
iD-Heart
iD-Heartは、院内の既存システムとの連携性に優れた健康診断システムです。特に電子カルテやレセプトシステムとの円滑な連携により、データの二重入力を防止できます。
健診予約管理や問診票の電子化、報告書作成など、充実した機能を標準搭載しており、業務全体の効率化をサポートします。
| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 対象規模 | 中〜大規模医療機関向け |
| 導入実績 | 医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院 医療法人寿芳会 加藤内科胃腸科 医療法人 ONE きくち総合診療クリニックなど |
| 主な機能 | 健診予約管理、問診票電子化、結果判定自動化、報告書作成、データ分析 |
| 電話番号 | 058-273-1445 |
| 会社所在地 | 〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町八丁目8番地1 |
iD-Heartは、診療報酬改定に自動的に対応する機能を備えています。
医療制度の改正に伴いシステムが自動更新されるため、法改正の影響を受ける業務の調整が不要となります。これにより、健診業務が常に最新の基準に準拠した形で運用できます。
また、院内の電子カルテやレセプトシステムとスムーズに連携することで、患者情報の二重入力を防ぎます。健診結果や予約情報の自動共有が可能になり、データの整合性が確保され、事務処理の効率がアップします。
健診業務の進捗管理も可能で、受診者ごとの検査ステータスを一目で把握できるため、業務遅延の防止にもつながります。
HealthECO
HealthECOは、小〜中規模医療機関向けに特化した健康診断システムで、特に経年管理機能に強みを持っています。
受診者の過去の健診データと比較しながら健康状態の変化を分析できるため、長期的な健康管理の精度向上に貢献します。
| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 対象規模 | 小〜中規模医療機関向け |
| 導入実績 | 本八幡セントラル放射線科クリニック 医療法人社団 三医会 三輪病院 医療法人社団 岡田医院など |
| 主な機能 | Web予約、問診管理、結果自動判定、報告書作成、経年管理 |
| 電話番号 | 042-726-1200 |
| 会社所在地 | 〒194-0021 東京都町田市中町1-26-4 シャトーグレイス103 |
HealthECOは医療現場の意見を反映したユーザーインターフェースを採用し、新しいスタッフでも短期間で操作を習得できる設計となっています。
Web予約機能を活用すると受診者が事前に問診情報を入力でき、受付業務の負担軽減が期待できます。問診管理機能では、情報を電子化することで診察時のスムーズな情報共有をサポートします。また、検査結果の自動判定機能も備えており、迅速かつ正確な結果判定を可能にします。
さらに報告書作成機能では、各施設のニーズに応じたフォーマットのカスタマイズが可能で、自院の性質や企業の要望を考慮した効率的な情報管理を実現します。
タック総合健診システム
タック総合健診システムは、全国約1,000施設以上で導入されています。小規模なクリニックから大規模な健診センターまで対応できるスケーラブルな設計が特徴です。
必要に応じて機能の追加ができるため、各医療機関の業務フローに適した運用が実現します。
| 料金プラン | 要問い合わせ |
|---|---|
| 対象規模 | 小〜大規模医療機関向け |
| 導入実績 | 全国約1,000施設以上 |
| 主な機能 | 予約管理、問診票電子化、結果自動判定、報告書作成、データ分析、請求管理 |
| 電話番号 | 584-75-6501 |
| 会社所在地 | 〒503-0803 岐阜県大垣市小野4丁目35番地12 |
タック総合健診システムは、特定健診や協会けんぽの制度改定に対応し、常に最新の基準で健診業務を運用できるよう設計されています。定期的なシステムアップデートにより、法改正や医療制度の変更にも迅速に対応可能です。
さらに、システムの運用を支える専任スタッフによるサポートデスクを完備し、導入後の業務運用や環境の変化にも対応できる体制を整えています。これにより、トラブル発生時の迅速な対応や運用の最適化が可能となり、医療機関の負担を軽減します。
加えて、受診状況やタスク管理機能の強化により、業務の進捗をリアルタイムで把握できます。個人・団体予約や仮予約に対応し、カレンダー上で空き枠を色と数値で識別できるため、予約管理の効率が向上します。
失敗しない健康診断システムの9つの選び方
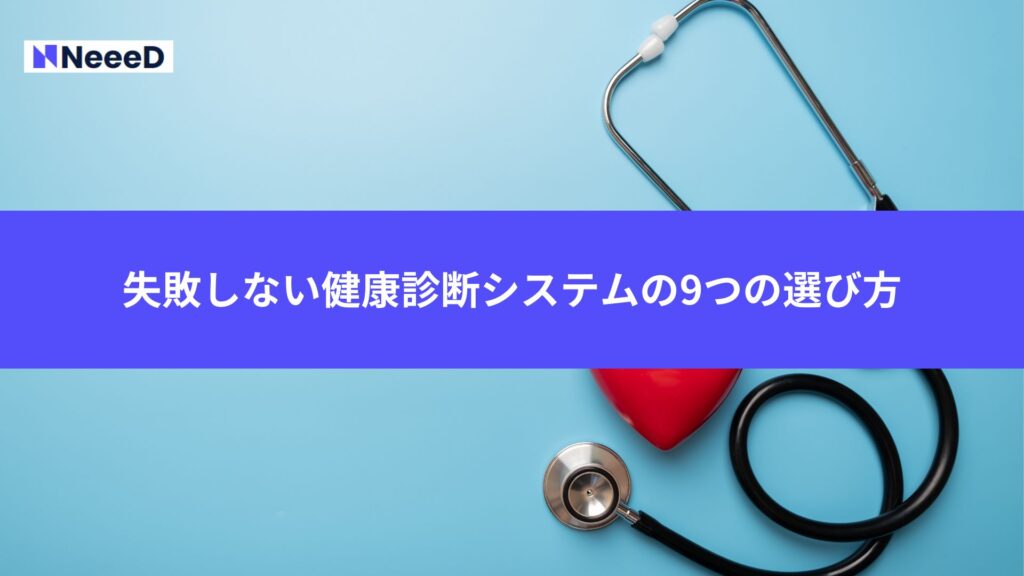
健康診断システムを選ぶ際には、以下の9つのポイントを押さえることで、自院に最適なシステムを見つけることができます。
病院の規模に適しているか
健康診断システムは、導入する医療機関の規模に応じた適切なものを選ぶことが大切です。
小規模クリニックでは、シンプルな機能で運用しやすく、導入コストや運用負担の少ないシステムが適しています。一方、大規模病院や健診センターでは、予約管理や結果判定の自動化、データ分析機能など多くの機能を搭載し、拡張性も高いシステムが必要です。
加えて、院内の電子カルテや他の医療システムとスムーズに連携できるかも重要なポイントとなります。自院の規模や運用フローに合ったシステムを選定することで、業務の効率化と健診サービスの質向上につながります。
クラウド型とオンプレミス型のどちらが自院に合うか
健康診断システムには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | インターネット経由でサービスを利用するタイプ | ・初期費用が抑えられる ・サーバー管理不要 ・場所を選ばずアクセス可能 ・自動アップデートに対応 | ・通信環境に依存 ・月額費用が継続的に発生 ・カスタマイズの自由度が低い |
| オンプレミス型 | 自院内にサーバーを設置して運用するタイプ | ・通信環境に左右されない ・高度なカスタマイズが可能 ・データ管理の自由度が高い | ・初期費用が高い ・サーバー管理が必要 ・アップデートに手間がかかる |
電子カルテなど他のシステムとの連携や、院内のIT環境、予算などを考慮して最適な方式を選択しましょう。
予算内で導入できる価格か
健康診断システムの費用は、大きく初期費用と月額費用に分かれます。
初期費用には、システム導入費やカスタマイズ費用、既存データの移行費用、ハードウェアの導入費などが含まれます。一方、月額費用には、ライセンス料、システムの維持管理にかかる保守費用、定期的なアップデート費用、クラウド型の場合はサーバー利用料が含まれることが一般的です。
導入前にこれらの総コストを明確にし、長期的な運用コストも考慮した上で、投資対効果を算出することが重要です。
また、機能追加やカスタマイズが必要な場合、追加費用が発生する可能性があります。契約内容やサポート体制を事前に確認し、コストと導入効果を比較検討することが重要です。
業務効率化に必要な機能が搭載されているか
自院の業務を効率化するために必要な機能が搭載されているかを確認することも大切です。
たとえば予約管理機能が適切に備わっていなければ、受診者のスケジュール管理が煩雑になり、予約の重複や空き枠の無駄が発生してしまいす。また、報告書作成機能が不十分だと、診断結果のまとめや提供に時間がかかり、受診者への迅速な情報提供が難しくなります。
予約管理、問診票登録、結果の自動判定、報告書作成などの基本機能が充実しているかをチェックするのが大切です。
基本機能について詳しく知りたい方は、健康診断システムの基本機能もあわせてご覧ください。
セキュリティが強化できるか
健康診断データは、個人の医療情報や機微情報を含むため、高度なセキュリティ対策が不可欠です。
データの不正アクセスや漏洩を防ぐために、2段階認証やワンタイムパスワードなどの認証機能を備えたシステムを選定することが推奨されます。また、データの暗号化技術を活用し、送受信時の情報保護を強化することも重要です。
さらに、定期的なバックアップ機能が搭載されているか確認し、災害時やシステム障害時に迅速な復旧が可能かどうかを事前に検討する必要があります。クラウドベースのシステムであれば、データの自動保存や遠隔アクセスによる安全な運用が可能です。
これらの対策を講じることで、健診データの安全性を確保し、医療機関の信頼性を維持することができるでしょう。
既存システムと連携しやすいか
医療機関の業務を効率的に進めるためには、電子カルテやレセプトシステムなど、既存の院内システムとスムーズに連携できることが重要です。
データのやり取りが複雑だと、入力ミスが増えたり、スタッフの負担が大きくなる可能性があります。そのため、新たに導入するシステムが、既存のシステムと簡単に情報をやり取りできるかを確認しましょう。
具体的には、どのような形式のファイルを扱えるか(CSVやXMLなど)、システム間の自動連携機能があるかといった点をチェックするとよいでしょう。
既存のデータフォーマットにフィットしているか
医療機関では、特定健診の結果だけでなく、人間ドックや企業向け健康診断など、多様な健診データを取り扱います。これらのデータを一元管理できるシステムを選ぶと、業務の効率化が期待できます。
そのため、自院が実施している健診の種類に対応したデータフォーマットを採用しているかどうかを確認しておきましょう。たとえば、DPC(Diagnosis Procedure Combination)データや、自治体ごとに異なる健診結果フォーマットに対応しているかをチェックするのがおすすめです。
さらに、システム内でフォーマットの変換機能が備わっていると、異なるデータ規格の統合がスムーズに行え、後々の運用が楽になります。
報告書の内容が変更しやすいか
健診結果の報告書は、受診者にとって健康管理の重要な指標となるため、適切な情報が分かりやすく記載されていることが求められます。
報告書のレイアウトやデザインを自由にカスタマイズできるシステムを導入すれば、自院のブランディングや診療方針に沿った形で情報を提供できます。また、文字サイズやフォントの変更、ロゴの挿入、グラフやチャートを活用した視覚的な表現が可能かどうかも確認しておくとよいでしょう。
さらに、患者のニーズに応じて多言語対応の報告書を作成できるシステムであれば、外国人受診者にもわかりやすい形で結果を提供できます。
法改正に対応しやすいか
健康診断に関する法令やガイドラインは定期的に改正されるため、導入するシステムがこれらの変化に迅速に対応できるかどうかを確認することも大切です。
特に、労働安全衛生法や高齢者医療確保法などの法改正に即座に対応できるシステムを選ぶことで、業務の混乱を防ぎ、法的リスクを軽減できます。
また、クラウド型システムを採用することで、提供元が自動的にアップデートを行い、新しい法規制や制度変更に対応できるメリットがあります。これにより、医療機関側で手動のアップデートを行う必要がなくなります。
オンプレミス型のシステムを導入する場合は、ベンダーによるサポート体制や、アップデートの頻度・方法についても事前に確認しておくと安心です。
健康診断システムとは何
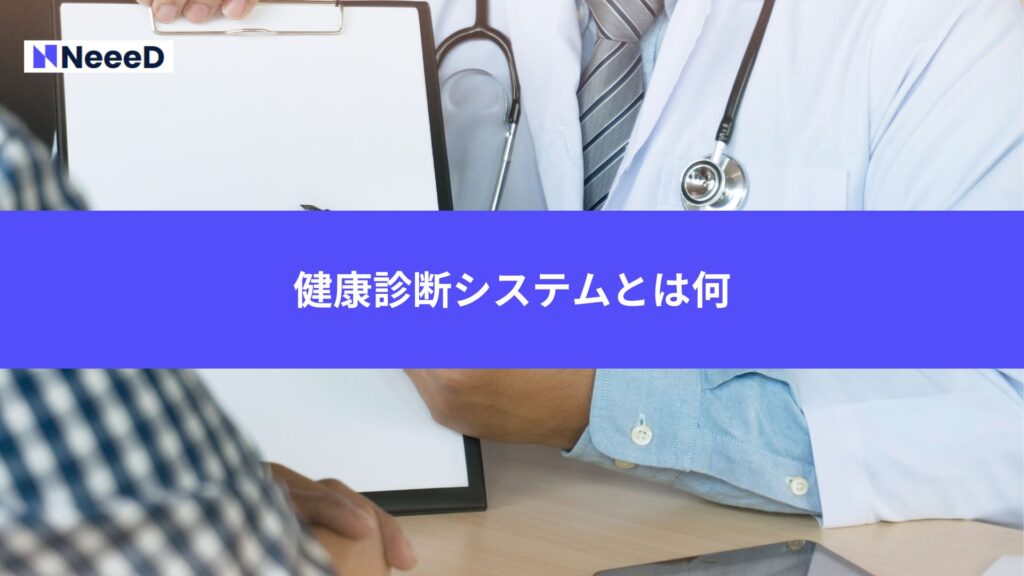
健康診断システムとは、健康診断の予約受付から結果管理、報告書作成までの一連の業務をデジタル化し、効率的に管理するためのシステムです。
従来の紙ベースの管理から電子化することで、業務効率の向上やヒューマンエラーの削減、データの一元管理を実現します。
健康診断システムは、主に以下の3つのタイプに分けられます。
- Web問診特化型:問診票のデジタル化に特化したシステムで、スマホやタブレットから問診入力が可能
- クリニック業務全般向け:予約管理から会計までクリニック全体の業務をカバーするシステム
- 健診・人間ドック専門型:健康診断や人間ドックの専門的な管理に特化したシステム
医療機関の規模や業務内容に応じて、最適なタイプを選択することが重要です。
健康診断システムの基本機能
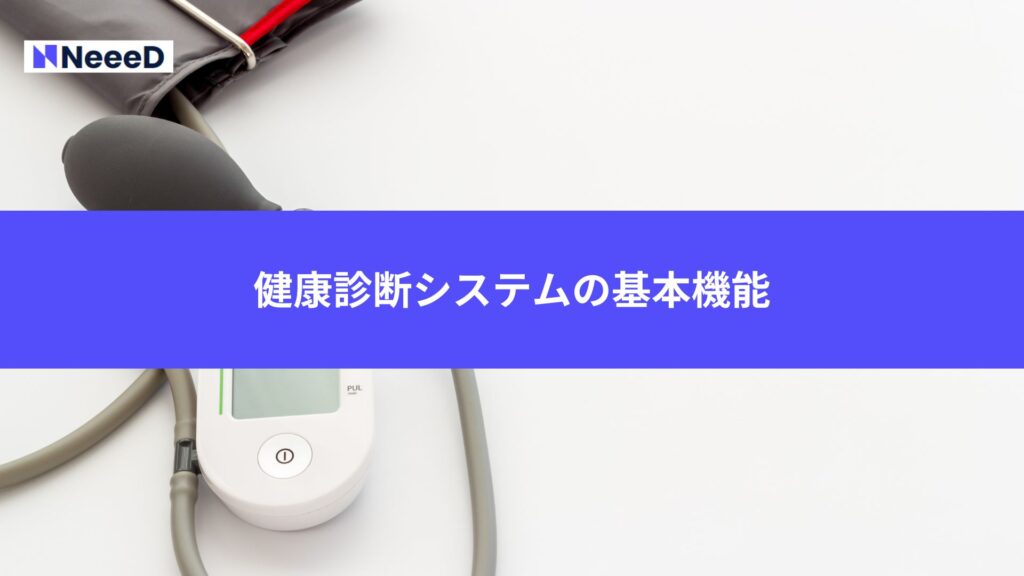
健康診断システムには、健康診断業務を効率化する機能や、従業員の健康管理を目的とした機能が搭載されています。主な基本機能は以下の通りです。
契約プランの登録・管理機能
健診コース、オプション検査、料金など、企業や個人と締結した契約内容を一元管理できる機能です。
契約プランをデジタル化することで、請求業務における人的ミスを削減できます。特に、複数の契約先がある場合、割引、特典、契約期間など個別の条件を一覧で確認できると、事務作業の負担を軽減できます。
また、システム内で契約内容の変更履歴を管理できる機能があれば、過去のデータを簡単に参照でき、トラブル防止にもつながります。
予約登録・管理機能
健康診断の予約状況をカレンダー形式で管理し、空き状況の確認や予約変更をスムーズに行える機能です。
特にWeb予約システムと連携することで、受診者は24時間いつでも予約が可能になり、電話対応の負担が軽減されます。また、企業単位での一括予約や、キャンセル待ち機能などが備わっていると、より利便性が向上します。
さらにリマインド通知機能を活用すれば、予約者の受診忘れを防ぎ、無断キャンセルのリスクを低減できます。
問診登録機能
受診者がスマートフォンやタブレットから事前に問診票を入力できる機能です。
従来の紙ベースの問診票と比較して、記入漏れや判読ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。入力されたデータは自動的にシステムに取り込まれるため、スタッフによる転記作業が不要になります。
また、過去の問診データを蓄積できるシステムであれば、前回の健診情報を参照しながら問診を記入できるため、受診者の作業負担も軽減できます。
健康診断自動判定機能
健康診断自動判定機能は、受診者の検査結果をもとに、基準値との比較や経年変化の分析を行い、異常値の検出や健康リスクの評価を支援する機能です。
各検査項目の正常範囲を設定し、それを超える値があれば即座に警告を表示し、必要に応じて医師の追加診断を促します。また、過去のデータを蓄積・分析して特定の疾患リスクや健康状態の変化を予測することで、早期発見・早期対応を可能にします。
この機能により、医師や保健師が診断すべき重要なポイントを迅速に把握でき、診断の質の向上につながります。
ストレスチェック機能
ストレスチェック機能は、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施・管理するために、受診者(従業員)のメンタルヘルス状態を簡便に評価できる機能です。
この機能では、ストレスチェック用の質問票をシステム上で管理し、受診者に配布・回収を行います。回答データは自動集計され、高ストレス者の抽出が可能です。
さらに、ストレスチェックの結果を企業向けにレポートとして出力する機能を備えたシステムもあります。
組織全体のストレス傾向を分析したデータを提供することで、企業は従業員のメンタルヘルス状態を把握でき、健康経営につながります。
結果報告書作成機能
結果報告書作成機能は、健康診断の結果を分かりやすくまとめた報告書を自動生成する機能です。
受診者ごとの健康状態を一目で把握できるよう、各検査項目の結果をグラフやチャートで視覚的に表示し、過去のデータと比較することで健康状態の変化を示します。異常値や注意が必要な項目については、強調表示や警告アイコンを用いることで、受診者自身がリスクを認識しやすくなります。
従業員の健康診断結果も自動生成できるため、企業の健康施策に役立てられます。
勤怠データ管理機能
勤怠データ管理機能は企業の従業員向けのもので、従業員の健康診断結果と勤怠データを統合し、健康状態と労働生産性の関連を可視化する機能です。
たとえば、長時間労働による疲労蓄積や睡眠不足が原因で欠勤や遅刻が増えている場合、その要因を分析し、企業に適切な健康支援策を提案できます。
また、従業員の健康データを定期的に分析することで、慢性的な健康リスクを抱える従業員を早期に特定し、適切な診療やフォローアップの機会を増やすことが可能です。
これにより、医院にとっては定期的な診察機会の増加や、企業との長期的な関係構築につながります。
福利厚生サポート機能
福利厚生サポートも従業員向けの機能となり、健康増進プログラムや健康イベントの案内、参加管理を行う機能を提供し、企業の福利厚生担当者と連携して従業員の健康意識向上を支援します。
たとえば、ストレスチェックの結果をもとにしたメンタルヘルス対策や、運動・食事改善プログラムの提供など、医院が健康指導を行う機会を増やせます。
また、定期的な健康セミナーやオンライン相談を実施することで、従業員との接点を増やし、継続的な医療サービスの提供が可能になります。
健康診断システムを利用する6つのメリット
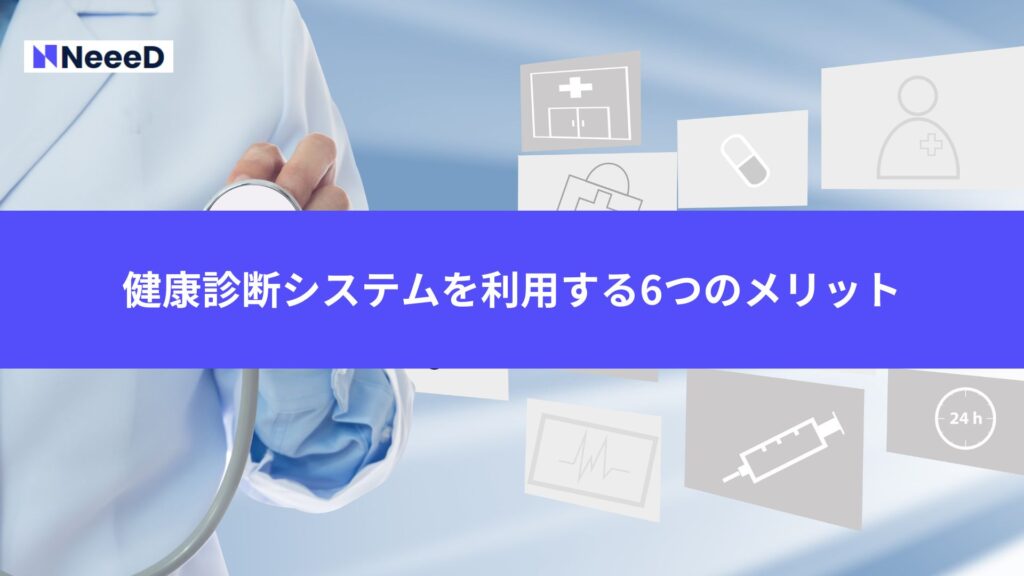
健康診断システムを導入することで、以下のようなメリットが得られます。
受診者の予約・受付業務が効率化できる
健康診断システムの導入により、受診者の予約や受付業務を効率化することができます。
オンライン予約機能を活用すれば、24時間いつでも予約が可能となり、電話対応の負担を大幅に軽減できます。また、予約状況がリアルタイムで可視化されるため、予約枠の調整や人員配置の最適化が可能です。
なお、受診者の氏名や住所、予約日時、健診メニューなどの情報を一括管理でき、スムーズな受診フローを実現できます。
さらに、QRコードを利用した受付システムを導入すれば、受診者が受付でスキャンするだけでチェックインでき、待ち時間の短縮にもつながります。これにより受付業務の負担を軽減し、多くの受診者をスピーディーに対応できるでしょう。
健診結果の報告書がスピーディに作成・送付できる
健康診断システムでは、検査データの入力から報告書の作成までを自動化できます。
テンプレート機能を活用することで、統一されたフォーマットの報告書を効率的に作成でき、医師のコメント入力もシステム上で簡単に行えます。そのため、結果報告のスピードが大幅に向上します。
これにより、異常値や要再検査の項目がある受診者に対して、迅速に通知することで早期の医療介入や生活改善を促すことが可能です。
手作業での報告書作成に比べて人的リソースや時間の削減につながり、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
健診会計の工程を削減して負担が軽減できる
健診コースや追加検査項目に応じた料金の自動計算機能を搭載することで、会計ミスを防止し、会計業務の負担を軽減できます。
たとえば、オプション検査の追加料金が自動反映されることにより、手動計算の手間を省いてミスの発生を防ぐことが可能です。また、領収書や請求書の自動発行機能を活用すれば、窓口での手続きをスムーズに進めることができ、受診者の待ち時間削減につながります。
さらに企業健診の場合は、契約条件に基づいた一括請求処理が可能で、経理業務の負担を軽減します。
保健指導に関する業務が可視化できる
健康診断システムには、健診結果データをもとに保健指導の対象者を自動抽出し、健康リスクの度合いに応じた指導内容を提案する機能を搭載したものもあります。
たとえば、高血圧や糖尿病リスクがある受診者には、生活習慣改善のための個別アドバイスを自動で提供します。また、保健指導の進捗状況や指導内容、効果測定をデータベース化することで、指導の質の向上や均質化を図れます。
医院側は、指導履歴を一元管理できるため、継続的なフォローアップが可能となり、患者との長期的な信頼関係の構築にもつながります。
企業向けの健康経営支援の一環として、従業員の健康管理サポートを提供することで、新たな収益機会を創出できる点も大きなメリットです。
事務作業の効率化が図れる
紙ベースの業務をデジタル化することで、データ入力や書類整理などの事務作業時間を大幅に削減できます。
たとえば検査データの自動取り込み機能を利用すれば、手入力による人為的ミスを防止できます。さらに診断結果の自動判定機能を活用すれば、異常値のチェックがシステム内で完結して迅速な結果通知が可能になります。
データの検索性も向上するため、過去の健診履歴を簡単に参照でき、統計分析や健康指導の計画立案にも活用できます。
従業員の離職率を下げられる
健康診断システムの導入により、業務の効率化が進み、スタッフの業務負担が軽減されます。
特に、予約管理や結果報告、会計処理などの時間が短縮されることで、残業時間の削減につながり、ワークライフバランスの改善が可能となります。これにより職場満足度が向上し、離職率の低下に寄与するでしょう。
また、システムによる業務の標準化により、業務の属人化を防ぎ、新人教育の負担も軽減できます。
健康診断システムを利用する際の注意点
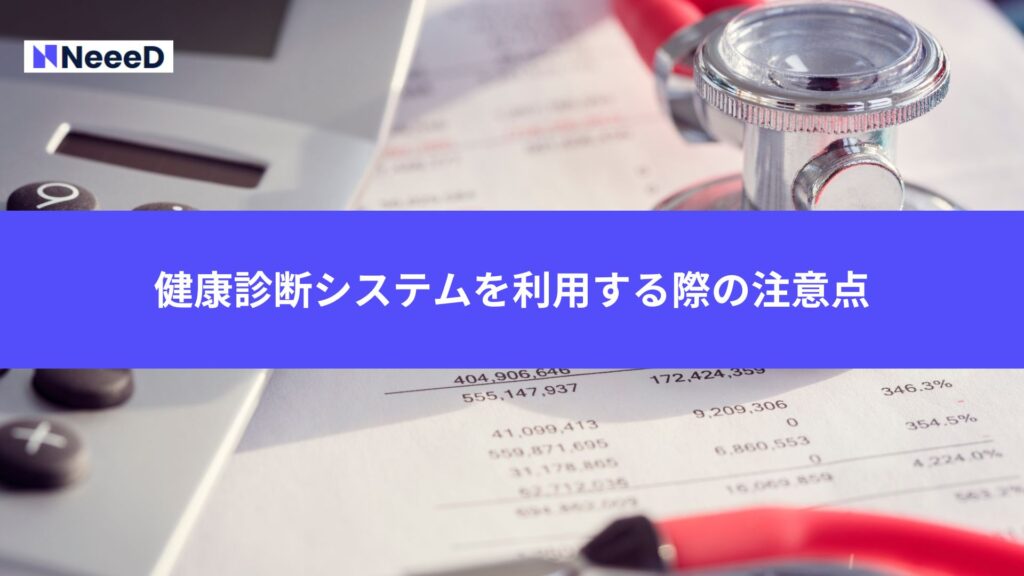
健康診断システムを効果的に活用するためには、以下の注意点にも留意する必要があります。
健康管理業務が可視化できるシステムを構築する
健康診断システムを導入する際は、単なるデータ管理だけでなく、健康管理業務全体の流れが可視化できるシステム構築を目指しましょう。
受診前の準備から、受診当日の流れ、結果報告、フォローアップまでの一連のプロセスが見える化されることで、業務の無駄や改善点を発見しやすくなります。また、スタッフ間での情報共有や引き継ぎもスムーズになり、サービスの質の均一化につながります。
導入初期には、現場の声を積極的に取り入れながらシステムをカスタマイズし、実際の業務フローに合った仕組みにしていくことが重要です。
セキュリティ対策に力を入れているかチェックする
健康診断データは個人の機微情報を多く含むため、セキュリティ対策は最重要事項です。システム選定時には、以下のセキュリティ機能が搭載されているかを必ずチェックしましょう。
- アクセス権限の細かな設定機能
- データの暗号化
- ログイン履歴の記録と監視機能
- 定期的なバックアップ機能
- 2段階認証などの強固な認証システム
また、システム提供企業のセキュリティに対する姿勢や、セキュリティ認証の取得状況も確認することをおすすめします。
万が一の情報漏洩に備え、賠償責任保険への加入状況なども確認しておくと安心です。
健康診断システムの比較に関するよくある質問
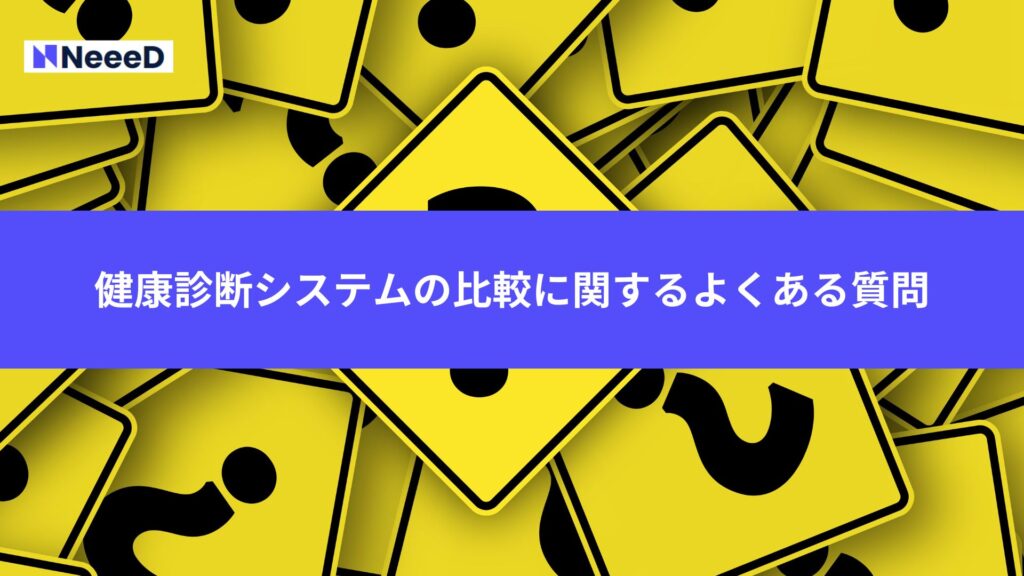
ここからは、健康診断システムについてのよくある質問に回答していきます。
健診システムと電子カルテを連携させるとどうなる?
健診システムと電子カルテを連携させることで、データの二重入力が不要になり、基本情報や検査結果が自動的に共有されます。これにより、入力作業の手間を削減できます。
また、健診データと日常診療の情報を一元的に管理・参照できるようになることで、より包括的な医療サービスの提供につながります。なお、健診で発見された異常所見についても、通常診療の中でスムーズに経過観察を行えるようになります。
健診データと診療データを組み合わせた分析が可能になることで、より精度の高い健康リスク評価を実現し、予防医療の質を向上させることができるでしょう。
クラウド系の健診システムを利用するメリットは?
クラウド型健診システムを導入することで、サーバー設備の購入や構築が不要となり、初期投資を抑えることができます。また、システムの保守管理やバックアップ作業を提供元が行うため、院内のIT管理負担が軽減されるというメリットもあります。
システム更新やバージョンアップが自動で行われるため、常に最新の機能を利用できる点も魅力です。インターネット環境があればどこからでもアクセス可能なため、テレワークや複数拠点での運用にも適しています。
加えて、業務の拡大に応じてシステムの規模を柔軟に拡張できるスケーラビリティの高さも、クラウド型ならではの特長です。
【まとめ】自院の業務内容に適した健康診断システムを選ぼう
診断システムは、健康診断の受付から結果の管理、日常業務の管理まで幅広く対応し、業務の効率化を支援するツールです。
さまざまなシステムが提供されており、それぞれに異なる特徴があるため、自院の規模や業務内容に適したものを選ぶことが重要です。
システムを選定する際には、まず必要な機能が備わっているかを確認することが大切です。さらに、クラウド型とオンプレミス型のどちらが自院のIT環境に適しているかを考慮し、導入コストが予算内に収まるかどうかを検討しましょう。
今回解説したポイントを総合的に考慮し、デモ体験やトライアル利用を活用しながら、自院に最適なシステムを選ぶことをおすすめします。
自院に合ったシステムの導入により、業務の効率化と医療サービスの質の向上の両立を目指しましょう。