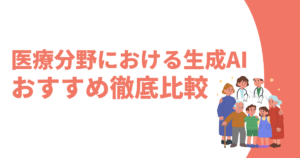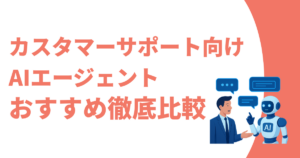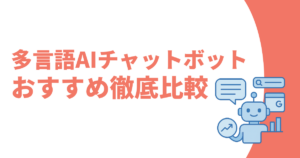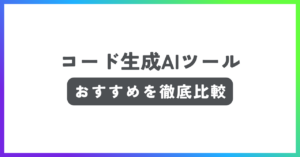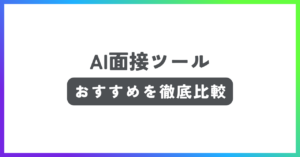【26年1月最新】AI搭載BIツールのおすすめ3選!AIとの違いや活用のコツも解説
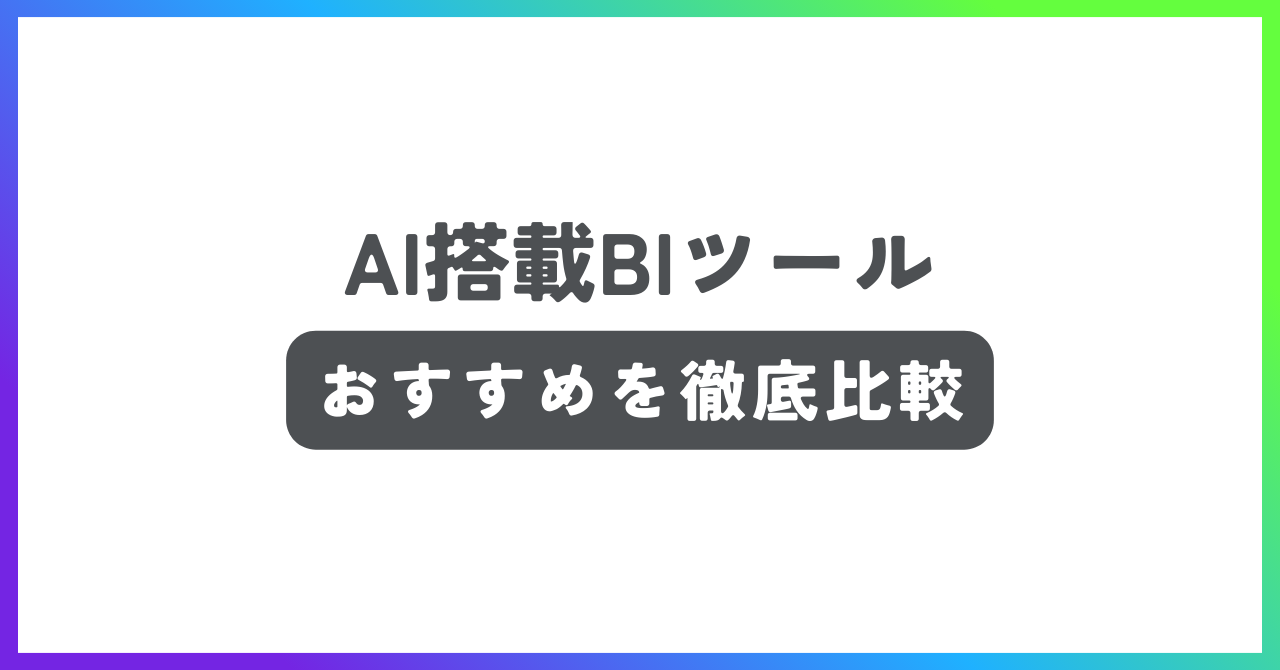
AI搭載BIツールは、従来のBIツールより高度なデータ分析や自動化に役立つとして注目を集めています。一方で、「BIツールとAIの違いは?」「どのAI搭載BIツールがおすすめ?」など、気になることが多い方もいるのではないでしょうか。
実際に、BIツールの種類が多すぎて比較しきれず、導入後に「想像していた使いやすさと違った」と後悔するケースも少なくありません。
本記事では、AI搭載BIツールのおすすめ3選を厳選してご紹介します。さらにAIとの違いや活用のコツにも触れているので、AI搭載BIツールを比較したい方や導入を検討している方はぜひご覧ください。
【2025年9月最新】おすすめのAI搭載BIツール3選
ここでは、おすすめのAI搭載BIツールを紹介します。
| BIツール | 特徴 |
|---|---|
| Microsoft Power BI | Microsoft 365との親和性が高く、Excelデータの分析に強い |
| Tableau | データの可視化表現が豊富で、直感的な操作が可能 |
| Looker Studio Pro | Googleサービスとの連携に優れ、リアルタイム分析に最適 |
いずれもAIが膨大なデータを短時間で処理し、傾向や異常値を自動検出してくれるツールであり、分析の自動化や業務効率化に役立ちます。自社に合うBIツールを選定するためにも、まずはツールごとの特徴を理解していきましょう。
以下では、ツールごとに詳細を解説します。
Microsoft Power BI

| 料金プラン | – Power BI Desktop:無料 – Power BI Pro:月額 1,360円/ユーザー(税抜) – Power BI Premium:月額 2,715円/ユーザー または 容量ベース課金 |
|---|---|
| 主な機能 | – データ可視化(豊富なグラフ・ダッシュボード) – AIを活用したデータ分析- Excel・Teams・Azureとのシームレス連携 – リアルタイムデータ分析- モバイルアプリ対応 |
| 提供形式 | クラウド(SaaS)/オンプレミス(Power BI Report Server) |
| 導入実績 | 世界中で25万社以上、日本国内でも大手企業・自治体が導入 |
| 会社所在地 | 米国ワシントン州レドモンド(Microsoft Corporation 本社) |
Microsoft Power BIはMicrosoftが提供するBIツールで、企業が持つ膨大なデータを収集・分析・可視化し、グラフやダッシュボードにまとめることでデータドリブンな意思決定を支援します。
無料版(Desktop)があるため、BIツール初心者でも導入しやすく、お試しで操作感を試すなどフレキシブルな使い方ができるのがポイントです。また、使いやすいUIでグラフ・ダッシュボードを簡単に作成できるので、複雑な操作が苦手な方にもおすすめできます。
Microsoft系列のツールと連携しやすい仕組みになっているため、Excel・Azure・Teamsなどを普段よく使う方には特におすすめです。「データ活用を始めたいけれど費用は抑えたい」「Excelを多用している企業」に特にメリットがあります。
Tableau

| 料金プラン | – Tableau Viewer:月額 15 USD/ユーザー – Tableau Explorer:月額 42 USD/ユーザー – Tableau Creator:月額 75 USD/ユーザー |
|---|---|
| 主な機能 | – 直感的なドラッグ&ドロップ操作によるデータ可視化 – 豊富なデータコネクタ(クラウド・オンプレ対応) – ダッシュボード共有・チームコラボレーション – AIを活用した予測分析・自然言語クエリ- モバイル対応 |
| 提供形式 | クラウド(Tableau Cloud)/オンプレミス(Tableau Server) |
| 導入実績 | トヨタ自動車株式会社 サントリーホールディングス株式会社 株式会社三菱UFJ銀行など |
| 会社所在地 | 米国ワシントン州シアトル(Tableau Software, LLC / 現 Salesforce, Inc. 傘下) |
Tableau(タブロー) は、アメリカのTableau Software(現 Salesforce傘下)が提供するBIツールです。大量のデータを視覚的に分析し、直感的な操作でグラフやダッシュボードを作成できることから、データの可視化と意思決定支援に強みを持つツールとして世界中で利用されています。
ドラッグ&ドロップで簡単にグラフやダッシュボードを作成できるなど、直観的な操作ができるのがポイントです。データ分析初心者でも扱いやすい他、複雑なデータや大量のデータでも扱える汎用性の高さが注目されています。
Tableau PrepやTableau CRMを組み合わせることで、予測分析や傾向分析もしやすくなるので連携ツールをお探しの方にもおすすめです。
Looker Studio Pro

| サービス名 | Looker Studio Pro(ルッカースタジオ プロ) |
|---|---|
| 料金プラン | – Looker Studio(無料版):0円 – Looker Studio Pro:ユーザー単位で月額課金 |
| 主な機能 | – Google製品と強力に連携 – 150以上のデータコネクタ(外部サービス含む) – ダッシュボード共有・リアルタイム更新 – チーム管理(Pro版)- サポート・SLA保証(Pro版) |
| 提供形式 | クラウド(SaaS、Google Cloud上で提供) |
| 導入実績 | パナソニック株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン 株式会社講談社など |
| 会社所在地 | 米国カリフォルニア州マウンテンビュー(Google LLC / Alphabet Inc.) |
Looker Studio Pro(ルッカースタジオプロ・旧Google Data Studio) は、Googleが提供するクラウド型BIツール です。
GoogleアナリティクスやGoogle広告などのデータと強力に連携できることから、Webマーケティングや広告分析に特化したBIツールとして利用されています。150以上の外部サービスやデータソースに接続できるので、多機能性が欲しい方におすすめです。
また、小規模・中規模チームは無料版からスタートでき、Pro版ではサポートやサービス保証が付帯するなどコストパフォーマンスのよい運用ができます。有料版では「Gemini in Looker」など機能が増えるので、スモールスタートから大規模利用まで柔軟に対応できるのもメリットです。
AI搭載BIツール選びのポイント

AI搭載BIツールはいずれも業務に役立つツールですが、機能・料金・提供形式・導入実績などがそれぞれ異なる点に注意しましょう。自社の目的や環境に合ったツールを選ばないと、「想像していたツールではなかった…」「ミスマッチが大きくて使いづらい…」などの後悔が生じます。
AI搭載BIツール選びのポイントは以下の通りです。
効率的にデータ活用を進めるためにも、事前の事前に確認しましょう。
必要な機能は搭載されているか
まずは、「自社の分析目的に合った機能が揃っているか」を確認しましょう。AI搭載BIツールには主に以下の機能が搭載されており、目的とする機能に抜け・漏れがないか確認することが大切です。
【AI搭載BIツールでチェックすべき機能例】
| レポート作成機能 | 自動・手動でレポートを作成し、定期配信できる |
|---|---|
| ダッシュボード機能 | 複数データを統合して視覚的に表示、カスタマイズ可能 |
| リアルタイム分析 | データの更新に応じてダッシュボードが自動反映 |
| AIによる予測分析 | 売上や需要の予測、傾向分析が可能 |
| 自動インサイト提示 | 重要なKPIや異常値をAIが自動で抽出・通知 |
| データ統合・連携機能 | 複数システムやクラウドサービスからデータを統合 |
| 自然言語クエリ(NLQ)対応 | 質問形式で分析結果を取得できる |
| 共有・コラボレーション機能 | チーム内でのダッシュボード共有やコメント機能 |
分析の目的に合う機能が漏れなく搭載されていれば、導入後に「必要な分析ができない」「ツールを使いこなせない」などの落とし穴が見つかることもありません。
特定業務に特化した専門的な機能はあるか
「自社の業界や業務に特化した機能があるか」も、事前に確認しておきたいポイントです。業界ごとに必要な分析視点は大きく異なるからこそ、業界特化機能を優先してみるとよいでしょう。
業界特化ごとに必要となる機能の一例は以下の通りです。
| 業界 | 特化機能例 | 効果・メリット |
|---|---|---|
| 製造業 | 生産ライン稼働状況分析 不良率分析 設備稼働予測 | 生産効率向上設備 トラブルの早期発見 |
| 小売業 | 在庫管理 売上予測 店舗別・商品別販売分析 | 適正在庫管理 売上向上 販売戦略の最適化 |
| 物流業 | 配送ルート最適化 需要予測 倉庫在庫管理 | 配送コスト削減 在庫回転率改善 |
| マーケティング | 広告キャンペーン 効果分析 顧客セグメント分析 | 広告ROI向上 顧客ターゲティング精度向上 |
業界特化機能があると、単なるデータ集計だけでなく業務に直結した具体的な改善アクションを取りやすくなります。業界ならではのやり方や特殊な業務が多いときにこそ、活用してみましょう。
既存環境でスムーズにデータ連携できるか
自社の既存システムやクラウドサービスとスムーズにデータ連携できるか、連携可否や拡張性をチェックしておきましょう。多数のツールと連携できればデータの取り込みや更新が容易になり、導入後すぐに分析業務を開始できます。
| ツールカテゴリ | 具体例 | 連携するメリット |
|---|---|---|
| スプレッドシート・表計算 | Excel、Googleスプレッドシート | 日常業務で使う表計算データをそのまま分析できる。 既存の資料をそのまま使える |
| CRM(顧客管理) | Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365 | 顧客データや営業データを分析して、売上予測・クロスセル・リード管理が効率化できる |
| 会計・ERP | SAP、Oracle NetSuite、弥生会計 | 財務・在庫・購買データと連携することで、コスト分析や在庫最適化が可能 |
| マーケティングツール | Google Analytics、Google広告、Facebook広告 | 広告効果やWebサイト訪問データを可視化して、ROI分析やキャンペーン改善に活用できる |
| クラウドデータベース・DWH | BigQuery、Azure SQL、Amazon Redshift | 大量データを高速に取り込み、リアルタイム分析や予測分析ができる |
| コラボレーションツール | Microsoft Teams、Slack | 分析結果やダッシュボードをチームに簡単に共有でき、意思決定が迅速になる |
まずは、既に使っているツールと連携できるか調べてみましょう。特に使用頻度の高いツールと連携できる場合、管理ツールを丸ごと入れ替える手間もかからずシームレスな導入が実現します。
また、マーケティング・営業・財務など業務ごとに最適な連携先を選ぶなど工夫して、BIツールの価値を最大化する方法もあります。
操作性がよく使いやすいか
非エンジニアでも直感的に操作できるかをチェックしておくことで、「操作が難しすぎてなかなか慣れない」「オンボーディングに時間がかかりすぎる」などのミスマッチを予防できます。
操作性を確認する際にチェックしたいポイントは以下の通りです。
- ドラッグ&ドロップでグラフやダッシュボードを作成できるか
- データの結合やフィルタリングが直感的に行えるか
- 分析結果やレポートを簡単に共有できるか
- マニュアルやチュートリアル、ヘルプ機能が充実しているか
- 管理画面が見やすくわかりやすく、システム部門の負担軽減になりそうか
反対に、操作が複雑で使いにくいツールは導入後に社員が使いこなせず、社内での普及率が低くなる可能性があるので注意しましょう。社内の誰でもデータを活用できるツールにすることが、BIツールの形骸化を防ぐカギとなります。
レポートやダッシュボードは見やすいか
経営層でも現場担当者でも確認しやすいレポートやダッシュボードであれば、進捗状況をリアルタイムに把握できます。
レポートやダッシュボードのチェックポイント例は、以下の通りです。
- グラフやチャートの種類が適切で、情報を直感的に理解できるか
- ダッシュボードのレイアウトが整理され、重要なKPIがひと目で分かるか
- フィルターやスライサーで必要な情報に簡単にアクセスできるか
- モバイルやタブレットでも見やすく、場所を問わず確認可能か
反対に、レポートやダッシュボードが複雑で分かりにくいと意思決定のスピードや精度に影響し、せっかくのBI導入効果が低下してしまうので注意しましょう。
「いつ見ても誰が見てもわかりやすいレポート」で「進捗状況がわかりやすいダッシュボード」であることが必須条件となります。ダッシュボードのデザインや掲載項目をカスタマイズできるBIツールにすることもおすすめです。
多言語に対応している
グローバル企業や多国籍企業では、英語など海外言語に対応しているBIツールにしましょう。多言語対応していないツールでは海外拠点での利用が難しく、社内での統一的なデータ活用や意思決定がしづらくなります。
多言語対応のチェックポイント例は、以下の通りです。
- ユーザーインターフェース(UI)が複数言語に切り替え可能か
- レポートやダッシュボードの表示言語を拠点ごとに設定できるか
- サポートやドキュメントが主要言語で提供されているか
- 日付・通貨・数字表記などの地域設定に対応しているか
「日本では日本語で、アメリカでは英語で」などの設定分けができたり、ユーザーごとに使用言語を選べたりするものがおすすめです。グローバルでのデータ活用を統一できる体制づくりに活用してみましょう。
料金体系は適切か
BIツールを導入する前に料金体系を確認し、予算に見合うかシミュレーションしてみましょう。初期費用だけでなく、月額費用や年間契約費用も含めて無理のない範囲で収まるか確認することが大切です。
コスト面でのチェックポイント例は、以下の通りです。
- 初期費用・月額費用・年間費用を明確に把握しているか
- ユーザー数や機能別の料金プランが自社に合っているか
- 無料トライアルや小規模プランがあり、スモールスタートできるか
- 将来的にユーザー追加や機能拡張をした場合の費用も確認しているか
ランニングコストや拡張コストも含めて、トータルで必要な金額がわかれば「想像以上に費用が嵩んだ」などの落とし穴もありません。ツールごとの料金を比較しながら決めるのが近道です。
サポートは充実しているか
初めてBIツールを導入する場合や手厚いサポートを期待する場合は、サポート体制をチェックしておきましょう。導入支援やトレーニング体制が整っていれば、社内普及率の向上に役立ちます。
サポート面でのチェックポイント例は、以下の通りです。
- 導入時のセットアップ支援や初期トレーニングの有無
- マニュアル・ヘルプ・オンラインチュートリアルの充実度
- 問い合わせ対応(チャット、電話、メール)の迅速性
- コンサルティングやカスタマイズ支援の提供有無
社内全体でBIツールを活用できる体制を整えられるので、浸透も早くなるのがポイントです。また、問い合わせ時のスピードや手法などもチェックしておくと、いざというときに安心できます。
BIツールとは
BIツール(=Business Intelligence)とは、企業が保有するさまざまなデータを収集・統合・分析し、経営や業務の意思決定を支援するソフトウェアのことです。
売上・在庫・顧客情報・Webアクセスデータなどを一元管理し、グラフやダッシュボードとして可視化しながら直感的にデータの傾向や課題を把握したいときに役立ちます。
BIツールの種類
BIツールの種類は、主に「従来型BI(Traditional BI)」と「セルフサービスBI(Self-Service BI)」とに分けられます。
| 種類 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 従来型BI(Traditional BI) | IT部門やデータ専門家がデータ分析・レポート作成を担当するBI | – 分析は専門チームが担当 – レポート作成に時間がかかる – 大規模データの統合に強い |
| セルフサービスBI(Self-Service BI) | 現場ユーザーが自分でデータを分析・可視化できるBI | – ドラッグ&ドロップで分析可能 – リアルタイムでダッシュボード作成 – 専門知識が不要 |
従来型BIはIT部門の担当者やデータ専門家が活用することの多いツールとして知られており、大規模データの分析・統合など専門性の高い業務と相性がよいのが特徴です。
反対に、セルフサービスBIはドラッグ&ドロップで分析できるなど使い勝手の良さとUIに強みがあり、データサイエンティストなどの専門家でなくても使いやすいデザインになっています。情報共有ツールや意思決定の支援ツールとして使われることも多く、専門知識不要で使える手軽さもあって近年大幅に導入件数を伸ばしました。
いずれも便利なツールであることに変わりはないため、自社に合うBIツールを選定・導入してみましょう。
BIツールの活用例
BIツールは、企業のさまざまな業務でデータを可視化・分析し、意思決定を支援するために活用できます。営業・在庫・顧客情報など幅広いデータを扱えるため、業務の効率化や戦略立案に役立てることが可能です。
| 主な活用例 | 特徴・内容 |
|---|---|
| 営業成績の可視化 | 売上や受注状況、営業担当別の成果をダッシュボードで管理し、目標達成度を一目で把握 |
| 在庫管理の最適化 | 商品別・店舗別の在庫状況を分析し、適正在庫の維持や欠品防止に活用 |
| 顧客データ分析 | 購買履歴や属性情報を分析して、ターゲットマーケティングやクロスセル施策を支援 |
| 財務・経理分析 | 売上・費用・利益の推移を可視化し、経営判断や予算管理を効率化 |
| マーケティング施策の効果測定 | 広告やキャンペーンの成果をリアルタイムで確認し、改善施策を素早く実行 |
つまり、業務の現状把握・課題発見・意思決定の迅速化のためにBIツールを活用している企業が多いとわかります。企業全体のデータ活用力を高めることにもつながり、自社の目的に応じた使い方も可能です。
BIツール導入にかかる費用
BIツールの導入には、初期費用・ライセンス費用・運用保守費用などがかかります。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 導入設定やシステム構築、初期トレーニングなどにかかる費用 |
| ライセンス費用 | ユーザー数や機能に応じて発生する月額・年額料金。 例:ユーザー単位、サーバー単位、利用機能別で料金設定されることが多い |
| 運用・保守費用 | バージョンアップ対応、サポート、追加トレーニングにかかる費用 |
| 追加費用 | データコネクタやアドオン機能の利用、ユーザー数追加時にかかる費用 |
安価なクラウド型は無料または月額数千円程度から利用できますが、大規模なツールでは数百万円規模が必要となることもあるので事前のシミュレーションが欠かせません。また、導入費用だけでなくトータルコストも試算し、無理なくランニングできるか検討しましょう。
BIとAIの基礎知識

近年、BIとAIを組み合わせることで、より企業のデータ活用を効率化する動きが盛んになっています。BIは過去のデータを可視化して分析することに強みがありますが、AIを組み合わせることで未来予測・異常検知・自動インサイト提示など、より戦略的な分析が可能です。
AIとは何か
AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、学習・判断・推論・認識などの知的作業をコンピュータに行わせる技術のことです。
AIができることは、以下の通りです。
| AIができること | 内容 |
|---|---|
| 学習(Machine Learning) | 過去のデータから傾向や規則を学び、予測や分類を行う |
| 推論(Reasoning) | 学習した知識をもとに最適な判断や意思決定を行う |
| 認識(Recognition) | 画像や音声、テキストなどを理解・分類できる |
| 自動化(Automation) | 繰り返し作業や複雑な処理を自動で実行する |
データをもとにパターンを学習し、予測・判断・問題解決を自動で実行できるので、意思決定や業務改善などビジネスの現場でも多数使われるようになっています。
BIとAIの違い
BIとAIはどちらもデータを活用する技術ですが、役割やアプローチに違いがあります。
| 項目 | BI(Business Intelligence) | AI(Artificial Intelligence) |
|---|---|---|
| 目的 | 過去のデータを可視化・分析し、現状把握や意思決定を支援 | データから学習・予測・推論を行い、未来の意思決定や自動化を支援 |
| 分析手法 | 集計・グラフ化・ダッシュボードなどの可視化 | 機械学習、自然言語処理、画像認識などの高度な分析 |
| 適用例 | 売上や在庫のトレンド分析、KPI管理、経営レポート | 需要予測、異常検知、レコメンド、自動インサイト提示 |
| 使用者 | 経営層・現場担当者・データ担当者 | データサイエンティストやAI搭載BIツールを利用する現場担当者 |
| 出力結果 | 過去や現在のデータの傾向・状況を把握 | 未来予測、意思決定支援、問題解決の提案 |
つまり、BIは「過去・現在のデータを見える化して意思決定を支援するもの」、AIは「データから学習し未来を予測・提案して意思決定を支援するもの」と捉えるとわかりやすいでしょう。
BIとAIの相乗効果
BIツールで整理・可視化したデータにAIを組み合わせることで、単なる過去分析に留まらず、より精度の高い未来予測や迅速な意思決定ができます。
BIが提供する「見える化」と、AIが提供する「予測・自動分析」の両方を活用することで、相乗効果が発揮されるのがポイントです。
BIとAIの活用例は、以下の通りです。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| 売上予測の精度向上 | 過去の販売データをBIで整理し、AIが需要予測を自動算出する |
| 異常値・リスクの早期発見 | BIで統合した複数システムのデータをAIが解析し、異常パターンを検知する |
| 業務効率化 | レポート作成や分析の一部をAIが自動化し、現場担当者は意思決定に専念できる |
| 顧客分析・マーケティング施策の最適化 | BIで顧客データを可視化し、AIが購買傾向や行動パターンを予測する |
BIとAIを組み合わせることで、「データの可視化」と「予測・自動分析」がセットになり、意思決定の速度と精度が格段に向上します。
AI搭載BIツールの主な機能
AI搭載BIツールの主な機能は、以下の通りです。
以下でそれぞれ詳しく解説します。
データの集約
AI搭載BIツールでは、複数のデータソースから情報を集約し、一元管理できる機能があります。散在していたデータを統合しながら分析・管理することが簡単になり、正確な意思決定につなげられます。
データ集約で期待されることは、以下の通りです。
- データベース、スプレッドシート、クラウドサービスなど複数のソースを統合する
- データ形式や単位の違いを自動で整形・変換する
- 部門やシステムごとに分かれた情報も一元管理する
- 集約後のデータをもとに、ダッシュボードやレポート作成をする
データの可視化
AI搭載BIツールには、データをグラフ、チャート、ダッシュボードで視覚的に整理する機能があります。複雑な数値や膨大なデータも直感的に理解でき、経営層や現場担当者が状況を一目で把握できます。
データの可視化で期待されることは、以下の通りです。
- 棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ・ヒートマップなど多様なチャートを作成する
- KPIや指標をダッシュボード上で統合表示する
- データのフィルタリングやスライスで必要な情報に素早くアクセスする
- モバイルやタブレットでも見やすく、場所を問わず確認する
レポートの作成
レポート作成機能を使えば分析結果を関係者にわかりやすく共有でき、意思決定や業務改善のスピードを向上できます。分析結果を社内で共有し、迅速な意思決定につなげたいときにも役立ちます。
レポート作成で期待されることは、以下の通りです。
- 定期レポートを自動生成し、手作業の負担を削減する
- 分析結果をグラフや表、ダッシュボードで可視化して整理する
- PDFやExcelなど多様な形式でエクスポートする
- 部門やチームごとにカスタマイズしたレポートを作成する
データマイニング
データマイニングとは、膨大なデータの中から 有用なパターンや傾向、規則性を自動的に発見する手法のことです。BIツールでも膨大なデータの中から有益なパターンや傾向を自動で抽出できるため、単純な集計や可視化では見えないデータの潜在的な意味や関係性を見出せます。
データマイニングで期待されることは、以下の通りです。
- 大量の取引データや顧客データを高速に分析する
- 異常値やトレンドを自動検出する
- 将来の需要予測やマーケティング施策の最適化に使う
- 分析結果をダッシュボードやレポートに反映し、社内共有に使う
プランニング
需要予測やシナリオ分析を通じて将来の計画を立てるシーンで活用されることも多いです。過去のデータやトレンドをもとにAIが分析することで、より精度の高い予測や戦略的な意思決定を支援します。
プランニングで期待されることは、以下の通りです。
- 過去の売上データや市場動向をもとに需要予測を自動算出する
- 複数のシナリオを比較し、リスクや成果をシミュレーションする
- 在庫管理、生産計画、予算策定などに活用する
- ダッシュボード上で予測結果を可視化し、迅速な意思決定を支援する
AI搭載BIツールを導入するメリット

AI搭載BIツールを導入するメリットは以下の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自動化により意思決定のスピードが上がる
AI搭載BIツールを導入すると、データ収集・分析・レポート作成のプロセスを自動化できます。結果、分析のスピードが上がり、意思決定も速やかになるのがメリットです。
従来では数時間、場合によっては数日かかっていた判断も瞬時に実行できるのがポイントです。例えば、売上データや在庫状況の変化をリアルタイムで把握し、適切な在庫補充や販売施策の調整を即座に決定するなどフレキシブルな動きができます。
他にも、マーケティングデータや顧客行動データを分析して需要の変化や購買傾向を予測し、タイムリーなキャンペーン施策に活用するなどの工夫も可能です。
業務の効率化と意思決定のスピード向上を同時に実現する戦略的ツールとして活用できます。
データ分析の属人化を抑えられる
AI搭載BIツールは直感的な操作性や自動分析機能を備えており、専門知識がなくても幅広い社員がデータを活用できる環境を構築できます。
今までは「ハイレベルなデータサイエンティストでないと分析できない」「担当者によって分析のクオリティが違う」などの問題が生じがちでしたが、誰でも使える手軽なBIツールであれば属人化を抑えられるのがメリットです。
例えば、営業担当者や現場スタッフでもドラッグ&ドロップ操作でグラフを作成したり、AIが示す傾向や異常値をもとに判断したりできるため、分析作業が特定の人物に依存する状況を防げます。
誰が操作しても同じ品質のアウトプットが得られるので、分析業務の属人化を防ぎ、組織全体のデータ活用力を底上げする効果をもたらします。
データ管理・共有がしやすくなる
AI搭載BIツールを導入すると、データの管理や共有が格段にしやすくなります。クラウド環境のBIツールであればオフィスでも外出先でも同じデータにアクセスできるので、社内での情報格差が生まれることもありません。
例えば、営業部門が現場の販売実績を入力した情報が即座に経営層やマーケティング部門でも確認できます。誰もがリアルタイムに最新データへアクセスでき、組織全体で共通認識を持ちたいときにも便利です。
データ分析の精度が上がる
AI搭載BIツールは扱えるデータ量も多く、処理能力も高いため、データ分析の精度が上がります。重要なパターンを見落としたり、予測の精度が十分でなかったりすることもなく、ハイレベルな分析がしやすくなるのでメリットです。
結果、人間では気づきにくい相関関係やトレンドを抽出できるなど、事業に役立つエッセンスを多く得られるのがポイントです。在庫の適正水準を自動で算出したり、今後どの商品が売れるのかを高い精度で予測したり、分析できる内容も増やせます。
つまり、AI搭載BIツールの導入は単に分析業務の効率化をもたらすだけでなく、競争力の源である「高度な分析力」を得るきっかけになるのです。
AI搭載BIツール導入の注意点

AI搭載BIツールは高度な分析や効率的な意思決定を可能にする一方、注意点もあります。
以下では、AI搭載BIツール導入の注意点を解説します。
想定外のトラブルやコンプライアンス違反を招かないよう、事前にチェックしておきましょう。
ツールの利用には知識が必要となる
AI搭載BIツール導入は幅広い人が使えるツールですが、ある程度の知識は必要です。例えば、複雑なデータ分析や高度なレポート作成を行う場合、統計やデータサイエンスに関する最低限の知識は求められるでしょう。単語や用語もわからないまま進めてしまうと、想定している分析にならないことも出てきます。
「誰でも使いやすい」ことを売りにしているツールであっても、実際には適切なデータ準備や設定が欠かせません。社内での教育体制を整え、データ分析に精通した担当者を配置することがポイントとなります。
初期費用とランニングコストがかかる
AI搭載BIツールを導入する際には、初期費用だけでなくライセンス料やクラウド利用料なども必要です。
ライセンス料やクラウド利用料は毎月定額で発生することが多く、ランニングコストとして収益を圧迫する可能性があるので注意しましょう。コストを正しく把握せずに導入すると「想定以上に費用がかかった」という事態になりかねません。
ツールによっては利用規模が拡大するほどコストが増加するため、事前に総額を見積もり、自社の予算感に合うかを確認することがおすすめです。
不十分なデータでは分析ができない
AI搭載BIツールは高性能な分析機能を備えていますが、前提となるデータが不十分だったり正確でなかったりする場合、効果を発揮できません。入力データが欠損していたり、フォーマットが統一されていなかったりすると、誤った分析結果や偏った予測につながるリスクがあります。
特に、AIを活用する場合、学習させるデータの質が成果に直結します。導入前に自社のデータ環境を見直し、適切なデータ基盤を整えておきましょう。
ツールの操作性によっては業務効率が落ちるおそれがある
操作性が悪いAI搭載BIツールを選んでしまうと、却って業務効率が落ちるリスクがあるので注意しましょう。直感的に使えないUIや複雑な操作手順が必要なツールでは社員が慣れるまでに時間がかかり、分析業務が滞ります。
また、社内で十分に活用されないまま「使いにくいツール」として形骸化するリスクもあるため要注意。導入前にはデモ版やトライアルを利用し、「実際の利用者にとって使いやすいか」の視点で使い勝手を試してみましょう。
AI搭載BIツールを活用するためのコツ
AI搭載BIツールは、導入するだけでは十分な成果を得ることができません。ツールの特性を理解し、社内での運用体制を整え、適切なデータを継続的に活用することが重要です。
AI搭載BIツールを活用するためのコツは以下のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
運用のルールを決めておく
AI搭載BIツールを効果的に活用するためには、事前に運用ルールを整備しておくことが欠かせません。データ入力の方法・更新のタイミング・利用フローなどを統一しておくと、データの形式や品質が揃います。
反対に、ルールが曖昧なまま運用を始めてしまうと、部署ごとに異なるデータ形式や管理方法が混在しやすくなるので注意しましょう。正確な分析ができない原因となり、データが増えれば増えるほど統一の工数が増すことになってしまいます。
ツールの活用方法を定期的に見直す
AI搭載BIツールは導入して終わりではなく、事業環境や業務状況の変化に応じて定期的に活用方法を見直しましょう。市場動向や社内業務の変化に合わせて、ダッシュボードの表示内容や分析指標を定期的に更新することがポイントです。
常に最新の業務フローに合わせて使えるツールになるため、「画面が古くて使えない」「時代に合わないツールになった」などのトラブルを防げます。
データ分析ができる人材を用意しておく
データ分析の知識やツール操作に精通した人材を社内に確保しておくことも重要です。ツールを使ったことがある担当者がいれば、導入時の設定・ダッシュボード作成・分析フローの整備などがスムーズに進みます。
また、社内での教育やサポート役としても機能するため、他の社員が安心してツールを活用できる環境づくりにも役立ちます。専門人材を中心に運用ルールや指標設定を整備しましょう。
積極的な活用支援を行う
AI搭載BIツールを使いこなすには、ただ導入するだけでなく「ツールの利用を促す支援体制を整える」ことも大切です。勉強会や操作研修を定期的に実施したり、丁寧なオンボーディングを意識したりしながら、現場に浸透させていきましょう。
また、活用事例の共有やQAセッションを設けることで、疑問や課題を早期に解消していく方法もあります。せっかく導入したツールが形骸化しないよう、使い方の事例紹介なども進めるのがポイントです。
人間による判断も適宜加える
AI搭載BIツールは企業の意思決定や分析支援に役立つツールですが、妄信したり依存したりするのは危険です。
BIツールはあくまでも道具のひとつであり、分析や結論が100%正しいとは限りません。あくまで参考情報に留め、最終的な意思決定には人間による判断を加えることが不可欠です。
AIの提案を無条件に受け入れると、データの偏りや誤りに基づいた判断をしてしまうリスクがある点に注意しましょう。過去の経験や現場の判断も、時には必要です。
【まとめ】AIとBIの組み合わせでデータ分析を充実させよう
AI搭載BIツールを活用すると、従来のBIだけでは難しかった高度な分析・予測・業務の自動化が実現します。AIによる需要予測や異常検知などの機能も活用できるので、自社の業務内容に合わせて分析業務を高度化していきましょう。
目的に合うAI搭載BIツールを導入し、効率化や生産性の向上を狙うのがおすすめです。