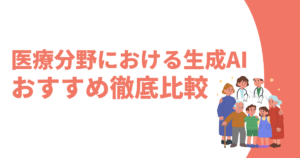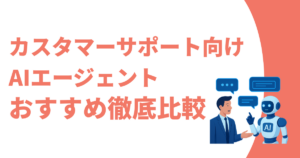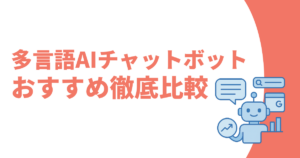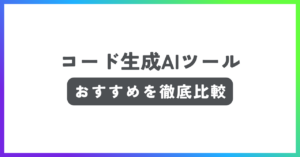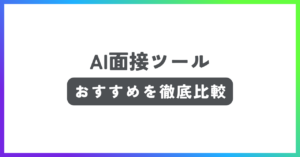【26年1月最新】おすすめのAI文字起こしツール3選を比較!選び方や活用事例も解説
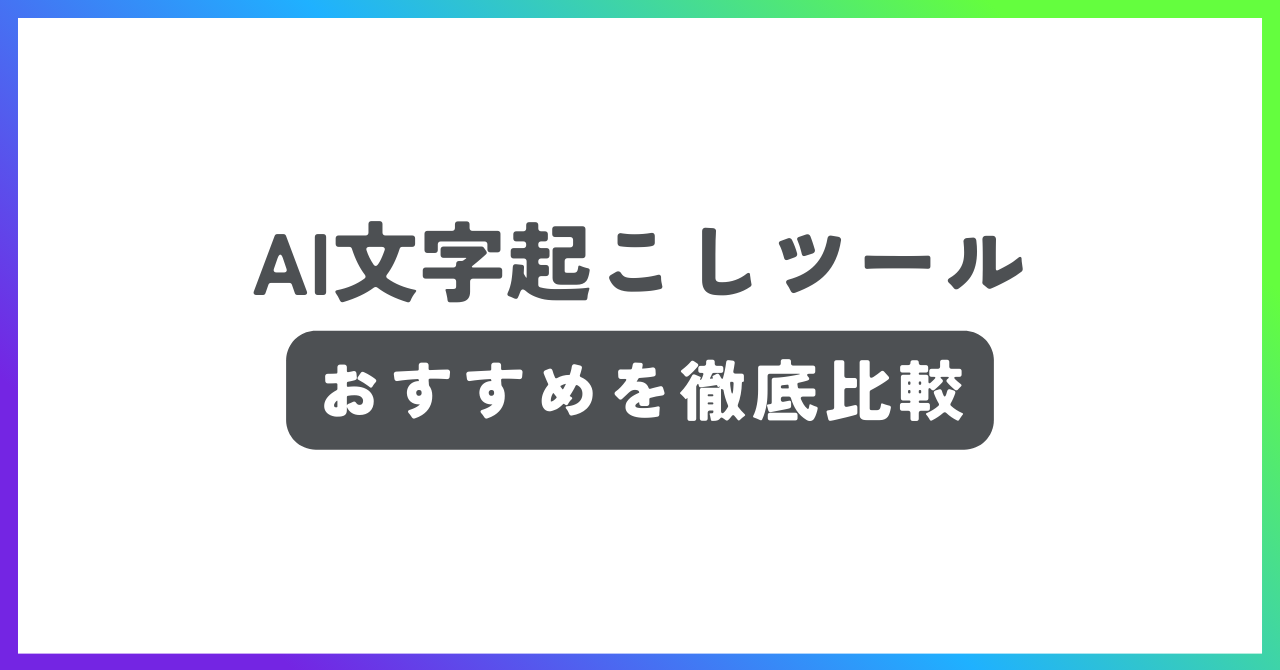
AI技術の発展により、会議やインタビュー、動画編集などで欠かせない文字起こし作業を自動化できるツールが増えています。近年では、リアルタイムで高精度な変換が可能なAI文字起こしツールが登場し、業務効率化の手段としても注目されています。
一方で、AI文字起こしツールごとに精度や料金体系、対応言語、セキュリティ面などが異なるため、迷うケースも少なくありません。
本記事では、おすすめAI文字起こしツールを比較し、選び方のポイントや活用事例を分かりやすく解説します。議事録作成や取材業務を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください。
おすすめのAI文字起こしツール3選
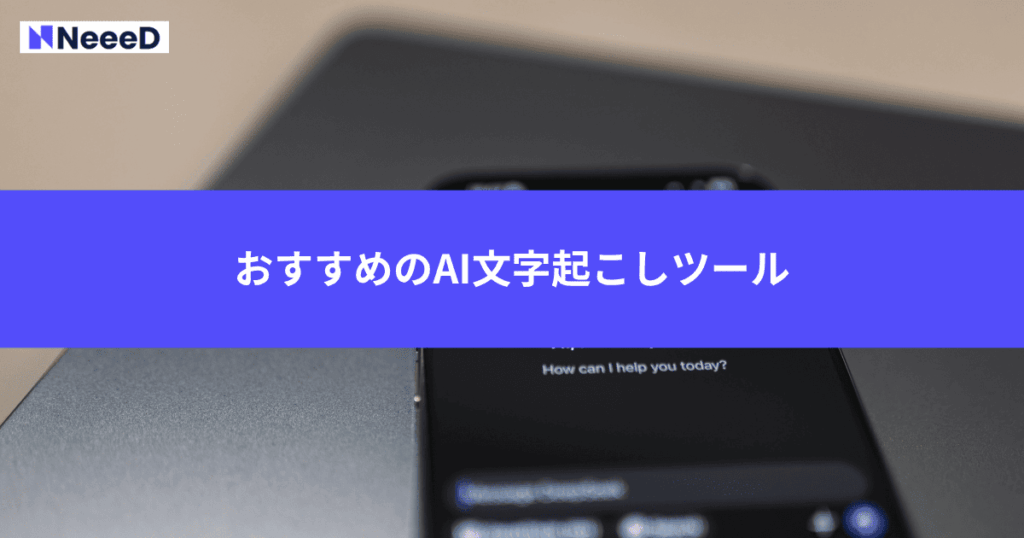
まずは、おすすめのAI文字起こしツールを3つ厳選しました。
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| notta | 高精度な日本語対応とリアルタイム文字起こし機能を備えたツール |
| Texter | AIによる自動文字起こしに加え、話者識別や要約など編集支援機能が充実 |
| 文字起こしさん | 無料AI文字起こしツールで、コストを抑えて音声のテキスト化が可能 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
notta

| 料金プラン | プレミアム 1,185円/月 フリー 0円 ビジネス 2,508円/月 エンタープライズ 要相談 |
|---|---|
| 主な機能 | AI要約機能 スケジュール連携 画面録画対応 議事録作成支援 翻訳機能(58言語対応) カレンダー連携 チーム共有・管理機能 営業支援AIエージェント |
| 強み | Web版・アプリ版・Chrome拡張など多様な環境で動作し、インストール不要で利用できる |
| 導入実績 | JUREN株式会社 株式会社幻冬舎メディアコンサルティング 遠州鉄道株式会社など |
| 会社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ3階 |
Nottaは、会議やインタビュー、オンライン商談など、ビジネスシーンでの文字起こしを効率化できるAIツールです。リアルタイムでの音声認識に加え、録音データのアップロードにも対応しており、発言内容を自動でテキスト化します。
AI要約機能を使えば、議事録や報告書の作成もスピーディーに完了できます。また、Googleカレンダー連携やチーム共有機能により、社内での情報共有もスムーズです。
セキュリティ面ではISO27001を取得しており、法人利用にも適した安心設計となっています。手間のかかる会議録作成を自動化したい企業におすすめのツールです。
Texter

| 料金プラン | Free 0円 Premium M 1,500円/月 Premium M+ 3,000円/月 Premium Y 7,400円/年 |
|---|---|
| 主な機能 | 音声録音→テキスト変換対応 発言者識別機能 編集・校正支援機能(誤認識修正など) 日本語対応(母語での文字起こし精度) 録音データからのアップロード変換対応 |
| 強み | 日本語に強い高精度の音声認識技術と発言者識別機能を備えている |
| 導入実績 | 要問い合わせ |
| 会社所在地 | 要問い合わせ |
Texterは、日本語音声の文字起こしに特化したAIツールで、高い精度とスピードを両立しています。発言者の識別機能を搭載しており、会議やインタビューなど複数人の会話でも内容を整理しやすいのが特徴です。
また録音データのアップロードはもちろん、リアルタイムでの音声認識にも対応しています。変換後のテキストはそのまま編集や整形が可能で、議事録作成や取材原稿の効率化に最適です。
直感的に使えるシンプルなUI設計で、初めて導入する方でも安心して利用できます。z
文字起こしさん

| 料金プラン | フリー・ライト 0円 ベーシックプラン 1,100円/月 バリュープラン 2,200/月 プレミアムプラン 3,300円/月 |
|---|---|
| 主な機能 | ファイルのアップロード変換 専門用語対応による認識精度の向上 1ファイルあたり最大時間の制限対応 複数言語での文字起こし対応 無料で一定時間分の文字起こし体験 ログなし・非学習設定でプライバシー保護 テキストの編集・ダウンロード |
| 強み | 高精度かつセキュリティ性の高く、低コストで手軽に利用できる |
| 導入実績 | 要問い合わせ |
| 会社所在地 | 〒 649-1201 和歌山県日高郡日高町原谷521-1 |
文字起こしさんは、音声・動画・画像データを簡単にテキスト化できるWebベースのAI文字起こしサービスです。専門用語を含む音声も精度高く変換できるよう設計されており、業務利用にも耐える認識力があります。
無料プランでは毎日一定時間分を試せるため、導入前に性能を確認できるのも魅力です。
ログなし・非学習モードでデータを残さずに処理できるので、機密性を重視した利用にも適しています。
また、 複数言語対応や編集・ダウンロード機能も備えており、使い勝手も十分です。コストを抑えながら文字起こしを導入したい企業や担当者にとって、有力な選択肢となるツールです。
AI文字起こしツールの選び方
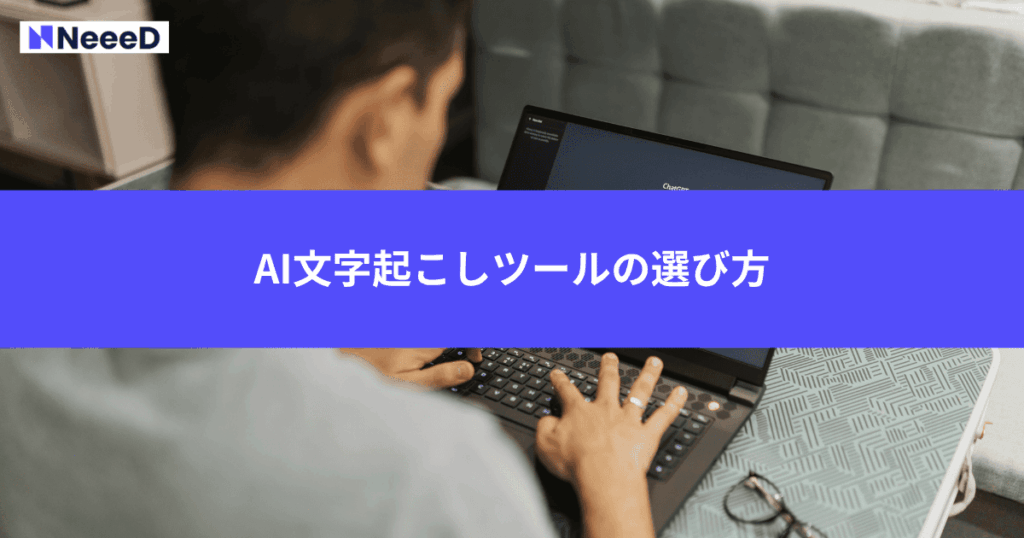
AI文字起こしツールを選ぶ際は、どのような場面で使うのかを明確にすることが大切です。自社の業務フローに適したツールを選ぶことが成功のポイントといえます。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
音声認識の精度が高いツールを選ぶ
AI文字起こしツールを導入する際に、重視すべきなのが音声認識の精度です。認識精度が高ければ、会議やインタビューなどの長時間音声でも正確なテキスト化が可能になります。
特に雑音の多い会議室や複数人が話す環境では、ノイズ耐性や話者ごとの声の聞き分け性能が重要です。精度が低いツールを選んでしまうと、修正作業に時間がかかり、結果的に業務効率が下がってしまいます。
導入前には、無料トライアルやデモ機能を活用し、実際の音声で精度を確認するのがおすすめです。高精度のツールを選ぶことで、修正コストを抑え、業務の生産性を大幅に向上させられます。
利用シーンに必要な機能がそろっているか確認する
AI文字起こしツールには、リアルタイム文字起こし型や音声アップロード型など、さまざまなタイプがあります。自社の利用目的や業務フローに合った機能が備わっているかを確認することが大切です。
チームで議事録を共有したい場合は、共同編集機能やクラウド共有機能が便利です。また、話者識別機能や自動保存、編集補助ツールなどがあると作業の効率化につながります。
出力フォーマット(テキスト・Word・CSVなど)にも違いがあるため、社内で扱いやすい形式を選ぶと良いでしょう。実際の業務フローを想定しながら、機能の充実度を見極めることがポイントです。
対応言語や翻訳機能の有無をチェックする
グローバル化が進む現在、多言語対応や翻訳機能の有無も重要な比較ポイントです。英語だけでなく、中国語、韓国語、フランス語など複数言語の文字起こしに対応しているツールを選ぶと、海外拠点や外国人スタッフとの業務連携がスムーズになります。
また、文字起こしと翻訳が一体化したツールであれば、別途翻訳作業を行う必要がなく、工数削減にもつながります。ただし、言語によって精度にばらつきがあるため、利用目的に合う範囲で実用性を確認することが大切です。
翻訳の精度と文字起こしの精度は別物として、それぞれ評価しましょう。
セキュリティ性やデータ保護体制を重視する
会議や取材などで扱う音声データには、機密情報や個人情報が含まれる場合があります。そのため、セキュリティ対策がしっかりしたツールを選ぶことが不可欠です。具体的に以下の有無を確認します。
- 録音データの暗号化
- 保存期間の明示
- データ削除機能
また、運営会社がどの国にサーバーを置いているか、データ保管場所が日本国内か海外かも重要な判断基準です。企業の情報セキュリティポリシーに沿って導入できるツールを選ぶことで、安心して業務に活用できます。
利用前にプライバシーポリシーや利用規約にも必ず目を通し、データ管理体制を把握しておくことが大切です。
料金プランと無料トライアルの有無を比較する
AI文字起こしツールの料金体系は、月額制・従量課金制・買い切り型などさまざまです。利用頻度や録音時間によってコストが変わるため、必要な範囲に応じたプランを選ぶことができます。
無料プランを提供しているツールもありますが、録音時間や機能に制限があるケースが多いため利用する際は注意が必要です。
有料プランを選ぶ場合、長時間録音・複数アカウント利用・チーム共有などに対応しているかを確認しましょう。導入前には無料トライアルを利用して、操作感や精度、速度などを実際に体験することをおすすめします。費用だけでなく、業務効率の向上という観点からも総合的に判断することが重要です。
AI文字起こしとは?
AI文字起こしとは、音声認識技術を活用して人の話した内容を自動でテキスト化する仕組みです。会議や取材、インタビュー、動画コンテンツなどの音声データを解析し、短時間で正確に文章へ変換できます。
従来の手作業による文字起こしと比べて作業時間を大幅に削減できるため、ビジネスの効率化に直結します。また、リアルタイムでの議事録作成や字幕生成など、活用の幅が広がる点も特徴です。
近年ではAIの精度向上により、企業のバックオフィス業務やメディア制作現場などでも導入が急速に進んでいます。人が聞き取り・入力を行う負担を減らし、より生産的な業務へ時間を使えるようになるのがAI文字起こしの最大の利点です。
AI文字起こしの仕組み
AI文字起こしは、音声認識技術(ASR)と自然言語処理(NLP)を組み合わせて構築されています。
まず、AIが音声の波形データを解析し、音の特徴から単語や文章を特定します。次に、文法や文脈に基づいて誤変換を修正し、自然な文章へと整える工程が行われます。雑音を除去するノイズキャンセリング機能や、複数話者を区別するスピーカー分離機能も活用できます。
AI文字起こしのプロセスの精度向上には、機械学習やディープラーニングといったAI技術が欠かせません。学習を重ねることで、人間の会話に近い認識能力を獲得し、より自然で正確な文字起こしが可能です。
AI文字起こしの活用事例
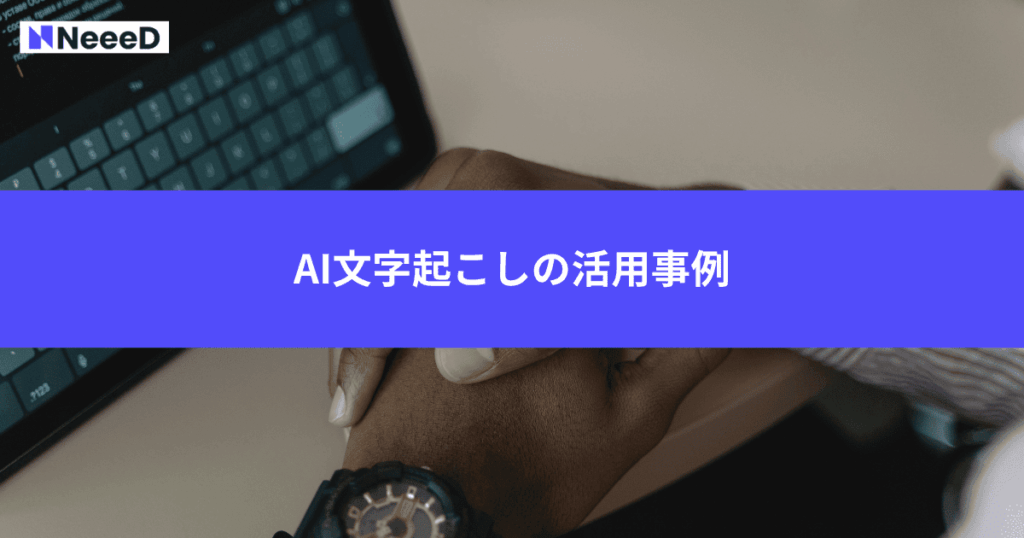
AI文字起こしツールは、単に会議をテキスト化するだけでなく、さまざまな業務に応用できる汎用的なツールです。
会議やミーティングの議事録作成
AI文字起こしの代表的な活用シーンが、会議やミーティングでの議事録作成です。リアルタイムで音声を文字化できるツールを使えば、発言内容をすぐに記録し、後からの修正も簡単に行えます。
手動でメモを取る場合と比べて、抜け漏れや記録ミスを防ぎつつ、作業時間を大幅に短縮できます。発言者の識別機能があれば、誰が何を発言したかを自動で整理でき、議論の流れを後から確認するのも容易です。
要約機能を活用すれば、重要ポイントを自動抽出して共有資料にも転用可能です。活用することで、社内報告やチーム内共有のスピードが格段に向上します。
インタビューや取材記事の作成
インタビューや取材記事の編集業務でも、AI文字起こしは大きな効果を発揮します。録音した音声を自動でテキスト化することで、ライターや編集者の文字起こし作業を大幅に削減可能です。
タイムライン付きで書き起こせるAI文字起こしツールを使えば、該当箇所をすぐに再生して内容を確認でき、編集作業のスピードが上がります。また、手動入力による聴き漏らしや誤記も防げるため、記事品質の安定にもつながりやすいです。
さらに、AIによる要約やキーワード抽出機能を活用することで、記事構成を組み立てる手間も省けます。取材から納品までの工数を減らし、短納期対応にも貢献するのが大きなメリットです。
研修やセミナー内容の資料化
研修やセミナーなど、講義形式のイベントでもAI文字起こしツールが活用されています。講師の発言内容をテキスト化することで、受講後の振り返り資料や社内教育用の報告書をスムーズに作成できます。
また動画配信の字幕生成や、オンライン研修のアーカイブ化にも応用できる点が魅力です。特に、複数拠点での同時研修や遠隔参加が多い企業では、参加できなかった社員への情報共有手段として有効的といえます。
自動文字起こしにより、講義内容の再利用性が高まり、教育コストの削減にもつながります。研修やセミナーの効果の最大化を目指す企業にとって、AI文字起こしは欠かせないツールです。
顧客対応や面談記録の保存
コールセンターや営業現場など、顧客対応の現場でもAI文字起こしは活躍しています。
通話や商談の音声を自動で記録・テキスト化することで、対応履歴を可視化でき、情報共有のスピードを高めます。記録を分析すれば、クレーム対応の改善やトークスクリプトの最適化にも活用可能です。
AIによる感情分析やキーワード抽出機能を併用すれば、顧客満足度の向上にも寄与します。記録を蓄積していくことで、対応品質を標準化し、属人的な業務からの脱却も可能です。
また、扱うデータには機密情報も含まれるため、セキュリティ対策の整ったツールを選ぶことが重要です。
不在者や関係者への情報共有
AI文字起こしを活用すると、会議や打ち合わせの内容をすぐに共有できるようになります。
文字化された議事録をメールや社内チャットに添付すれば、出席できなかったメンバーも内容を把握することが可能です。会議の全体像を正確に伝えられるため、認識のずれを防ぎ、チーム全体の理解度を高められます。
特にリモートワークやハイブリッド勤務が定着した昨今において、情報共有のスピードは生産性に直結します。AI文字起こしを活用すれば、伝達のタイムロスを最小限に抑え、スムーズな意思決定を実現することが可能です。
動画字幕の自動生成
AI文字起こしは、動画制作や配信コンテンツにも幅広く応用されています。音声から自動で文字を抽出し、字幕として付与することで、視聴者の理解を深める効果があります。
特に、YouTubeや社内研修動画など音声コンテンツを多用する企業にとっては大きな時短手段といえます。また、音声検索対応やアクセシビリティ向上にも寄与し、より多くのユーザーに情報を届けることが可能です。
多言語翻訳機能を活用すれば、海外向けの動画展開も容易になります。動画制作とAI技術を組み合わせることで、発信力の高いコンテンツ運用が期待できるでしょう。
アイデアや音声メモの整理
AI文字起こしは、会議や業務だけでなく個人の思考整理にも活用可能です。例えば移動中や出先で音声メモを録音し、自動でテキスト化することでアイデアを逃さず整理できます。
発想の断片を文字として蓄積できるため、企画書や議事メモの作成ベースにもなります。要約機能やタグ付けを活用すれば、過去の発言や思考を簡単に検索・分類することも可能です。
手書きメモよりもスピーディで、後から見返しやすい点も魅力の一つです。忙しいビジネスパーソンにとって、AI文字起こしは思考を可視化するパートナーとして役立ちます。
AI文字起こしを使うメリット
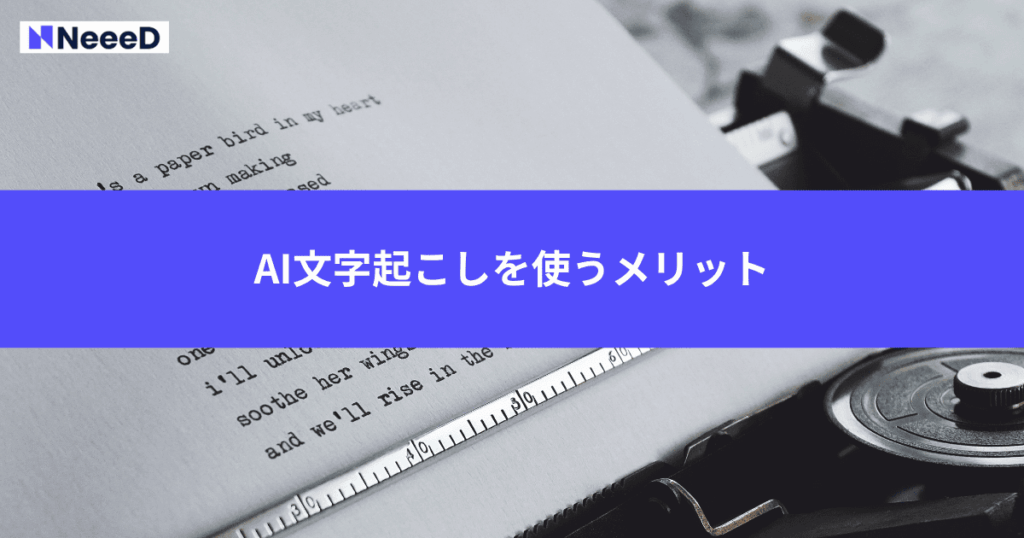
AI文字起こしツールを導入することで、記録作業の効率化だけでなく、業務全体の生産性向上にもつながります。
AI文字起こしを導入する主なメリットを具体的に解説します。
手作業に比べて作業時間を大幅に短縮できる
AI文字起こしツールを使えば、録音を再生しながら手入力していた従来の方法に比べて、作業時間を劇的に短縮できます。
現在は、1時間の音声データを、数分〜10分程度で自動的に文字化できるツールも登場しています。手動入力による反復作業や確認工数が削減され、より重要な編集・分析業務に時間を充てることが可能です。
また、録音を止めて再生を繰り返す手間もなく、効率的に業務を進められます。AIが自動的に文脈を補完するため、文章の整形にかかる手間も軽減されます。作業者の負担を減らしつつ、生産性を高めたい現場に適切なツールです。
高精度な認識で修正作業の負担を減らせる
新しいAI文字起こしツールは、ディープラーニングによる学習精度の向上により、誤変換が少なくなっています。句読点の自動補完や話者識別、要約機能などが搭載されており、精度だけでなく実用性の面でも進化しています。
雑音がある環境や専門用語の多い会話でも、高い認識性能を維持できるツールも多いです。誤変換が少ないほど修正作業の時間が減り、結果的なトータルの作業効率が向上します。
また、AIが会話の文脈を理解して変換するため、自然な文章が生成されるのも特徴です。精度と手直しのしやすさを両立できるツールを選ぶことが、導入効果を最大化するポイントです。
外注に比べてコストを削減できる
AI文字起こしツールを利用すれば、外部の文字起こし代行サービスに依頼する場合と比べて大幅にコストを抑えられます。
従量課金制のサービスでは1時間あたり数千円かかるケースもありますが、AIツールなら月額数千円程度で使い放題のプランがほとんどです。無料プランやトライアルを提供しているツールも多く、予算に合わせて柔軟に選択できます。
社内の業務フローに組み込むことで、継続的に利用できる点も魅力です。特にフリーランスや小規模チームでは、コストパフォーマンスの高さが業務効率化に直結します。初期投資を抑えながら、品質の高い文字起こしを実現できるのがAI文字起こしツール導入の強みです。
多言語対応で国際的な場面でも活用できる
AI文字起こしツールの進化により、多言語対応が可能な製品が増えています。英語・中国語・韓国語などに対応するツールを導入すれば、海外拠点との会議や外国人顧客との商談にもスムーズに対応できます。
さらに、自動翻訳機能を組み合わせることで、文字起こしと翻訳を同時に行うことも可能です。海外取材や国際カンファレンスなど、グローバルな業務でも活用範囲が広がります。
日本語以外の音声でも高い認識精度を誇るツールが増えており、国際的なビジネス現場での利便性が高まっています。多言語の壁を越えて情報共有をスムーズにする点も、AI文字起こしツール導入のメリットです。
テキスト化により検索・分析が容易になる
AIで文字起こしされたデータは、検索・共有・分析といった二次利用がしやすくなる点が特徴です。発言内容をキーワードで検索できるため、特定の話題や発言箇所をすぐに確認できます。
また、タグ付けや要約機能を活用すれば、過去の会議や顧客対応の履歴を整理・分析することも可能です。テキスト化されたデータはナレッジ資産として社内に蓄積でき、業務マニュアルやレポート作成にも再利用できます。
データを活用することで、組織全体の知見共有や改善サイクルを加速させることができます。AI文字起こしは単なる記録ツールではなく、情報を活かす仕組みを支える重要な基盤です。
AI文字起こしのデメリット
AI文字起こしツールは多くの業務を効率化できる一方で、注意すべき点も存在します。
5つにまとめたので、それぞれ確認していきましょう。
雑音や早口があると精度が落ちやすい
AI文字起こしは高性能化が進んでいるものの、録音環境が悪い場合や複数人が同時に話す場面では認識精度が低下しやすい傾向があります。早口や独特な訛り、専門用語を多用する会話では誤変換が増えやすいです。
バックグラウンドノイズやマイクの位置なども精度に影響するため、録音時の環境を整える工夫が欠かせません。また、会議室の音響設定や発話者ごとの距離を調整することで、一定の改善が期待できます。
AIによる補正機能はあるものの、精度が不安定な場面では一部手動での修正が必要になることもあります。明瞭な発声を意識し、ツールの特性を理解して活用することが重要です。
長時間音声では誤変換や抜けが発生することがある
長時間の音声データでは、処理の途中で一部が欠落したり、誤変換が増えることがあります。特に一括アップロード型のツールでは、音声の品質や話者数によって精度にばらつきが出ることも少なくありません。
長尺データを扱う場合は、一定時間ごとに分割して処理するなどの工夫が求められます。また、要点抽出や要約機能を併用することで、全体の確認工数を減らすことも可能です。
長時間コンテンツでは、精度だけでなく処理速度やファイル容量制限も確認しましょう。業務で安定して使うためには、AI文字起こしツールの仕様や処理能力を事前に把握することが重要です。
完全自動化は難しく最終確認が必要になる
AI文字起こしは便利なツールですが、現状では100%正確な自動化はまだ難しいといえます。文脈の解釈や話し言葉のニュアンスなど、人間の判断が必要な部分は残りやすいです。
そのため、最終的には人の目による確認・修正を行うことが前提となります。誤字・脱字や文法の不自然さを見逃さないよう、レビュー工程を省略しないことが大切です。
また、編集機能やコメント機能を備えたツールを活用すれば、チームでのチェック作業も効率化できます。AIの自動化に頼りすぎず、最終品質を確保する運用体制を整えることが理想です。
セキュリティ面でのリスクに注意しなければならない
AI文字起こしツールでは、録音データの中に機密情報や個人情報が含まれることも少なくありません。特にクラウド型のサービスでは、データが外部サーバーに保存されるため、情報漏洩のリスクを十分に考慮する必要があります。
AI文字起こしツールの選定時には、暗号化通信やデータ削除機能、アクセス制御などのセキュリティ対策を必ず確認しましょう。そして、国内サーバーで運用されているかどうかも判断基準の一つです。
また、企業としては社内規定や情報管理ポリシーに沿った利用を徹底することも重要なポイントです。利便性と安全性のバランスを意識して導入を進めることが求められます。
無料プランは時間や機能に制限がある
多くのAI文字起こしツールには無料プランが用意されていますが、録音時間・保存容量・アップロード件数などに制限があるケースが一般的です。そのため、長時間の議事録作成や商用利用を目的とする場合は、有料プランへの切り替えが前提となります。
無料版では精度や出力フォーマットに制約がある場合もあり、業務レベルでの利用には不向きなことが多いです。導入前に料金体系を比較し、自社の利用目的に合ったプランを選びましょう。
まずはトライアルを活用して、実際の操作感や精度を確認してから検討すると失敗を防げます。費用面だけでなく、機能面でのバランスを重視して判断することがポイントです。
【まとめ】自社に合ったAI文字起こしツールを選んで効率化しよう
AI文字起こしツールは、会議や取材などの音声データを効率的にテキスト化し、業務の生産性を大きく向上させます。単なる作業の自動化にとどまらず、情報共有のスピード向上やコスト削減にもつながる点が大きな魅力です。
導入を検討する際は、活用目的や業務の特性に応じて複数のツールを比較することが大切です。精度・機能・コスト・セキュリティといった複数の観点から総合的に判断することで、自社に最適な選択ができます。
まずは無料トライアルを活用し、実際の使用感や精度を確認しながら運用に取り入れていくのが効果的です。AI文字起こしを上手に活用し、日々の業務をよりスマートで効率的なものにしていきましょう。