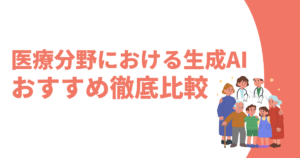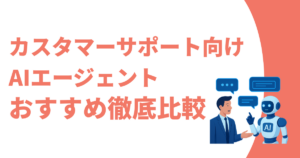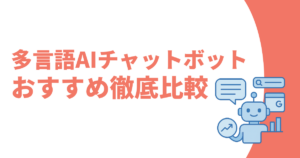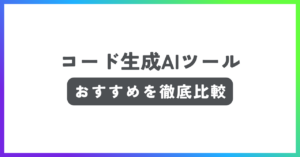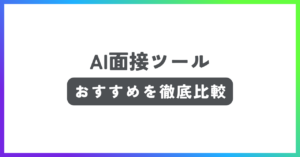【26年1月最新】おすすめのAI研修企業3選を比較!メリットや選ぶ時のポイントも解説
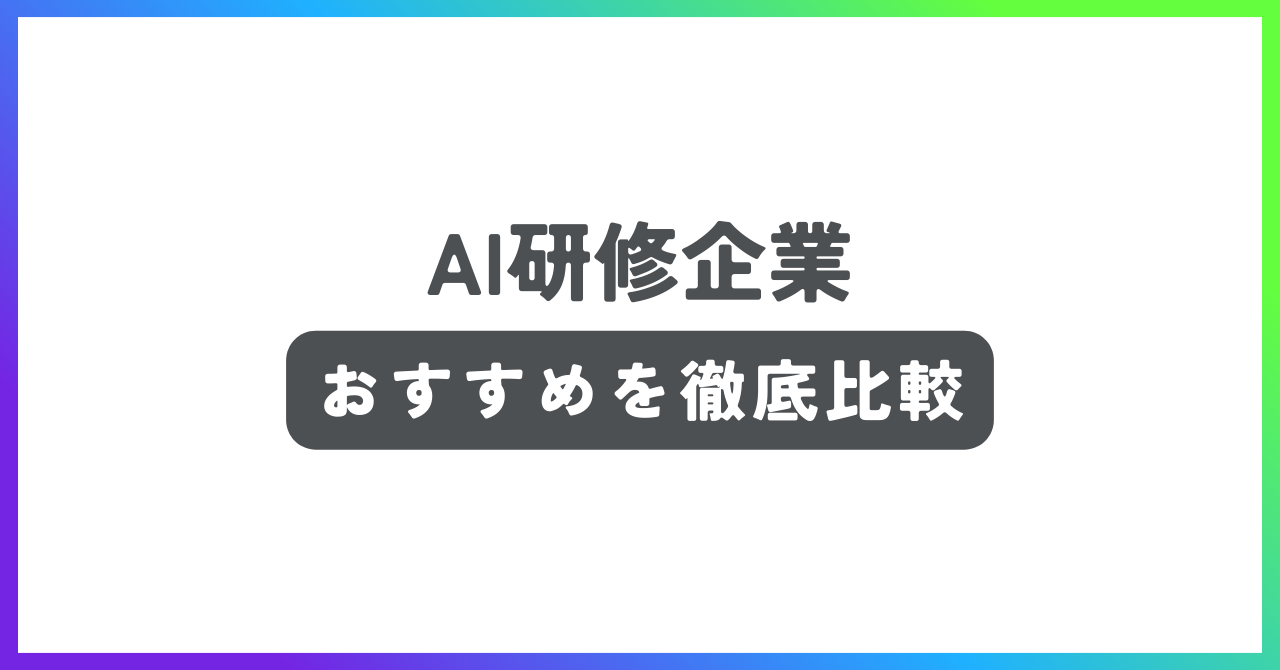
DXや生成AIの活用が進む現在、社員のリテラシー向上やAIの実務活用力の強化を目的としたAI研修が、多くの業界で注目を集めています。
しかし、「どの研修会社を選べばいいのか」「自社の課題に合った研修内容なのか」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、実績豊富なおすすめのAI研修企業3選を紹介します。また、AI研修の種類や選ぶポイント、費用相場まで解説しているので、AI研修の比較検討の際にお役立てください。
おすすめのAI研修企業3選
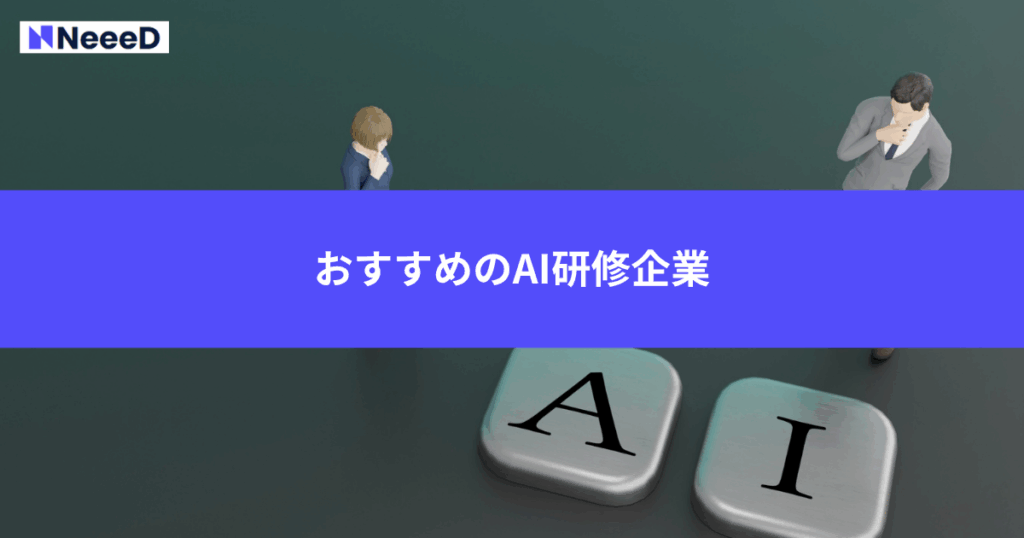
まずはAI研修のおすすめ企業を3社紹介します。
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| 株式会社キカガク | AI・機械学習領域で企業向けカスタマイズ研修からオンラインスクールまで対応 |
| トレノケート株式会社 | IT技術教育とビジネススキル教育をグローバルに展開 |
| 株式会社AVILEN | AI開発と人材育成をワンストップで提供 |
それぞれの企業が行っている研修について詳しく見ていきましょう。
株式会社キカガク

| 研修費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 提供している主な研修 | 企業向け生成AIブートキャンプ、生成AI実践メソッド研修など(オンライン) 企業向けカスタマイズ 研修AI・データサイエンススキルの可視化・育成支援 |
| 導入実績 | 住友重機械工業株式会社 農林水産省 株式会社セブン-イレブン・ジャパンなど |
| 設立年月日 | 2017年1月17日 |
| 会社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F |
キカガクはAI・機械学習領域に特化した教育や研修事業を展開する企業です。企業のDX推進やAI人材育成を支援するパートナーとして、多くの法人研修の実績があります。
同社の強みは、カスタマイズできる研修プログラムです。受講者のスキルレベルや自社の業務課題に応じてカスタマイズできるため、現場で活用できる実践的な研修が可能です。
研修プログラムは基礎から実践まで段階的に学べる構成で、非エンジニア層からエンジニアまで幅広い層に対応しています。e-ラーニングも充実しており、時間や場所を選ばずに学習できる環境が整っている点も魅力です。
トレノケート株式会社

| 研修費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 提供している主な研修 | AI基礎・入門研修 AI企画研修 AI開発・実践研修 AI・データサイエンス分野の法人向け研修 |
| 導入実績 | 第一三共株式会社 東亜建設工業株式会社 サッポロホールディングス株式会社など |
| 設立年月日 | 1995年12月6日 |
| 会社所在地 | 〒163-6020 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー20階・27階 |
トレノケートは、IT技術教育とビジネススキル教育を柱に、法人向け研修ソリューションをグローバルに展開している企業です。
同社の強みは豊富な研修実績と、世界各国で展開するグローバルな研修コースです。質の高い公式トレーニングを提供しており、講師の高い教育品質と万全のサポート体制も整っています。
また、IT教育分野で長年の実績を持つことも同社の大きな強みです。製造業から自治体まで多岐にわたる業種・企業規模で研修実績を重ねており、知見に基づいた最適な研修プログラムを提案してくれます。
株式会社AVILEN
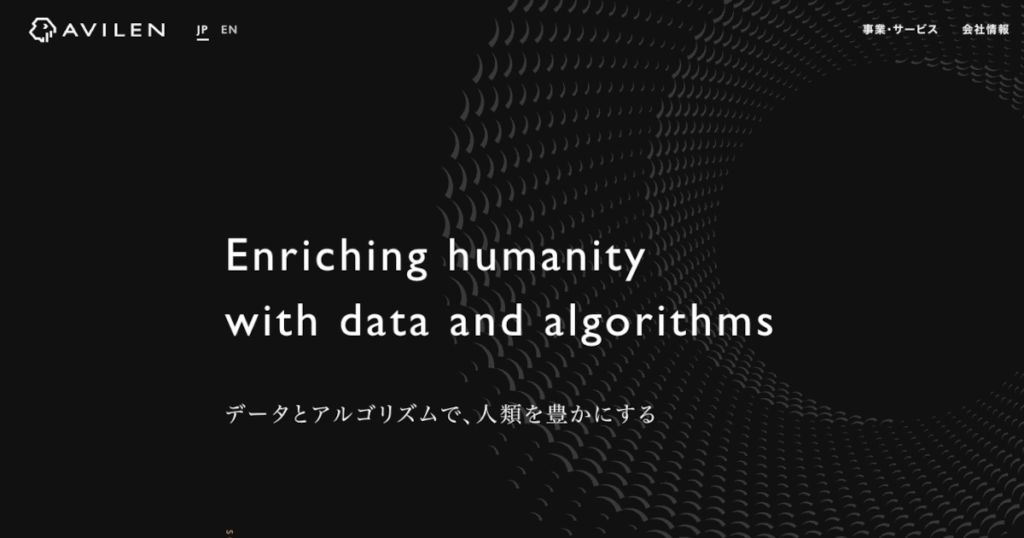
| 研修費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 提供している主な研修 | 生成AIリテラシー研修 ChatGPT研修 生成AI活用研修 実践プロンプトエンジニアリング研修 |
| 導入実績 | 株式会社大塚商会 株式会社クレハ 三菱UFJ信託銀行株式会社など |
| 設立年月日 | 2018年8月15日 |
| 会社所在地 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9F |
AVILEN(アヴィレン)は、AI人材育成支援とAI搭載ソフトウェア開発をワンストップで提供している企業です。
強みはAIソリューション開発の知見を研修に活かしている点です。教育サービスだけでなく、実際にAIソリューションを開発・提供しているため、実務に直結した生きたノウハウを提供できます。
多数の導入実績があり、戦略策定からAI導入・内製化まで一気通貫で支援できることも同社の大きな強みです。質の高いカリキュラムと実践的な演習には定評があり、生成AI・ChatGPT活用研修にも注力しています。
AI研修とは?
AI研修とは、人工知能(AI)の基本知識や活用スキルを体系的に学ぶためのプログラムです。
専門知識の習得だけでなく、AIを使いこなして業務効率化や新規事業創出につなげる実践的な知識を身につけることに重点が置かれています。
AIの進化により、AI活用の必要性はITエンジニアだけでなく営業や企画、人事などの部門にも急速に広がっています。
それぞれの社員がAIリテラシーを身につけることで業務スピードが上がり、企業の競争力の強化が可能です。
AI研修が注目される背景
AI研修の注目度が高まっている背景には、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の加速と、AIの業務活用が急速に進んでいる現状があります。企業が競争力を強化するには、AIを理解し活用できる人材の育成が不可欠です。
AI人材のニーズは、あらゆる業種で高まり続けています。AIツールを操作できるだけでなく、AIの特性を理解した上で業務改善や新規事業創出に活かせる人材が求められています。
また、デジタル人材育成が政府の重要な方針にもなっている点も大きな要因です。経済産業省や文部科学省などでAI教育を推進しており、企業へのAI教育支援も進んでいます。
社会的・産業的な動向も重なり、AIリテラシーの向上が企業の競争力を左右する時代となり、AI研修の必要性が一段と高まっています。
AI研修を選ぶときのポイント

AI研修を選ぶときのポイントは以下の通りです。
サービスを選定するときの参考にしてください。
目的や課題に合った内容かを確認する
まずはAI研修の目的を明確にしましょう。一般的に、選択すべき研修は達成したい目的によって異なります。
AIの基礎的な理解が目的なら、AIの概念や活用事例を学べるリテラシー研修が向いています。一方で、実践スキルの習得を目指す場合は、Pythonや機械学習ツールを使ったハンズオン型研修が最適です。また、社内でAI活用を推進できる人材を育てたい場合は、プロジェクト設計やデータ活用戦略までを扱う研修を選択すると良いでしょう。
自社の目的と研修内容がズレていると受講の満足度が下がるだけでなく、期待した効果も得られません。事前にAI研修会社とコミュニケーションを取り、カリキュラムの詳細を確認した上で選ぶことが大切です。
対象者のレベルに適しているか確認する
学習効果を高めるためには、受講者のスキルやレベルに合った研修を選ぶことが重要です。初心者向けや中級者向け、技術職向けなど、受講者の現在のスキルレベルを把握した上で研修を選定しましょう。
難易度が高すぎる研修は、受講者が内容についていけず途中で挫折する原因となります。一方で、簡単すぎる内容では新たな学びが少なく、十分な成果が得られない可能性があります。
AI初心者が多い場合は、丁寧なフォロー体制や豊富な演習が用意されている研修が最適です。入門編から応用編まで段階的に学べる体系が整っている研修会社を選ぶと、受講者の成長に合わせてスキルアップできます。
受講形式と学習期間を比較する
受講形式と学習期間も重要な選定ポイントです。AI研修には対面研修やオンライン研修、録画視聴型のeラーニングなど、さまざまな受講形式があります。
学習期間にも短期集中型と長期継続型があります。社員の勤務形態や業務スケジュールに合わせて最適な受講形式を選択しましょう。
また、業務時間内に受講するのと業務時間外に受講するのでは、最適な形式が異なります。無理なく継続できる受講形式を選ぶことが、学習効果を高めるために重要です。
費用と得られる成果のバランスを見る
AI研修を選ぶ際は、研修費用と受講して得られる成果のバランスを判断することが重要です。
実用性の高いプログラムは受講費用が少し高くても明確な成果が期待できるため、費用対効果は高いといえます。反対に、価格の安さだけで選んでしまうと内容が浅く、実務に結びつかないこともあるため注意が必要です。
費用と成果のバランスは、社員人数に受講単価を掛けた総コストと、受講によって得られるリターンを具体的にシミュレーションすることで判断できます。
また、助成金対象となる研修であれば、積極的に活用することも検討しましょう。
講師やカリキュラムの質を確認する
講師とカリキュラムの質はAI研修の成果を左右する重要な要素です。実務経験が豊富で、業界での実績がある講師が担当している研修を選びましょう。
ビジネス現場でのAI活用経験を持つ講師が担当していれば、教科書にはない実践的な知見を学べます。講師の質を判断するには、Webサイトに記載されている講師の経歴や、受講者のレビューが参考になります。
また、カリキュラムが最新のトレンドに対応しているかも重要なポイントです。特に生成AIは進化のスピードが早いため、最新動向を踏まえたカリキュラム設計が不可欠です。カリキュラムの更新頻度や事例の新しさを確認しましょう。
受講後のアフターフォローやサポート体制を確認する
AI研修を受講した後のアフターフォローやサポート体制も、AI研修を選ぶときに注目するポイントです。研修で学んだスキルを継続的に伸ばしていくためには、受講後のフォローやサポート体制が整っている研修を選ぶことが重要になります。
チャットやメールでの質問受付や定期的なフォローアップセッション、追加教材の提供など、学習を継続的に支援する仕組みがあるAI研修はスキルを着実に定着させ、実務での活用にも役立ちます。
また、学習のモチベーションを維持できる仕組みがある研修も効果的です。例えば受講者同士のコミュニティや定期的な成果発表の場などが用意されていると、互いに刺激を受けながら前向きに学習を続けやすくなります。
AI研修の導入にかかる費用

AI研修にかかる一般的な費用は以下の通りです。
目安となる相場と費用を左右する要因について解説します。
一般的な費用相場の目安
一般的なAI研修の相場は、短期の入門講座で1人あたり数万円からです。中期的な実践研修では10万円〜30万円程度が相場です。また、長期プログラムや専門的な内容になると50万円以上の研修もあります。
研修内容や期間、講師の質や教材の充実度、サポート体制の手厚さなどによっても研修費用が変動するので、事前に確認しましょう。
なお、無料で体験できるプログラムを用意している企業もあるため、導入前に体験プランの有無を確認してみるのもおすすめです。
受講形式による費用の違い
AI研修の費用は受講形式によって大きく変わります。オンライン研修は会場費や移動費がかからない分、対面研修と比べてコストを抑えられる傾向にあります。
特に録画視聴型のeラーニングは、一度作成したコンテンツを多くの受講者に提供できるため、比較的リーズナブルな価格設定になっていることが多いです。
一方、対面の集合研修は会場費などのコストが計上されるため、費用は高めになります。しかし、直接質問できる環境や受講者同士の交流による学習効果の高さなど、費用に見合った価値があることが多いです。
また、両者の中間的な位置づけとして、オンラインライブ型の研修も存在します。オンライン型の研修は移動の手間なく、双方向のコミュニケーションが取れるため、費用対効果のバランスが良い選択肢といえます。
対象人数と研修規模による費用
企業向けの研修では、社員の人数や研修規模によって費用が変動するのが一般的です。参加人数が多いほど一人あたりの単価は下がり、個別指導や少人数制の研修では単価が高くなる傾向があります。
少人数制の研修は、講師が一人ひとりに丁寧に指導できるため学習効果が高い一方、コストは相応に上がります。一方、大人数での集合研修は総額が大きくなるものの、一人あたりの負担を抑えられるのが利点です。
そのため、研修効果を最大化したいのであれば、受講人数を増やすことは最善とは限りません。特に実践的な演習を含む研修では、講師がフォローできる人数には限界があります。費用を抑えつつ学習効果を維持できる、最適な人数規模の見極めが重要です。
カリキュラム内容とレベルに応じた費用
研修カリキュラムの内容とレベルもAI研修の費用に直結する要素です。基礎理解を目的とした研修は比較的リーズナブルな価格設定になっていることが多いです。
中級レベルの応用実践を含む研修になると、実際にデータを扱う演習やケーススタディが増えるため費用は高くなる傾向があります。
さらに上級レベルの研修では、高度な技術やツールを使った実践的なプロジェクト型学習が中心となります。研修期間も長期になるため、50万円以上の費用がかかるものも珍しくありません。
補助金や助成金の活用も検討する
AI研修の費用を抑えるために活用できる、国や自治体の補助金や助成金があります。補助を受けることで企業負担を大幅に軽減し、AI人材育成への投資を促進できます。
代表的なのが従業員の職業能力開発に取り組む事業主を支援する制度である「人材開発支援助成金」です。要件を満たせば研修費用の最大75%の助成を受けられます。
他にもAI研修が対象となっている助成金は多くあります。ただし、補助金や助成金の利用には事前申請や一定の要件を満たす必要があり、手続きも細かく定められているため、事前の確認が必須です。
また、研修会社によっては助成金申請のサポートを行っているところもあるため、制度の活用を検討している場合は、事前に対応可否を確認しておきましょう。
主なAI研修の種類
主なAI研修には以下の5種類があります。
詳しい内容を検討する前に、自社に必要なAIスキルについて整理しておきましょう。
AIの基礎知識を学ぶ研修
基礎研修はAIの基本的な考え方や仕組みを理解し、実際のビジネスでの活用方法を学ぶ入門的な研修です。
AI基礎研修はプログラミング知識がない非エンジニアでも、AIの全体像や可能性が理解できる内容になっていることが特徴です。基礎研修でも実際のAIツール操作や簡単な課題解決のシミュレーション演習などを行うこともあります。
基礎研修は社内の共通認識づくりや、企業のAIリテラシーの底上げに適した研修です。経営層から現場の社員までAIの基本を理解することで、後のDX推進がスムーズになります。
プログラミング・データ分析研修
プログラミング・データ分析研修は、より実践的なスキル習得に特化したプログラムです。
プログラミング言語を用いて、AIやデータ分析の基礎的な実装方法を学びます。具体的には、Pythonのライブラリを活用してデータを整理・処理したり、グラフ化して分かりやすく可視化したりする手法などを習得します。
プログラミング・データ分析研修は、実務でのデータ前処理や可視化に対応できるスキルを身につけることを目指しており、エンジニアやデータ担当者に向けた実践的な内容です。
エンジニアやデータ分析担当者だけでなく、マーケティング部門や企画部門でデータを扱う機会が多い企業にも適した研修です。
機械学習・ディープラーニング研修
機械学習・ディープラーニング研修は、AIの仕組みを支える重要な技術を実践的に学べるプログラムです。データからルールや傾向を見つけ出して予測や分類を行う方法を理論から実践まで一通り学びます。
研修ではAIがデータを学習する主要な手法である、教師あり学習や教師なし学習、強化学習など、機械学習の基本を学びます。さらに高度な研修では、画像を認識するのが得意な「CNN」や、文章や時系列データを扱う「RNN」などのAIモデルについての理解度を高めることも可能です。
機械学習・ディープラーニング研修は、より高度なAI開発に携わりたいエンジニアや、自社でAIモデルを内製化したい企業の技術者に適した研修です。
ビジネス活用に特化したAI研修
ビジネス活用に特化したAI研修は、エンジニアではなくビジネス職を対象に、AIを業務や戦略で活かすための知識を学ぶプログラムです。実際のビジネス現場で役立つ知識と発想を身につけることを目的としています。
ビジネス活用型研修の特徴は、AI応用事例を豊富に学べることです。業界別・課題別の具体的な成功事例や失敗事例を通じて、AIの活用法についての理解が深まります。
また、ビジネス特化型の研修は、AIプロジェクトの企画や評価を適切に行うための判断力や理解力も養うことが可能です。そのため、AIモデルの設計や実装などの技術的な部分を外部に依頼する場合でも研修で得た見識が役立ちます。
オンライン型・短期集中型のAI研修
オンライン型・短期集中型のAI研修は、忙しいビジネスパーソンが効率的に学べるプログラムです。1日完結型のセミナーから数週間の集中プログラムまで、さまざまなバリエーションがあり、自分の学習スタイルに合った形式を選べます。
オンライン受講が可能なため、自宅や職場から参加でき、移動時間や交通費の負担がないことが大きなメリットです。録画視聴型であれば自分のペースで学習を進められ、ライブ配信型であればリアルタイムで質問しながら学べます。
仕事と学習を両立させたい場合や、地方在住で対面研修への参加が難しい場合、手軽にAIを学び始めたい方に最適な研修形式です。また、短期間で基礎を押さえられるため、社内の多くの社員に受講させたい場合にも効率的です。
AI研修で習得できる代表的なスキル

AI研修を通じて習得できる代表的なスキルは以下の5つです。
どれも実践でAIを活用するために体系的に身につけておきたいスキルです。それぞれ解説します。
AIの基礎知識とリテラシー
AI研修でまず習得できるのが、基礎知識とリテラシーです。AIの定義や構造、できること・できないことを正しく理解することで、AIに対する誤解や過度な期待を解消し、適切な判断ができるようになります。
AIリテラシーは、技術者だけでなくビジネスパーソン全般に必要なスキルです。AIを使うときや外部に依頼するときの判断、リスクを見極める判断力も養えます。
また、社内で共通認識を持つための教育としてもAIリテラシーの習得は効果的です。経営層から現場スタッフまでが一定のAI知識を持つことで、AI導入やDX推進を社内全体で円滑に進められるようになります。
データ分析・統計スキル
データ分析・統計スキルは業務に活用できる重要なスキルで、専門的なAI研修を通じて身に付きます。
データの前処理や統計についての手法を体系的に学ぶことで、感覚や経験に頼らない、客観的なデータに基づいた提案や意思決定ができるようになります。
データ分析・統計スキルはマーケティングや営業企画、経営企画など、データに基づいた意思決定が求められるさまざまな部門で活用可能です。
分析や統計のスキルは、ビジネスの信頼性と説得力を高められる大きな強みとなります。
Pythonなどのプログラミングスキル
研修プログラムによっては、AI開発やデータ分析に欠かせないPythonなどのプログラミングスキルが学べるカリキュラムもあります。
実際にコードを書いて動かす演習を通じて、基本的なプログラミングの知識や技術を習得でき、エラー対応やデバッグ方法の習得も可能です。
さらに、実務で必須のライブラリを使いこなせるようになると、データの読み込み・加工から分析・可視化までの一連の作業を効率的に行えるようになります。
研修内容によってはプログラミング未経験者でも、数ヶ月で実務レベルのプログラミングスキルの習得が可能です。
機械学習・深層学習の実装力
機械学習・深層学習の実装力は、AI研修の中でも特に専門性の高いスキルです。
データからパターンを学び、予測や分類を行う機械学習の基本理論と実装方法を体系的に学ぶことで、実際に動くAIモデルを構築できるようになります。
また、業務で扱うデータを想定した課題設定からモデル構築、評価、改善までの一連のプロセスを体験することで、実務へ応用できる力も養われます。
機械学習・深層学習の実装力は、企業がAIプロジェクトの内製化を推進する上で不可欠なスキルです。
ビジネス課題解決への応用力
ビジネス課題を解決できる応用力は、AI研修で身に付けられる重要なスキルです。研修では知識だけではなく、学んだAIスキルを業務改善や意思決定に活かせる実践力の養成を重視します。
実際の事例やケーススタディから学ぶことで、自社の課題をAIで解決する思考力を養うことが可能です。たとえば、売上予測による在庫最適化の事例や顧客分析による離反防止対策、業務を自動化して生産性を向上させるメソッドなどについて、効果的なAIの活用方法を考案できる可能性が高まります。
ビジネスシーンでのAI活用事例から学ぶことで、具体的な応用イメージが湧きやすくなり、実務での活用にもつながります。知識の習得だけではなく、実務を前提とした思考力を身につけることがAI研修の大きな目標です。
AI研修を受けるメリット

AI研修を受講するメリットは以下の4つです。
比較検討する際には上記を意識して最適な研修を選びましょう。
AIリテラシーの向上
AI研修のメリットの1つは、IT職以外の社員もAIのリテラシーを身につけられることです。営業や企画、人事や経理など幅広い職種の人がAIの基本を学ぶことは、企業がDXを推進するときの土台となります。
また、AIについて社内で共通言語を持てる点もメリットです。AIの活用方法を具体的にイメージできることで、建設的な議論ができるようになります。
AIに関する基本スキルを身につけ、思考力や提案力、判断力のベースラインが向上することは組織全体の成長力にもつながります。
業務効率化と生産性アップ
AIの仕組みや活用方法を習得することで、業務を自動化して省力化が可能になります。定型的なデータ入力作業やレポート作成など、これまで人手で行っていた単純作業をAIに任せることで大幅な時間短縮が可能です。
また、AIによってデータ集計や分析にかかる時間も大幅に削減できます。例えば、Excelで何時間もかけていた作業が、Pythonのスクリプトを使えば数分で完了するケースも少なくありません。
削減できた時間を使って、より創造的で付加価値の高い業務に集中できます。社員一人ひとりの生産性が向上することで、企業全体の競争力が強化されます。
キャリアアップや市場価値の向上
キャリアアップや市場価値が向上することもAIスキルを習得するメリットです。
多くの業界において、AIリテラシーを持つ人材が高く評価されるようになっています。エンジニア以外の職種でもAI研修で身につけたスキルを活用することで活躍の場が広がります。
また、AI研修は自己投資としての価値が高いため、転職・昇進のチャンスを広げられることも大きなメリットです。
身に付けたAIスキルは研修の修了証によって客観的に証明できます。また、研修で作成したプロジェクトや分析結果を具体的な成果物としてポートフォリオに示すことで、実績として示すこともできます。
AI研修は、個人の市場価値とキャリアの可能性を高める大きなチャンスです。
企業全体のDX推進に貢献
企業全体のDX推進力が高まることも、AIリテラシーを身につけるメリットです。研修を通じて社員にAIへの理解と前向きな姿勢が生まれることで、新しい取り組みに対する抵抗感が減り、DX導入をスムーズに進められるようになります。
また、現場と経営の橋渡しとなる人材を育てやすくなることもAI研修を実施するメリットです。技術部門だけでなく、企画や営業などのビジネス部門もAIを理解することで、共通の視点でプロジェクトを進めやすくなります。
研修で得られた知見を元にAIを導入し、成功事例が社内で共有されることで、さらなるAI活用の機運が高まり、企業全体の競争力強化につながっていきます。
【まとめ】自社に合ったAI研修を選んで社員のAIスキルを高めよう
AI研修は社員のスキル向上と企業の競争力を強化させるために優先度の高い施策です。
ChatGPTなどの生成AIが登場したことで、AIは一部の専門家だけのものではなく、すべてのビジネスパーソンが活用する必須のツールとなりました。今こそ体系的な研修を通じてAIリテラシーを高める絶好のタイミングといえます。
社内展開や応用プロジェクトへの活用も視野に入れながら、継続的に学べる環境を整え、AI人材の育成と企業のDX推進をさらに加速させましょう。